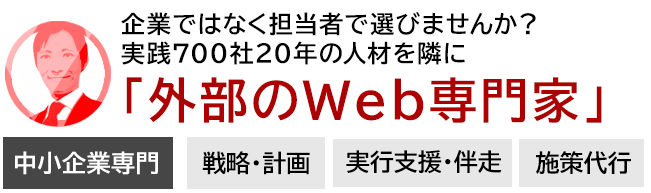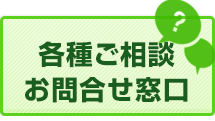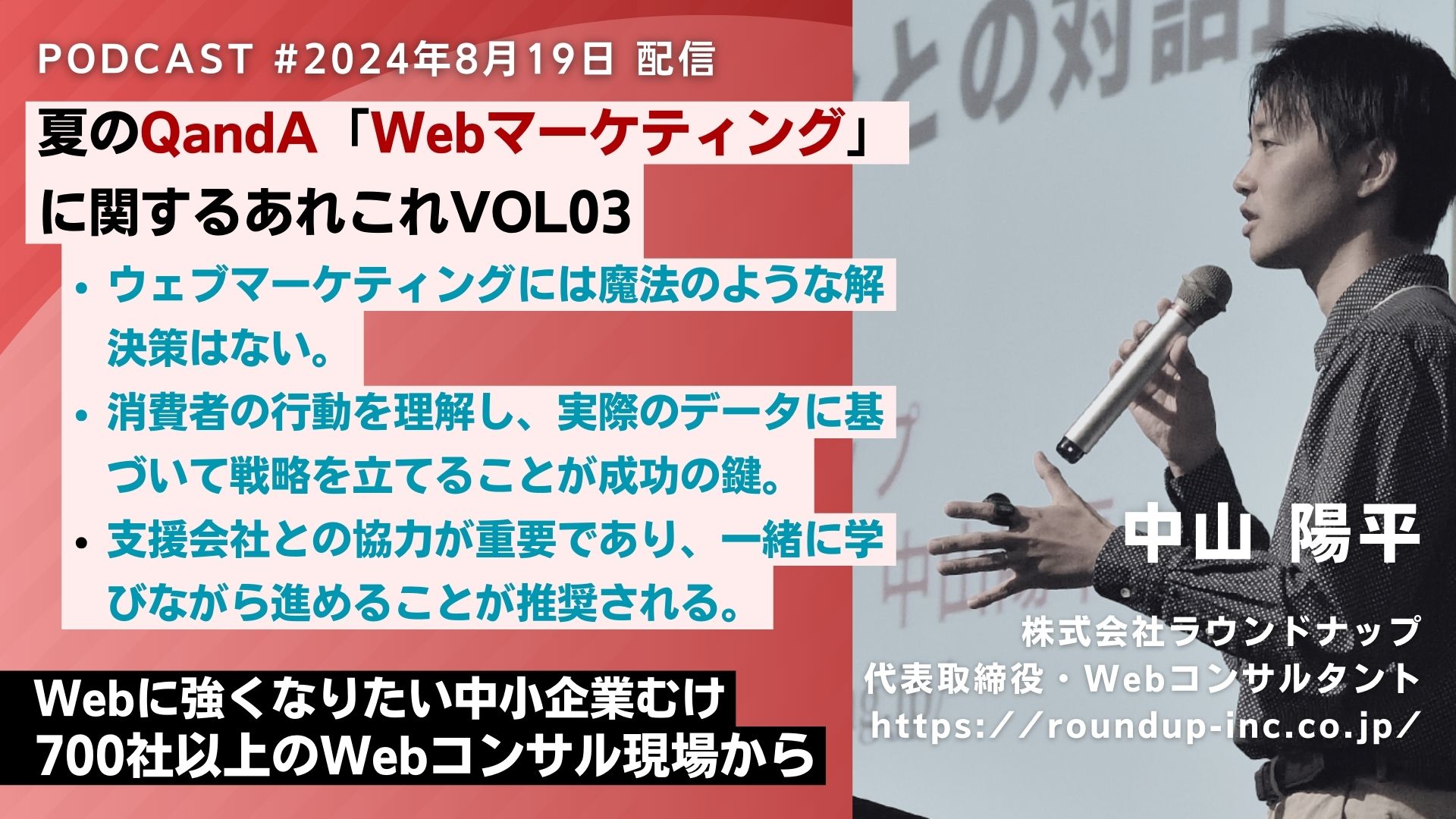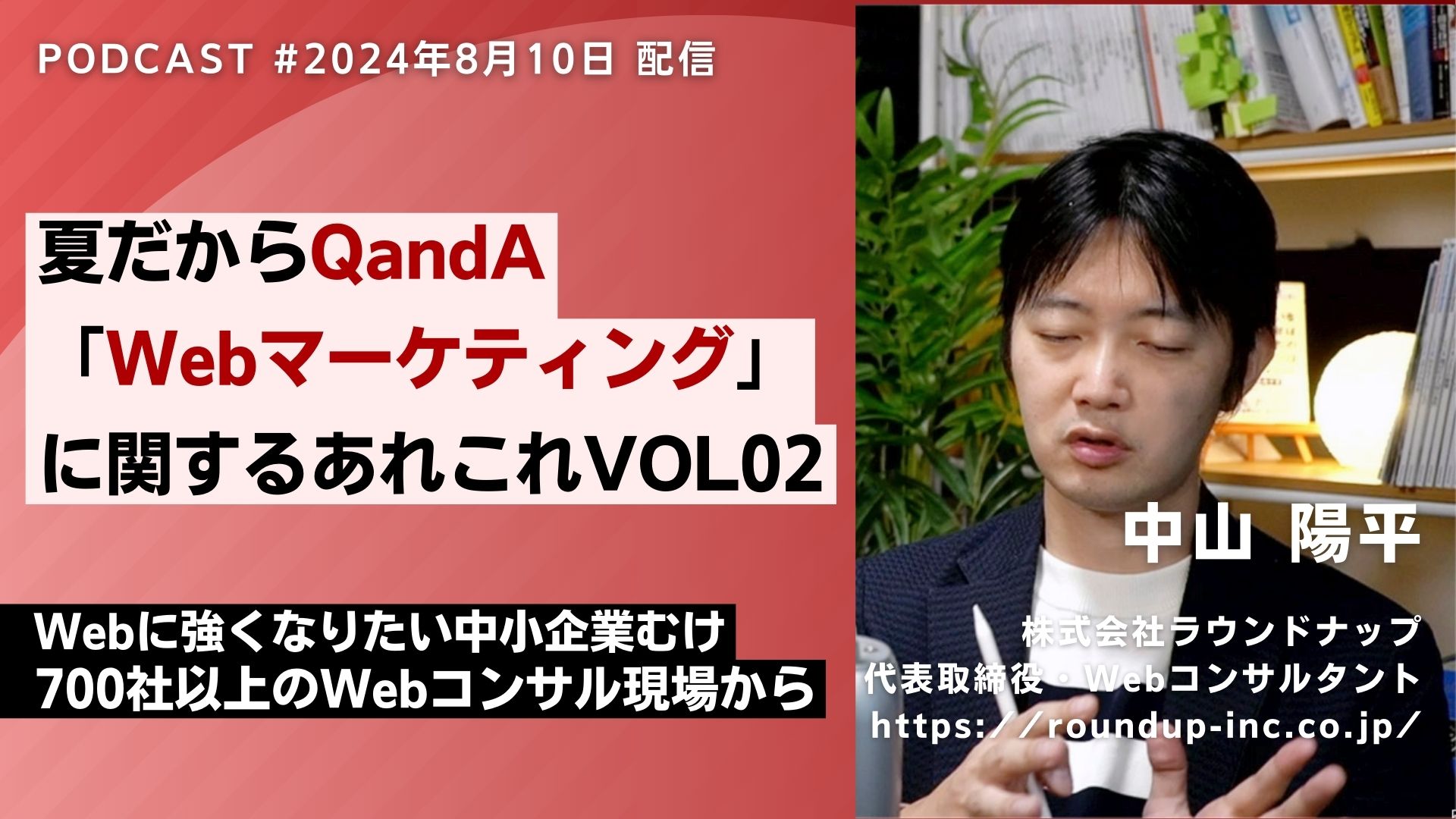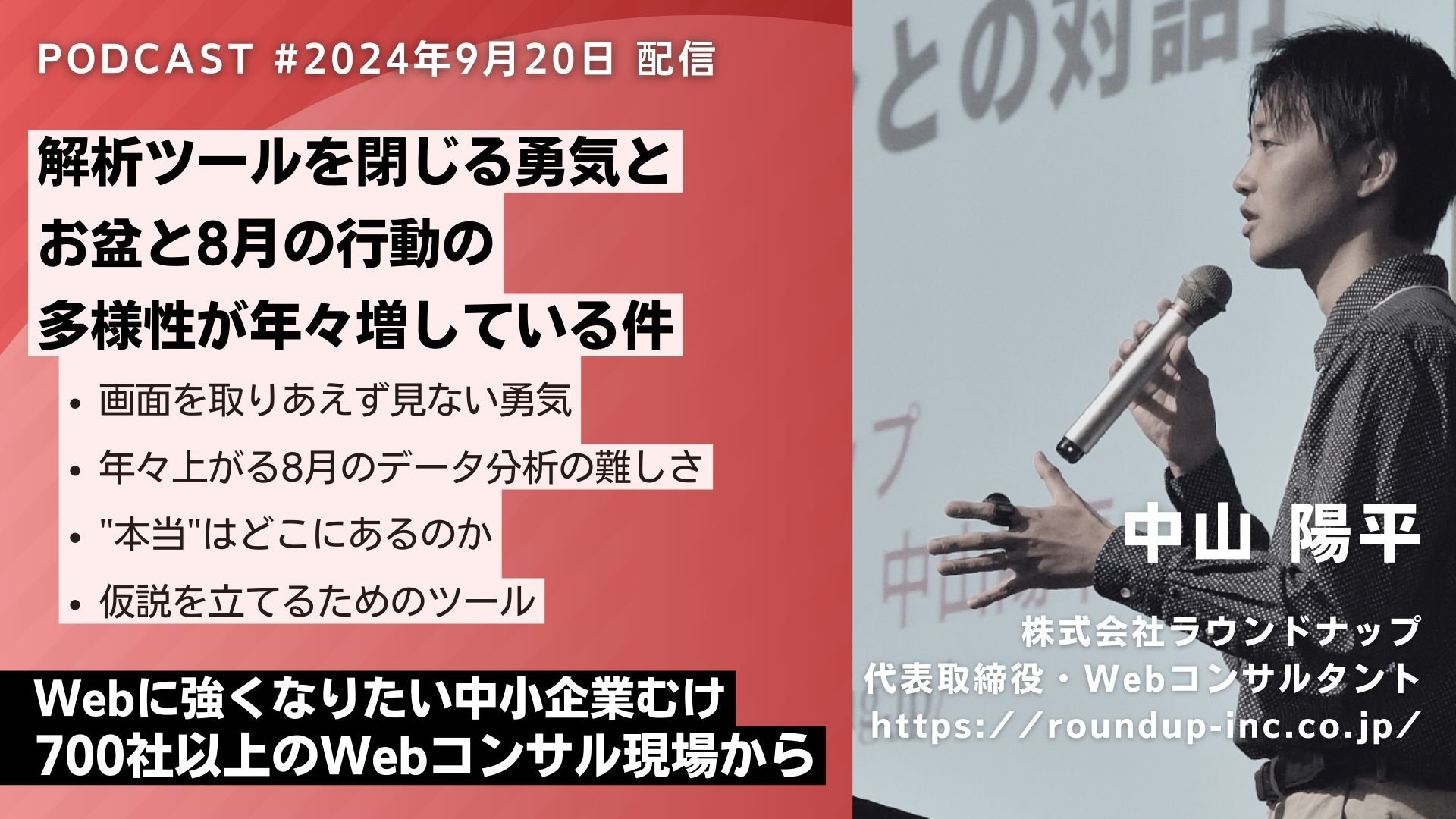Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
Webマーケティングの「最初の一歩」とは何か
この記事を読むと分かること
- 「Webマーケティングの最初のステップ」を、ツールやテクニックではなく「お客様の意思決定プロセス」から考える視点
- カスタマージャーニーマップやペルソナだけに頼り切ると、現実とズレやすい理由と、その代わりにどこを見ればよいか
- 支援会社(制作会社・代理店・コンサル)との付き合い方と、最終的に独り立ちしていくための考え方
- Webマーケティングで「まず入れておきたいツール」と、「ツール導入で失敗しないための考え方」
- 成果を出している会社に共通する、現場のスタンス
いきなり「これをやればいい」という処方箋を探すのではなく、自分の会社とお客様の状況から、一緒に考えていくための材料として読んでもらえればと思います。
「Webだから何か特別」がスタート地点になると迷子になる
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。よくいただく質問の一つに、「Webマーケティングを行う際の最初のステップは何ですか」というものがあります。
この質問の背景には、どこかで「Webには何か特別な手法があって、それを使えば一気に集客できるのではないか」という期待があることが多いです。特に、広告費が直接は見えづらいSEOやSNSのような施策には、そういったイメージがつきまといやすいところがあります。
結論から言うと、「Webマーケティングを行う際の最初のステップ」という形の、万人共通の答えはありません。
Webとリアルを分けて考えること自体が現実的ではなくなっている
今の私たちは、ほとんど常にスマートフォンを持ち歩き、いつでもインターネットに接続して情報を得ています。いわゆる「ユビキタス」な環境の中で暮らしています。
この状況で、「ここからがWeb」「ここからがリアル」と線を引いて考えること自体が、現実の行動とあまり合わなくなっています。
皆さん自身の行動を思い返してみてください。
- 「今からWebを使うぞ」と意識してからスマートフォンを触る
- 「今はWebではなくリアルだ」と意識してから店舗に行く
こういった区切りを意識することは、ほとんどないはずです。実際には、日々の生活の中で、
- 情報を探すときはこのサービスを使う
- 詳しく調べるときはこの媒体を見る
- 人や会社を見つけるときはこういう探し方をする
といった、自分なりの「習慣」があるだけです。その中に、自然にWebもリアルも入り混じっています。
それは、そのままお客様側でも同じです。年代や趣味・嗜好、業界などによって多少の違いはあっても、基本的には「Webとリアルをきれいに分けて行動している人」はほとんどいません。
カスタマージャーニーマップやペルソナがそのままでは使いづらくなっている理由
ここでよく出てくるのが、カスタマージャーニーマップやペルソナという考え方です。
- カスタマージャーニーマップ:
ある人が意思決定をするときに、どんな情報や接点に触れ、最終的に購買に至るのか、その流れを可視化するもの - ペルソナ:
代表的なお客様像を1人の具体的な人物として設定し、その人を基準に考えるためのモデル
これらは今でも役に立つ場面がありますが、以前のように「きれいな一直線のモデル」として使おうとすると、現実とズレやすくなっています。
Googleが示している「バタフライ・サーキット」や「パルス消費」という考え方でも説明されているように、今の消費者は、
- 一気に調べて、比較して、決めて、すぐ買う
という、まっすぐなプロセスをたどることが減っています。
私たちは普段から「損をしたくない」「きちんと自分で考えたというアリバイを作りたい」という気持ちを持っています。その結果として、
- いろいろな候補を一度にたくさん考え始める
- 少し考えては、別のことを考え始める
- あるきっかけでまた思い出して、調べ直す
といったことを、頭の中で何度も繰り返しています。
この、深掘りすることと一旦忘れることを行ったり来たりする動きが、「バタフライ・サーキット」のイメージです。その中で、ふとしたきっかけで「そういえば、あれ欲しかったんだよな」と強く意識が戻り、一気に購買に踏み切る瞬間が生まれます。これが「パルス消費」です。
こういう前提に立つと、従来の「認知→関心→比較→検討→購買」ときれいに並んだカスタマージャーニーは、現実の動きと合わないケースが増えてきます。途中からいきなり始まったり、急に最初に戻ったりするので、「一枚の絵」として描いても、その通りには動いてくれません。
ペルソナも同じで、「典型的なお客様」を一人にまとめてしまうと、どうしても脳内ペルソナ、つまり自分の頭の中だけで作った仮想のお客様になりがちです。
最初のステップは「お客様の解像度を上げること」
こうした前提を踏まえると、「Webマーケティングの最初のステップは何か」という問いは、次のように言い換えられます。
「自分たちが来てほしいお客様が、どうやって情報を集め、どんなタイミングで、何をきっかけに行動しているのかを、できるだけそのままの形で理解すること」
ここで大事なのは、
- 自分の頭の中にいる「理想のお客様」ではなく
- 実際に存在している「リアルなお客様」
の考え方を知っていくことです。
そのためには、
- 実際のお客様に、どうやって自社を見つけたのかを丁寧に聞く
- 同じ属性のお客様が集まる場所と仲良くなり、日頃どう考えているのかを観察させてもらう
といった一次情報(生の情報)を集めていくことが、何よりも重要になります。
つまり、「Webマーケティングだからこうしよう」ではなく、
- まずお客様の現実の行動を知る
- その上で、Web・リアルを問わず「自分たちができること」を考える
という順番で考えていくことが、「最初の一歩」にあたるということです。
戦略づくりも「最初の一歩」と本質は変わらない
「Webマーケティングの戦略をどう立てればよいか」という質問
最初の質問とよくセットで聞かれるのが、
「どのようにして効果的なWebマーケティング戦略を立てることができますか」というものです。
言葉としては「戦略」となっていますが、多くの場合、頭の中でイメージしているのはWebマーケティングの施策です。つまり、中身としては「最初のステップは何ですか」という質問とあまり変わりません。
「効果的な戦略」は、ある程度やってから見えてくる
ここでポイントになるのが、「効果的な」という言葉です。これは多くの場合、
- できるだけ少ない労力で、できるだけ大きな成果を出したい
という気持ちの表現です。その気持ちは、経営者としてもよく分かります。
ただ、本当に意味のある「効率の良さ」は、ある程度しっかり取り組んでいき、
- 自分たちの事業の特性
- お客様の動き方
- どの施策がどう効きやすいか
といった「引き出し」が増えてきたあとに、初めて見えてくる部分が大きいです。
人間を相手にした仕事や、集団を相手にした仕事は、やはり考えることが必要です。「過程はどうでもいいから、アウトプットだけ欲しい」という種類の仕事とは違います。
ですから、「最初から効果的な戦略だけを選びたい」と考えすぎると、かえって大事なところを見落としてしまうことがあります。まずは、お客様をよく知ることと自社で考えることを避けない、というスタンスが必要です。
支援会社との付き合い方と「独り立ち」までのイメージ
最初は「引き出し」がほとんどゼロから始まる
では、お客様のことを理解して、「このあたりをWebでやるのが良さそうだ」というところまで来たとします。
そこで出てくるのが、
- 具体的に何をどうやって実現するのか
という問題です。
事業としてWebマーケティングを始めたばかりの段階では、やりたいことに対しての「手段の引き出し」は、ほとんどゼロに近いはずです。
この段階で頼りになるのが、
- Web制作会社
- 広告代理店
- Web・マーケティングのコンサルティング会社
といった支援会社です。そこには、
- 「それなら、こういうやり方もありますよ」
と提案できるような、たくさんの引き出しがあることが期待されます。
「ラーニングさせてくれる支援会社」と組む
ここで重要なのは、一緒に学ばせてくれる支援会社を選ぶことです。
「なぜ、そのやり方なのか」「他にどんな選択肢があるのか」という部分を、
- きちんと説明してくれる
- 質問すると、丁寧に答えてくれる
という関係を築けるかどうかが、その後の伸びに大きく関わってきます。
逆に、自分たちには何をしているのかよく分からないまま、全部お任せになってしまうような形は、長い目で見るとおすすめしづらいです。
どこまで自社でやるかは「会社の文化」によって変わる
ラーニングと実行を支援会社と一緒に進めていくと、少しずつ自社の中にもノウハウがたまっていきます。
その先の姿としては、大きく分けて二つあります。
- 自社が中心となって回す形(例:自社8割・支援会社2割)
- 支援会社との二人三脚を続ける形(例:自社3〜5割・支援会社5〜7割)
どちらが良いかは、その会社の
- 企業文化や風土
- 人材がどれくらい確保できているか
- 経営者や、社内の空気を作っている人のスタンス
によって変わります。
規模が小さい会社ほど、経営者やごく少数のキーパーソンの考え方に左右される部分も大きくなります。私自身も、現場でお話を伺いながら、
- この会社はどうやったら動きやすいか
ということを毎回読み取りながら進めているので、「この形が正解です」とは言い切れません。
最終的には「独り立ちできる」状態を視野に入れる
とはいえ、ラーニングと施策の実施を並行して進めていき、最終的にはある程度独り立ちできるようなモデルを目指すのは、一つの良い方向性です。
人材が確保できていて、社内の協力も得やすいのであれば、
- 自社主導で進める割合を8割
- 支援会社に相談する割合を2割
といった形を目指すのも良いでしょう。
一方、事情があってそこまで自社で抱え込めない場合でも、「学びながら進める」前提で、3対7や5対5くらいのバランスで支援会社と一緒にやっていくという考え方も十分ありです。
大事なのは、「よく分からないけれど、任せておけば何とかなるだろう」という形ではなく、
- 自社としても理解しながら、できることは増やしていく
というスタンスを持ち続けることです。
Webマーケティングに必要なツールは何か
ツールは「星の数ほど」あるが、全部は使えない
三つ目の質問が、
「実際にWebマーケティングを行う際に必要なツールは何ですか」というものです。
これも、実際に現場でとてもよく聞かれます。
Webやデジタル関連のツールは、本当に星の数ほどあります。カテゴリだけ見ても、
- アクセス解析ツール
- 検索エンジン経由の流入を見るツール
- ヒートマップやマウストラッキングなどの行動観察ツール
- チャットボット
- BIツールやダッシュボード系のツール
- SEO支援ツール
- 広告運用支援ツール
- SNSの投稿・分析ツール
- コンテンツ作成を支援するツール
など、挙げればきりがありません。
ただ、現実的には、どの分野もいくつかの大手ツールに集約されていることが多く、マイナーなツールが長く生き残るのは難しい世界でもあります。
まずは「最低限押さえておきたいツール」だけで十分
そのうえで、「これはほとんどのサイトで入れておいた方がよい」というツールは確かにあります。
- アクセス解析ツール
例:Google アナリティクス 4(GA4)など - 検索エンジン経由の流入を把握するツール
例:Google Search Console(サーチコンソール) - 定性分析ツール(ヒートマップ・セッション録画など)
例:Microsoft Clarity、Crazy Egg、Lucky Orange など
このあたりを入れておけば、まずは「どのくらい見られているのか」「検索経由でどう来ているのか」「ページのどこでつまずいていそうか」といった基本的なことは見えるようになります。
それ以上に何かツールを入れるかどうかは、「何をするか」が決まってからで大丈夫です。
ツール導入の順番は「目的 → 改善のサイクル → 必要なツール」
ツール導入の考え方としては、
- まず「何を実現したいのか」「何を改善したいのか」をはっきりさせる
- そのために、どんな情報があれば改善のサイクルを回せるかを考える
- その情報を得るために、必要なツールを選ぶ
という順番をおすすめします。
この順番を逆にして、
- 「良さそうだから、とりあえず入れてみる」
という形でツールを導入すると、
- 誰も見ないまま放置される
- サイトが重くなる
- 料金だけがかかる
といったことになりがちです。
無料ツールでも同じで、「無料だから」とりあえず入れてしまうと、かえって真剣に見なくなることがよくあります。親に買ってもらったものほど大事に使わない、という感覚に近いかもしれません。
高額ツールの「サンクコスト」に縛られない
特に注意したいのが、高額なツールをいきなり導入するケースです。
高いお金を払ってツールを導入すると、
- 「せっかく高いお金を払ったのだから、何とかして使い切らないと」と考えてしまう
という「サンクコスト(埋没費用)」の心理が働きやすくなります。
その結果、本来やりたかったことではなく、
- ツールを使うこと自体が目的になってしまう
という本末転倒な状態になりかねません。
ツール提案を受けたときに、遠慮せず質問する
制作会社や代理店、コンサル会社、フリーランスなどから、
- 「このツールを入れた方がいいですよ」
と提案されることもあると思います。
そのときには、遠慮せずに、しつこいくらい質問して良いところです。
- なぜ、そのツールなのか
- 他の選択肢と比べて、何が違うのか
- 自分たちはどこまで使いこなせるのか
- 自分たちで使えない部分は、そのツールを使って何をしてもらえるのか
こういったことをしっかり聞いていくと、相手の本当の意図も見えやすくなります。
ツールによっては、開発元と紹介契約を結んでいて、紹介側に報酬が入るようなケースもあります。それ自体が悪いわけではありませんが、身の丈に合わない高額ツールを導入してしまうリスクもあるので、なおさら「なぜそのツールなのか」を確認しておくことが大切です。
デジタルが苦手でも、質問はした方が良い
デジタルやWebが得意ではないと感じていると、
- 質問するのが申し訳ない
- 説明してもらうのが気が引ける
- もう分からないから、考えるのが面倒になる
といった気持ちが出てきやすいです。
ただ、学び方として効率が良いのは、
- 質問する → 回答を聞く → さらに質問する
というやりとりを重ねることです。ツール導入の場面は、その良い機会にもなります。
ツールは本当にたくさんあり、開発費も高くつきます。環境の変化も早く、為替レートの影響で海外ツールが割高になることもあります。だからこそ、「目的から入って、必要なものだけを選ぶ」という姿勢を大事にしてもらえればと思います。
成果を出している会社に共通するスタンス
「最初に何をやればいいか」を即答されるのは危ないサイン
セミナーなどで、
- 「Webマーケティング、最初に何をやればいいですか」
と質問したときに、皆さんのことをほとんど知らない会社が、
- 「まずはこれをやりましょう」と即答してくる
という場面があったとしたら、少し注意した方が良いかもしれません。
もちろん、特定の業界にものすごく詳しくて、典型的なパターンが頭の中にある場合など、例外もあります。ただ、多くの場合は、
- 地域や商圏、業態によって、効果的な施策が大きく変わる
のが実情です。特に地域商圏では、その傾向が顕著です。
ですから、
- 「聞いてみなければ分からない」
というのが正直なところです。
現場リサーチにもコストがかかる
「現場を見れば分かるのでは」と考えられることもありますが、実際には、
- 客先への同行
- リサーチそのものの実施
には、それなりのコストがかかります。
最初からそこまで踏み込んだリサーチをするのは、現実的に難しい場合も多いです。だからこそ、日頃から皆さん自身がお客様の情報を集めておくことが、あとで効いてきます。
一緒に頑張る気持ちを持っている会社が、安定して成果を出している
私自身の現場の感覚として、安定して売上や問い合わせを得ている会社に共通しているのは、
- 「一緒に頑張ろう」というスタンスを持っている
という点です。
こちらから情報を出すだけでなく、
- 自分たちもお客様の情報を集める
- 施策の意図を理解しようとする
- 分からないところは質問する
といった姿勢を持っている会社は、結果として、安定して成果を出しやすくなっています。
もちろん、事情があってそうなれない会社もありますし、「こうしなければいけない」と言いたいわけではありません。ただ一つ言えるのは、
- Web業界に「魔法のような何か」があるわけではない
ということです。
「これさえやれば一気に変わる」という言い方をしてくる人や会社がいたら、少し慎重になった方が良いかもしれません。
まとめ:Webだからと特別視せず、「お客様の解像度」を上げることから始める
ここまでの話を、あらためて整理すると次のようになります。
- Webとリアルを分けて考えるのではなく、お客様の実際の行動から出発する
- カスタマージャーニーやペルソナは、あくまで補助的なフレームとして扱う
- 最初のステップは、「お客様の解像度を上げること」
実際にどうやって情報を集め、どういう流れで自社や競合にたどり着いているのかを、一次情報として集める - Web・リアルを問わず、「その中で自分たちができること」を考える
- 施策の具体化やツール選びは、その後の話
目的 → 改善のサイクル → 必要なツール、という順番で考える - 支援会社とは「ラーニングさせてくれる関係」をつくり、最終的な独り立ちも視野に入れる
うちのようなコンサルティング会社としても、皆さんから情報をいただけない限り、角度の高い提案をするのは難しいです。お互いに情報を出し合い、一緒に考えながら進めていく。その中で、Webマーケティングはようやく「効いてくる」ようになります。
この文章が、「最初の一歩」を具体的に考えるきっかけになればうれしく思います。
小規模事業者・中小企業専門でWebのコンサルティング・サポート全般を行っている、株式会社ラウンドナップ 代表取締役の中山がお送りしました。何かありましたら、お気軽にご相談ください。
関連リンク
本文中で触れた概念やツールの公式情報です。理解を深める際の参考としてご覧ください。
- パルス消費につながる情報探索とは? バタフライ・サーキットと8つの動機(Think with Google)
- [GA4] 次世代のアナリティクス、Google アナリティクス 4 のご紹介
- Google Search Console の紹介ページ
- Microsoft Clarity(公式サイト)
よくある質問(FAQ)
- Q1. Webマーケティングの「最初の一歩」は結局何をすればいいですか?
- 特定のツール導入や施策から入るのではなく、「来てほしいお客様がどうやって情報を集め、どういう経路で自社や競合にたどり着いているか」を実際に聞いたり観察したりして、一次情報として集めることが最初の一歩です。
- Q2. 効率の良いWebマーケティング戦略を、最初から目指しても良いですか?
- 「少ない労力で大きな成果を出したい」という気持ちは自然ですが、本当に意味のある効率化は、ある程度取り組みを続けて、自社とお客様のパターンや「引き出し」が増えてから見えてきます。最初は、お客様の理解と自社で考えることを避けないスタンスを優先した方が結果として近道になります。
- Q3. Webマーケティングで最低限入れておいた方が良いツールは何ですか?
- 多くのサイトで共通して役立つのは、アクセス解析ツール(例:Google アナリティクス 4)、検索経由の流入を把握するツール(Google Search Console)、ヒートマップやセッション録画などの定性分析ツール(Microsoft Clarityなど)です。それ以外は、やりたいことが決まってから検討すれば十分です。
- Q4. 支援会社からツール導入をすすめられたとき、どう判断すれば良いですか?
- 「なぜそのツールなのか」「他の選択肢と何が違うのか」「自分たちはどこまで使えるのか」「使えない部分は何をしてもらえるのか」といった点を、遠慮せず質問して確認することが大切です。高額ツールほどサンクコストの影響も出やすいので、目的と導入理由をよく確かめましょう。
- Q5. 支援会社とは、最終的にどのような関係を目指すのが良いですか?
- ラーニングと施策実行を並行して進めて、自社にもノウハウがたまっていく状態を目指すのが一つの考え方です。人材や社内の状況によって、自社8割・支援会社2割のように自社主導に寄せる場合もあれば、3対7や5対5で二人三脚を続ける場合もありますが、どちらにしても「学びながら進める」「最終的にはある程度独り立ちできる」ことを視野に入れておくと動きやすくなります。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/