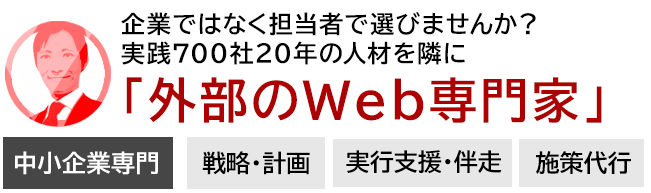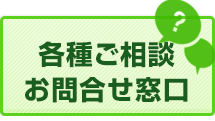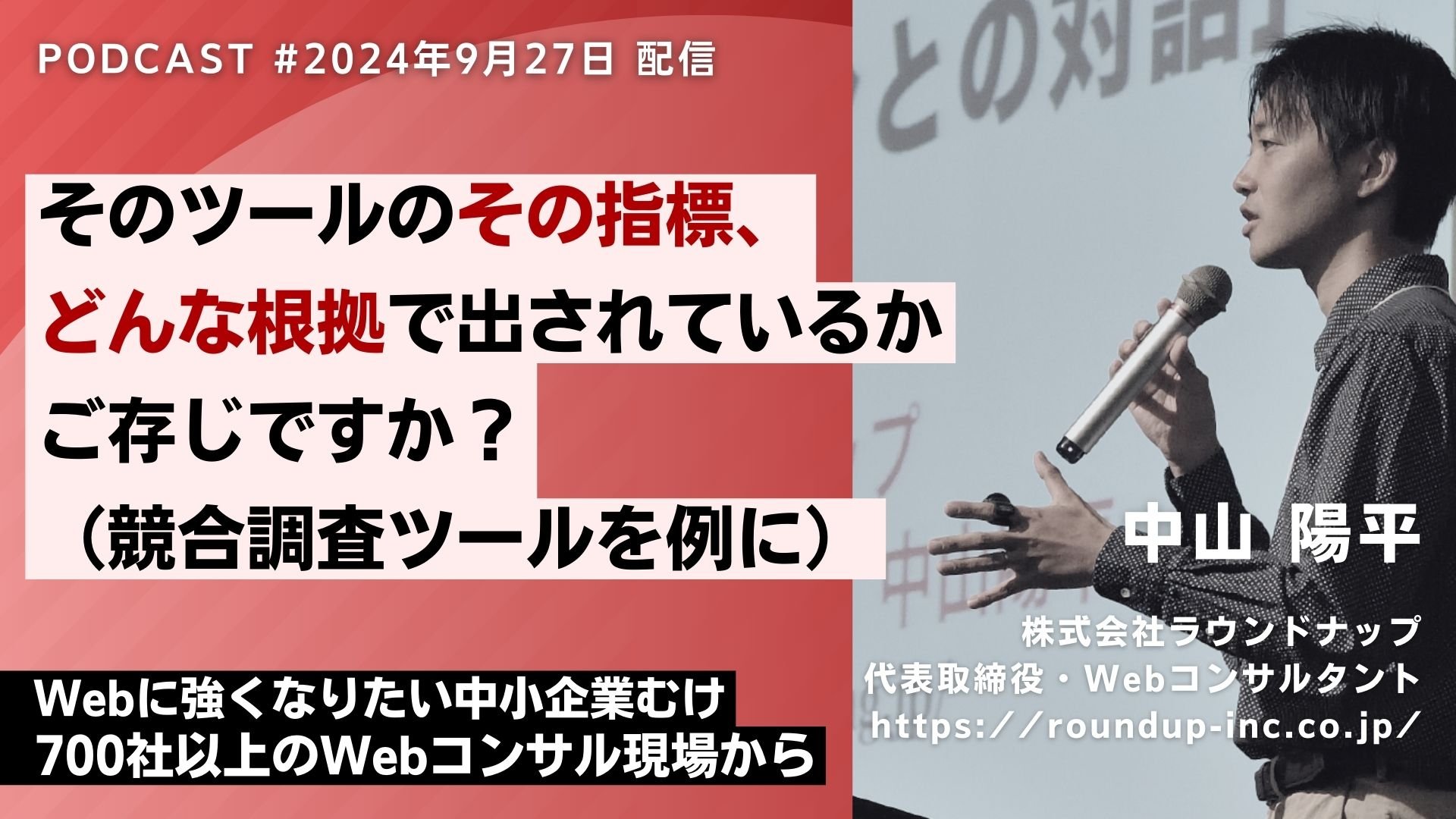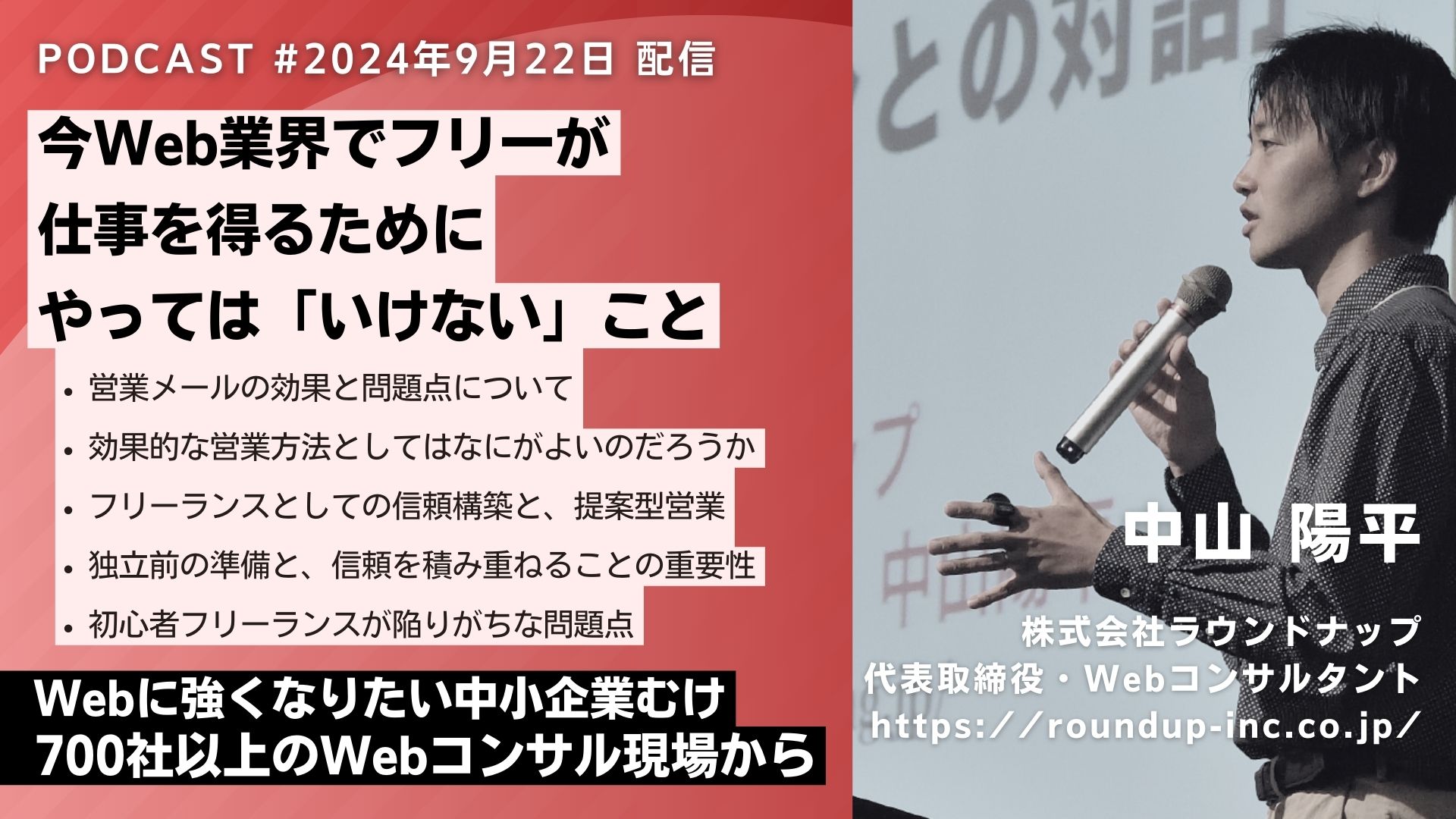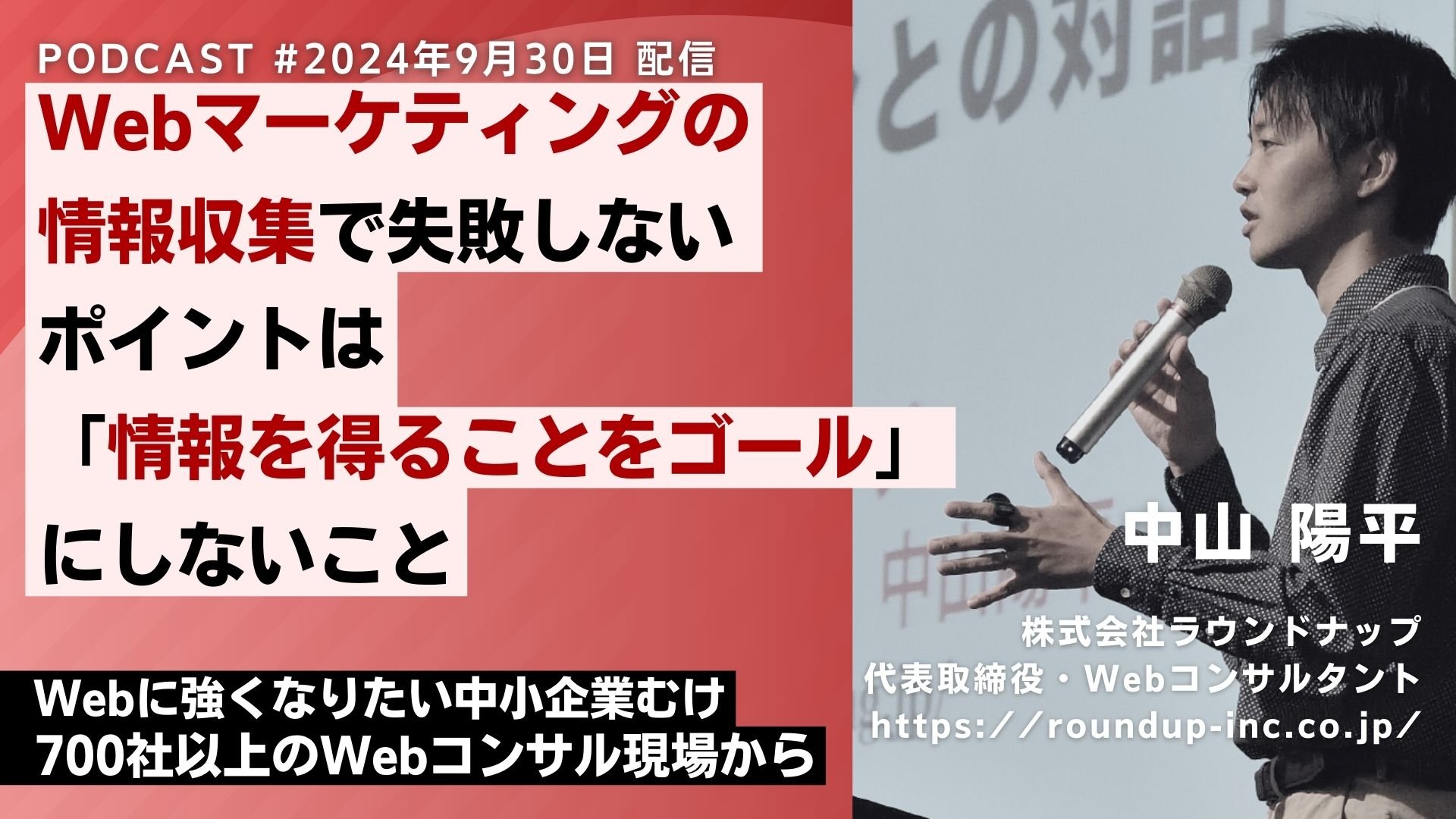Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
サマリー
- 競合調査ツールの数字は、あくまで推定値であり、「実測値」ではない前提で見る
- DR・UR・ARなどのスコアはリンク周りの一部の情報に基づく指標であり、それだけで勝ち負けを判断しない
- オーガニックトラフィックやCPCの推定値は、特にニッチな業界ほど誤差が大きくなるので、提案の根拠としては使いどころを選ぶ
- 数字としてしっかり扱えるのは、自社が直接取得している一次データ(Search Consoleやアクセス解析、広告の管理画面など)である
- ツールは、流入ページやキーワード、広告の有無といった「構造的な情報」や、自社サイトの内部監査に活用する
- まずは普通の商売の原点に戻り、実際にサイトを見たり、お客さんに話を聞いたりすることを大事にする
- 外部の会社に任せきりにするのではなく、自社でも数字の意味を理解して会話できる状態を目指す
- 高額なツールが本当に必要かどうかは、Googleの純正ツールをやり切ったうえで改めて考えても遅くない
今回お話しするテーマについて
今回のテーマは「競合調査ツールの数字、信じて大丈夫ですか? データに振り回されないWeb解析」です。
競合調査ツールやSEOツールが出してくれる数字を、どこまで信じていいのか。
そして、そもそもどう付き合えばよいのかという話をしていきます。
競合調査ツールの全体的な使い方については、過去の第515回「ウェブサイト競合調査ツールの現状と、それを踏まえた上での使い方とは」でまとめていますので、全体像を整理したい場合はそちらも参考にしてください。今回は、その上に少し細かい話を乗せるような位置づけです。
競合調査ツールが魅力的に見える理由と、その落とし穴
なぜここまで期待してしまうのか
競合調査ツールは、とても魅力的に見えます。
たとえば次のようなことが「分かりそう」に見えるからです。
- 競合がどんなキーワードで集客していそうか
- どのページが人気で、アクセスを集めていそうか
- 今、どんなことに力を入れているのか
ビジネスの視点で言えば、競合の動きが見えたら助かりますし、知りたくなりますよね。
そういったニーズに応える形で、コンピューターが自動で推定してくれる分析機能が、SEOツールや競合調査ツールとしてたくさん出てきています。
「数字の根拠」を知らないと、実態とズレた世界を見る
ただ、そのときに「出ている数字の根拠」を押さえていないと、現実とズレた判断をしやすくなります。
たとえば、あるツールで「競合のアクセスが急成長している」と見えていたとしても、実際には大して変わっていない、ということがあります。
数字の作り方を知らないまま眺めていると、競合の「実体」が見えた気になりながら、じつは違う景色を見てしまう危険があるのです。
結論のざっくりしたイメージ
先にざっくりとした結論を言うと、競合調査ツールについては、次のような切り分けで考えると扱いやすくなります。
- 数字系(スコア・トラフィック推定・CPCなど)は、検証した上で「ほどほどに」信用する
- ページのURL・流入キーワード・広告の有無など、数字以外の情報は、そのまま参考にしてよい場面も多い
つまり「数字はほどほど、数字以外は普通に参考にする」くらいの距離感が、現実的だと考えています。
まずはヘルプを見る習慣を持つ
SNSで語られがちな「CPCが高いキーワードを狙え」論への違和感
SNSなどを見ていると、よくこんな話が出てきます。
- 「CPC(クリック単価)が高いキーワードは購買意欲が高い」
- 「だから、そういうキーワードを狙えば売上につながるアクセスが取れる」
こういう話をしている人は、おそらくですが、ツールのヘルプをほとんど読んでいないのではないかなと感じています。
ヘルプや用語集には、本来、その数字がどういう意味で、どのくらい自信を持って出しているのかが書かれているからです。
AhrefsやSemrushなど、海外ツールの情報源
たとえば、最近よく名前が出るのがAhrefs(エイチレフス)です。
日本の代理店ができて、日本語のブログやヘルプも増えています。以前はインターフェースもヘルプも英語だけでしたが、今は日本語で読める情報もかなりあります。
Semrushもそうですが、日本のSEO会社さんが代理店になっていて、日本語でのヘルプや解説が用意されています。
ツールを使うときは、まずこうしたヘルプや用語集を押さえるようにすると、数字に振り回されにくくなります。
AhrefsのUR・DR・ARなどの指標は何を見ているのか
「ahrefs」という名前と、UR・DR・ARのざっくりした意味
少し具体的に、Ahrefsを例にお話しします。
まず名前ですが、私も最初は読み方がよく分からず「アフレフス」などと読んでいた時期がありました。正しくは「エイチレフス」。HTMLにリンクを書くときの <a href="..."> の「href」から来ている名前ですね。
Ahrefsは決して安いツールではありませんが、世界的に見ると「信頼性が高いツール」として支持されています。
そのAhrefsには、UR・DR・ARといった指標があります。
- UR(URL Rating):ページ単位の評価
- DR(Domain Rating):ドメイン全体の評価
- AR(Ahrefs Rank):世界中のサイトの中での順位のようなもの
DRが示しているのは「バックリンクの強さ」だけ
DRについて、Ahrefsの説明では「そのサイトのバックリンクプロファイル(どんなサイトからリンクされているか)の全体的な強さを表す」と明確に書かれています。
リンク元のサイトの質や量、サイズなどを見てスコア化している、ということですね。
つまりDRは「外部からのリンク」に関する評価であって、サイト内のコンテンツや、ユーザーの行動といった内部要因は含んでいません。
内部要因を評価に入れていないからダメ、という話ではなく、指標の役割が最初からそういう設計になっている、ということです。
DRが低い=勝てない、という話にはならない
ここで大事なのは、DRで比較したときに「自社はDRが低いから負けている」「DRが高いから勝っている」と単純に考えないことです。
DRは外部リンクまわりの指標なので、それだけで「検索結果で勝てるかどうか」までは判断できません。
Googleはコンテンツやユーザー行動など、いろいろなシグナルを総合して評価しています。
それを外部のツールが、限られたクローリングデータと匿名データだけで再現しようとすると、どうしても一部の要素に絞った指標になります。AhrefsのURやDR、AR、Mozの指標などは、そういった「一部の要素を切り出したスコア」として見ておいたほうが、使いやすいと感じています。
ヘルプを読むと、ツール側も「これはあくまでバックリンクに関する指標です」というニュアンスをわりとはっきり書いています。
ですので、DRやURなどのランキングは、「目安としてほどほどに見る」くらいがちょうどよいのではないでしょうか。
オーガニックトラフィックの推定値は、あくまで「推定」
オーガニックトラフィック推定値はどう作られているか
競合調査ツールには、推定のオーガニックトラフィックの数字が出るものが多いですよね。
これも、いろいろな場面で「競合のアクセス推移」として使われているのを見ます。
ただ、この数字もあくまで推定値です。
ざっくり言うと、ツール側は次のような情報を組み合わせて数字を出しています。
- ツールが把握している検索クエリの一覧
- それぞれのクエリに対して、どのサイトが何位にいるか
- 月間検索数のデータ
- 順位ごとの推定クリック率
このあたりはAhrefsの用語集やブログにも書かれていますが、「あくまで見積もりであって、実際のアクセス数そのものではない」と自ら説明しています。
ニッチな業界ほど誤差が大きくなる
ツールが把握している検索クエリは、Googleが持っているデータと比べると、どうしても網羅性が低くなります。
しかも、Google自身が「毎月、新しい検索クエリがどんどん生まれている」と言っているくらいなので、ツール側がすべてを追いかけるのは現実的ではありません。
特に、皆さんが関わっている業界がニッチであればあるほど、ツールが持っているデータが薄くなり、推定の誤差が大きくなります。
昔、Ahrefsに日本の代理店ができる前から使っていたのですが、その頃は日本のサイトの数字がほとんどまともに出ないこともよくありました。トラフィックがずっとゼロだったり、急にスパイクしたり。データの元が少ないと、ちょっとした変化が過剰に増幅される、ということですね。
実務で感じた「変動の激しさ」
うちでも昔、競合調査の数字を、別のツールですが毎月PDFにまとめてお渡ししていた時期がありました。
しかし、月ごとの変動があまりにも激しくて、参考にしづらいという感覚が強くなり、今はその形では出していません。
競合の実際の数字を直接見られるわけではないので「精度が悪くなった」とまで言い切ることはできませんが、少なくとも提案資料にそのまま載せるには苦しい変動の仕方になってきた、という印象です。
なので、オーガニックトラフィックの推定値も、「全体の傾向を見る材料」くらいにとどめておくほうが、安全だと思います。
CPC(クリック単価)指標は、さらに不確実
CPCは現場でも絶えず動いている
CPC、つまりクリック単価についても、ツール側は「正確性は低い」といったニュアンスで注意書きを出しています。
これは、実務で広告運用をしている方なら肌感覚として分かるところだと思います。
今の広告運用は、「特定キーワードにいくらで入札する」という固定的なやり方だけではなく、
コンバージョン単価の目標や、いろいろな条件を組み合わせて、かなり柔軟に自動調整が行われています。
そのため、あるキーワードに対しての実際のクリック単価は、短いスパンでどんどん変わります。
「ワンクリックいくら」という形で固定されているわけではなく、状況に応じて動いているものです。
「CPCが高い=売れるキーワード」と決めつけるのは危険
こういう前提がある中で、ツール側が出しているCPCの数字は、もともと無理のある指標です。
データが少ないニッチな領域であればなおさらで、ゼロになったり、急に高額な数字が出たりと、かなり上下します。
「この業界は全体的に単価が高そうだ」「このあたりのキーワードは低めだな」といった傾向を見るには使えますが、
たとえば次のような使い方は、かなり危ういです。
- ある瞬間にCPCが高いキーワードを見つける
- 「ここは売れるキーワードに違いない」と判断する
- そのままSEOの狙い目として決めてしまう
実際にやってみると、こういったやり方はまずうまくいきません。
もし検証したいなら、自分で広告を出し、ランディングページを用意してテストする、という形で確かめたほうが、まだ納得感のある判断ができます。
Ahrefsのサイトを見ても、CPCについては「参考値として見てください」というニュアンスの注釈が書かれています。
ツール側も、すべての有料キーワードを正確にカバーできているわけではない、という前提で出している数字です。
「数字に振り回されない」ための考え方
いったん立ち止まって、数字との付き合い方を見直す
ここまで、
- DR・UR・ARなどのスコア
- オーガニックトラフィック推定値
- CPCの推定値
といった数字について、「どこに限界があるか」という話をしてきました。
もし、今のところこういった数値を当たり前のように参考にしているのであれば、一度立ち止まって、「自分たちの判断に本当に意味があるのか」を振り返ってみるのがおすすめです。
慣れてきた会社さんほど、これらの数字に振り回されているケースをよく見かけます。
そもそも「分からないものは分からない」と割り切る
では、「このツールの数字がダメなら、何で調べればいいのか」という疑問が出てくると思います。
ここで大事なのは、「そもそも分からないものもある」と割り切ることです。
たとえばクリック単価であれば、自分で実験的に広告を出せば、ある程度の感覚はつかめます。
しかし、それ以外の「競合のトラフィックが実際にどれくらいあるか」といったものは、基本的に外からは分かりません。
強いて言えば、キーワード関連で分かる範囲については、Googleの純正のキーワードツールなどの数字をきちんと見る、というくらいです。
「ツールなら何でも分かるはずだ」と期待しすぎるのをやめる、というのが一つのポイントだと思います。
ツールは「数字以外」と「内部監査」に使う
こういう前提を置いた上で、競合調査ツールの使い方を改めて考えると、次のような方向性が見えてきます。
- 数字そのものではなく、流入ページやキーワードの種類、広告の有無など「構造的な情報」を見る
- 自社サイトの内部監査など、本来の得意分野に使う
私はそもそもSEO専門会社ではないということもあり、今は競合調査ツールをそこまで使っていません。
ツールで調べて、その数字をもとに提案書を作るということも、基本的にはしないようにしています。
競合のサイトを見たときに、
- 「こういうキーワードで流入していそうだ」
- 「このあたりのコンテンツを増やしたほうが良さそうだ」
といったことを考える材料として、流入キーワードやページの情報を使うことはありますが、あくまで「数字以外」の部分を中心に見ています。
リアルな競合調査に戻るという発想
お店の世界でやっていることをWebでもやる
競合調査と言うと、ついツールの画面を思い浮かべてしまいますが、もともとリアルの商売で競合を調べるときは、数字を見る前にやることがありますよね。
- 実際にお店に行って、どんな品揃えなのか、どんな雰囲気なのかを見る
- そのお店を使ったことがあるお客さんに話を聞く
こうした「ストレートなやり方」で競合を知ろうとするはずです。
Webの世界でも、本来は同じで、実際にサイトを見たり、サービスを利用した人の声を聞いたりするほうが、ツールよりも多くのものが見えます。
AIツールに「魔法」を期待しすぎない
最近は、AI関連の海外ツールが「今までにない魔法のようなツール」として語られることもあります。
しかし、実際には、どのツールも限られたデータと推定モデルを組み合わせているだけで、特別な裏情報を持っているわけではありません。
華やかに見えるツールに夢を見すぎるのではなく、普通の商売の原点に戻って、目で見て、話を聞いて、考える。
そのうえで、ツールは「できることの範囲を理解した道具」として使っていくほうが、長い目で見ると安定します。
アクセス解析でも「数字から入らない」ほうがうまくいく
この話は、以前からお伝えしている「アクセス解析の数字から入ってはいけない」というテーマと、根っこは同じです。
データを眺めてから「さて、何をしようか」と考えるのではなく、
- まず「こういうふうに攻めたほうがよいのではないか」という仮説を持つ
- その仮説を支えるデータは何かを探す
という順番で考えたほうが、ブレにくくなります。
競合調査ツールについても同じで、「数字がこうだからこうする」のではなく、
「この方向で進めたい、その裏付けとなる証拠はあるか」という考え方で数字を見ると、振り回されにくくなります。
ツールの数字を使う前に、まず自社で検証してみる
自社サイトの数字とどれくらい合っているかを確認する
競合調査ツールをどう扱うかを決めるとき、まずできるのは「自分たちのサイトの数字とどれくらい合っているか」を確認することです。
- 自社サイトをツールに登録する
- Search Consoleやアクセス解析の数字と、ツールの推定値を比べてみる
それで全然合っていないようであれば、その業界ではツールの数字があまり役に立たない、という判断もしやすくなります。
その場合は、ツールの数字部分は参考にしないほうが安全です。
「数字として扱えるのは一次データだけ」と考えておく
「数字としてきっちり扱えるもの」は、基本的に自分たちが直接取得している一次データだけだと考えておくと、最初は安心です。
- Search Console
- アクセス解析ツール
- 広告管理画面の数字
これらは、自社サイトについての一次データです。
それ以外の数字、特に競合調査ツールの数値は、「推定値であり、参考値に過ぎない」として見ておくのが現実的だと思います。
ツール費用と「本当に必要か」の見直し
最後に、お金の話も少しだけ。
海外製のツールは、円安の影響もあり、以前よりもだいぶ高く感じられるようになっています。料金が上がっていく中で、「本当にこのコストをかける価値があるのか」は、改めて考えるタイミングかもしれません。
私の考えとしては、「競合調査ツールは必須ではない」と思っています。
Googleの純正ツールだけでも、できることはたくさんありますし、まずはそこをやり切ってからでも遅くはない、という感覚です。
パートナーとの付き合い方と、自社のスタンス
結局のところ、
- どこかの会社にすべて任せてしまい、自社は考えない
というモデルは、これからますます持ちこたえにくくなっていくと思います。
少なくとも、
- 出てきた数字が何を意味しているのか
- どこまで信じてよい数字なのか
といったことを、自社内でも会話できる状態を目指したほうが、長期的には安心です。
そのうえで、「一緒に考えてくれる」「育ててくれる」パートナーを選ぶことが大事だと感じています。
お問い合わせやご質問について
今回の内容について、「ここをもう少し詳しく聞きたい」「自分のところの場合はどう考えればよいか」といったご質問があれば、気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォームからでも、匿名でも大丈夫です。ポッドキャスト専用のフォームもありますが、少し見つけづらいかもしれないので、通常のお問い合わせフォームから送っていただいて構いません。
中小企業専門でWeb活用のサポート(コンサルティング・制作など)を行っている、ラウンドナップWebコンサルティングの中山が、可能な範囲でお返事させていただきます。
まとめ
- 競合調査ツールの数字は、あくまで推定値であり、「実測値」ではない前提で見る
- DR・UR・ARなどのスコアはリンク周りの一部の情報に基づく指標であり、それだけで勝ち負けを判断しない
- オーガニックトラフィックやCPCの推定値は、特にニッチな業界ほど誤差が大きくなるので、提案の根拠としては使いどころを選ぶ
- 数字としてしっかり扱えるのは、自社が直接取得している一次データ(Search Consoleやアクセス解析、広告の管理画面など)である
- ツールは、流入ページやキーワード、広告の有無といった「構造的な情報」や、自社サイトの内部監査に活用する
- まずは普通の商売の原点に戻り、実際にサイトを見たり、お客さんに話を聞いたりすることを大事にする
- 外部の会社に任せきりにするのではなく、自社でも数字の意味を理解して会話できる状態を目指す
- 高額なツールが本当に必要かどうかは、Googleの純正ツールをやり切ったうえで改めて考えても遅くない
関連リンク
- Ahrefs SEO Metrics: A Glossary(Ahrefs公式)
- Google キーワード プランナー(Google 広告 公式)
- Google Search Console(サーチコンソール 公式紹介)
- Google 検索セントラル(SEOに関する公式情報)
- Google アナリティクス(公式紹介ページ)
FAQ
- Q1. 競合調査ツールの数字は、どこまで信用してよいのでしょうか。
- A. DR・UR・AR、オーガニックトラフィック、CPCなどの数字は、いずれも推定値です。ツール側もヘルプでそう説明しています。実測値として扱うのではなく、「傾向をつかむための目安」として、ほどほどに信用するくらいが現実的です。
- Q2. DRやURが競合より低いと、検索で勝てないのでしょうか。
- A. DRやURは、主にバックリンクの情報に基づいた指標で、コンテンツやユーザー行動などの内部要因は含まれていません。そのため、DRが高いから必ず勝てる、低いから必ず負ける、といった単純な話にはなりません。一つの目安として見るくらいがちょうどよいと考えています。
- Q3. 競合のオーガニックトラフィック推定値は、提案書や報告書に使ってよいですか。
- A. ニッチな業界ほど誤差が大きく、月ごとの変動も激しいため、提案書で「事実」として扱うのは難しいと感じています。全体の増減傾向を見る材料としては使えますが、具体的な数値として根拠にするのは控えめにしたほうがよいと思います。
- Q4. CPCが高いキーワードを狙えば、売上につながるアクセスを取れるのでしょうか。
- A. ツールが出すCPCは推定値であり、実際の入札単価は短いスパンで変動します。ある瞬間のCPCだけを見て「ここは売れるキーワードだ」と判断するのは危険です。検証したい場合は、自分で広告を出し、ランディングページを用意してテストするほうが、まだ納得感のある判断ができます。
- Q5. 高額な競合調査ツールは、Web担当として必ず契約すべきでしょうか。
- A. 私は「必須ではない」と考えています。Googleの純正ツール(Search Consoleやキーワードプランナー、アクセス解析など)だけでもできることは多く、まずはそれらをやり切ってから必要性を考えても遅くはありません。ツールに期待しすぎるのではなく、普通の商売の視点と、自社の一次データを大事にするほうが、長い目で見ると安定します。
続きはPodcastをご覧下さい。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/