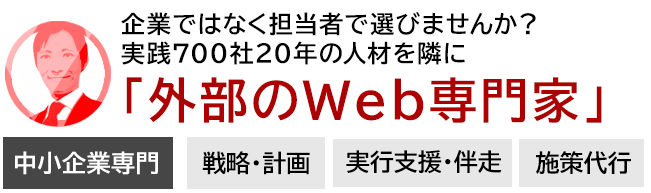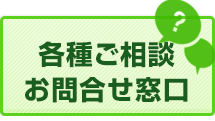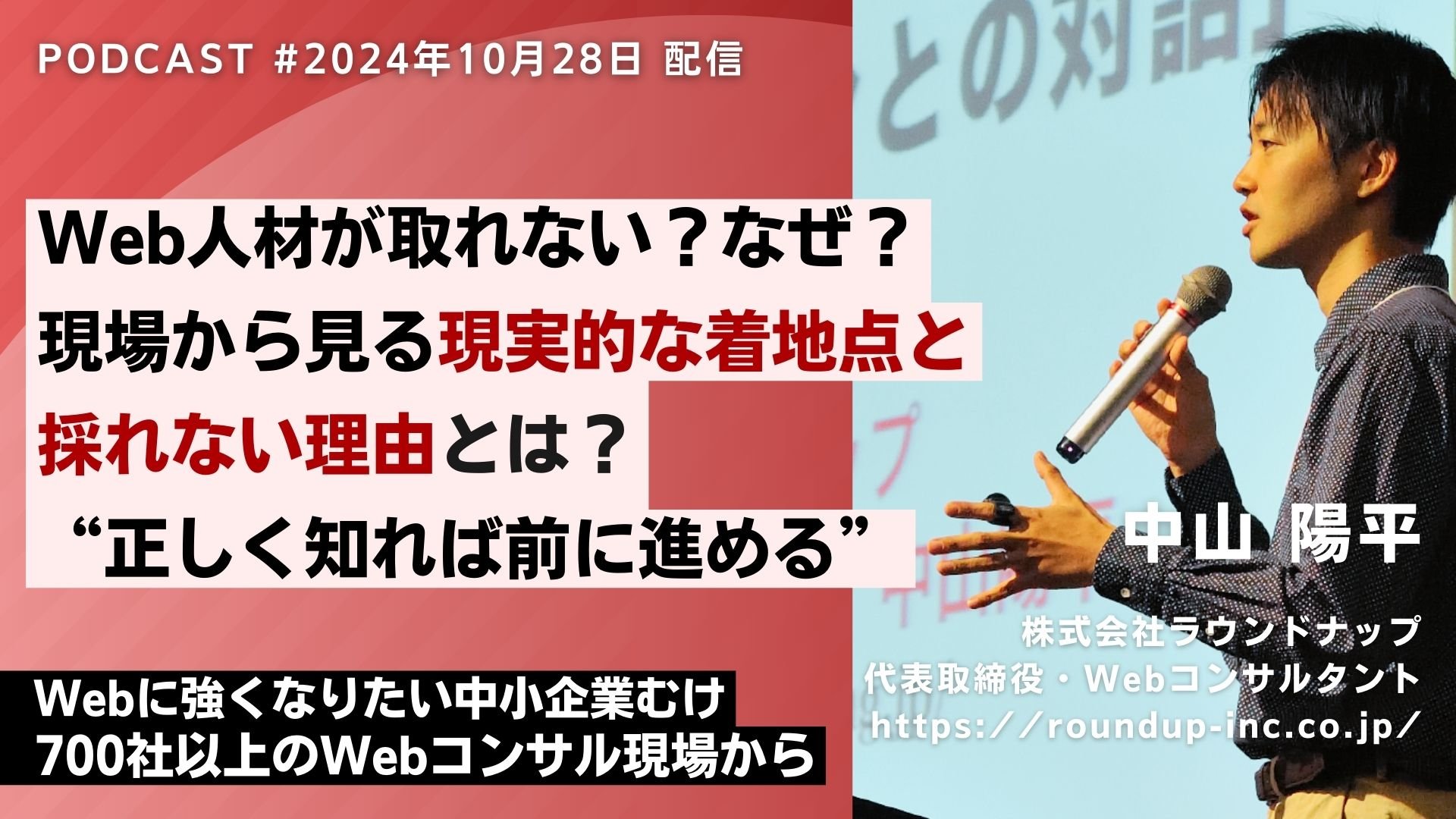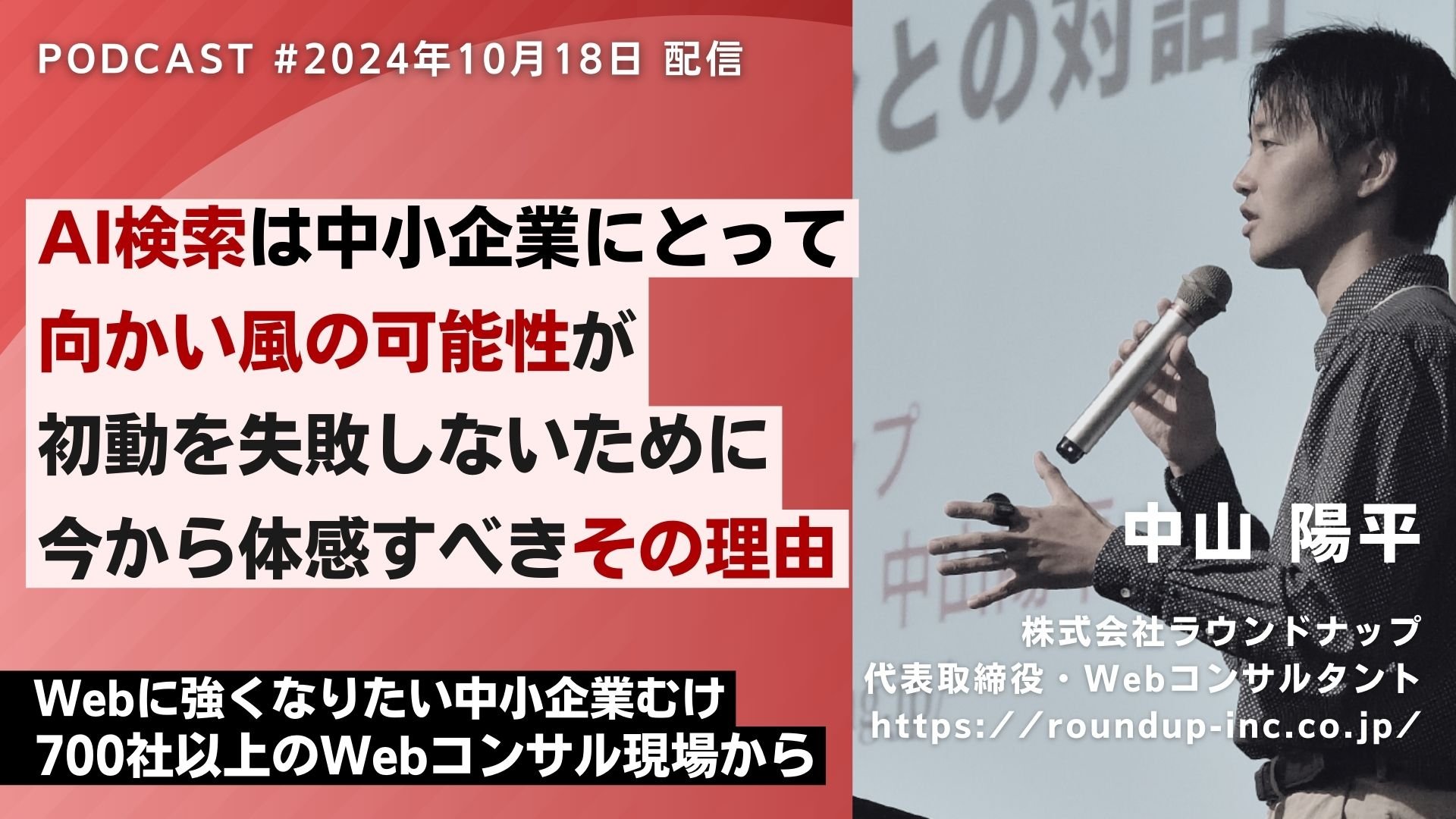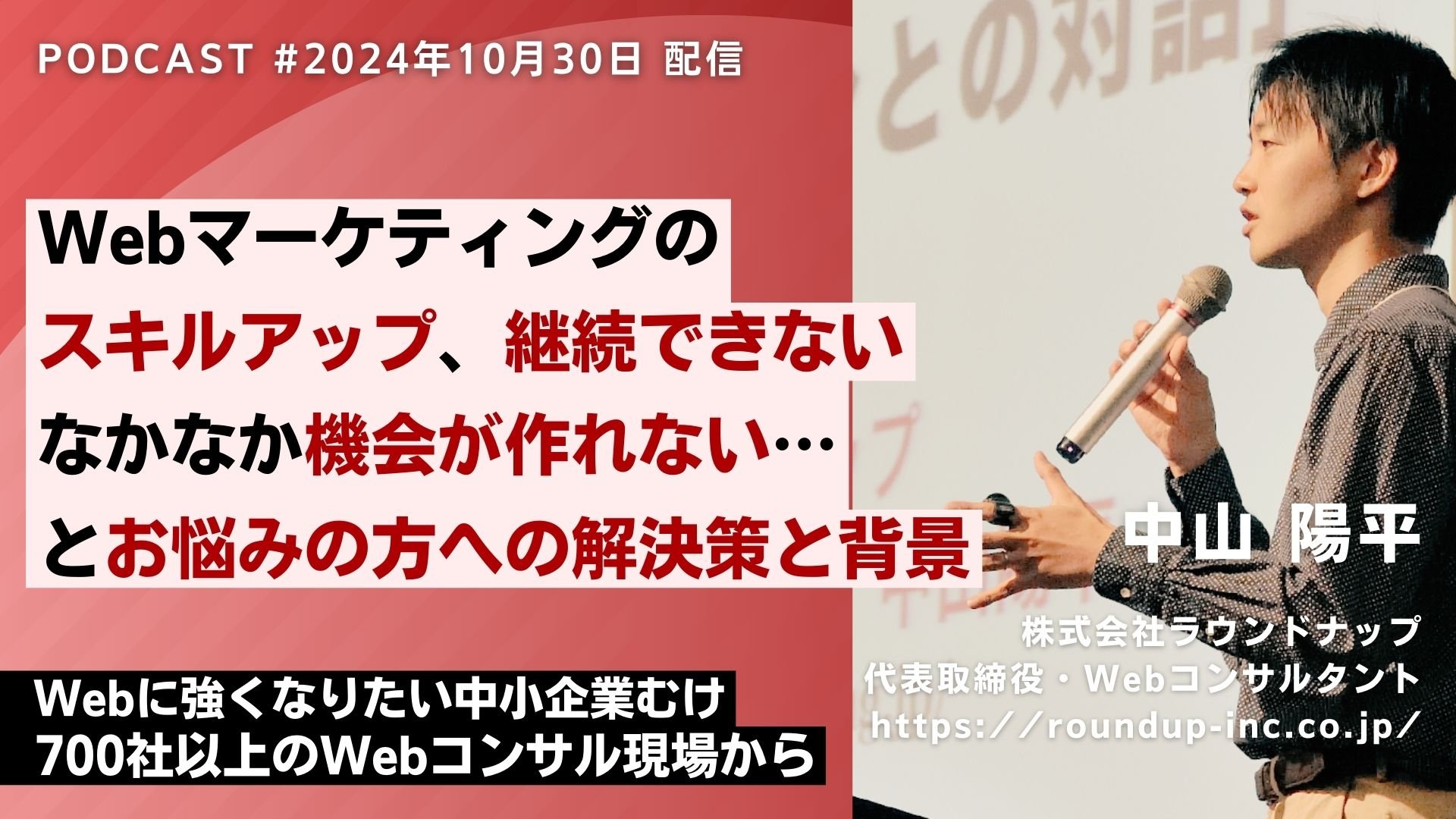Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
内容について
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
うちでは、社内研修や外部向けの研修で、日々いろいろなご質問をいただきます。全部にはその場で答えきれず、質問をずっとストックしてきたのですが、改めて分類してみたところ、大きく次の10項目に分かれることが分かりました。
- 人材・スキル関連
- 予算・リソース関連
- 戦略・計画関連
- 実施・運用関連
- コンテンツ関連
- 技術・ツール関連
- 成果・効果測定関連
- 組織・体制関連
- 法律・規制関連
- 新規顧客獲得・ブランディング関連
それぞれの大項目に、5〜6個ずつの個別の質問がぶら下がっている状態です。以前「ウェブマーケティング一問一答」という形でまとめて扱ったこともありますが、今回は一つ一つの質問をもう少し丁寧に、個別のテーマとして取り上げていこうと思います。
今回はその中の「人材・スキル関連」の一つ目、つまり
デジタルマーケティング(Webマーケティング)の専門知識を持つ人材がどうしても不足している。採用しようとしても見つからないし、社内にもいない。どうしたらいいのか。
というお悩みについて、現場での経験も交えながらお話しします。
「デジタルマーケティング人材がいない」は本当に人材不足なのか
まず押さえておきたいのは、Webマーケティングも、基本的には「普通のマーケティング」「営業」と同じ世界だということです。チャネルに「Web」が入っただけで、やっていることの本質はそれほど特殊ではありません。
ところが、Web担当者やデジタルマーケティング人材に対して、こんなイメージを持っているケースがとても多いと感じます。
- デジタル・Web・IT全般に広く詳しい
- SEO、広告、SNS、各種コンテンツなど一通りやったことがある
- 施策の設計から実行・分析・改善まで一人で回せる
- 最新情報も常にキャッチアップしていてトレンドに詳しい
- しかも社内を引っ張るリーダーシップもある
つまり、「何でもできるデジタルのスーパーマン」を無意識に求めてしまっているケースが多いのではないか、ということです。
同じ条件で「営業のスーパーマン」を採ろうとしたらどう感じるか
これを、リアルの営業に置き換えてみてください。
例えば、こんな人を採ろうとしているイメージです。
- 新規開拓・既存深耕、アウトバウンドもインバウンドも一通りの手法に精通している
- 業界ごとの攻め方や、最近の営業手法(例えばアカウントベースドマーケティング)もよく知っている
※アカウントベースドマーケティング(Account Based Marketing)は、特定の企業アカウントごとに戦略を組み立てて集中して営業・マーケティングを行う考え方です。 - チームを率いてマネジメントもできる
- 施策の計画・実行・評価・改善、いわゆるPDCA(Plan・Do・Check・Act)を回すのも得意
- しかも最新の営業トレンドも常に追いかけている
こういう人を「普通に求人を出して採用しよう」と考えたら、どうでしょうか。多くの方は「そんな人、そもそもなかなか市場に出てこない」と感じるのではないでしょうか。
Webの世界もまったく同じです。「すごい人」は、そもそも転職市場にほとんど出てこないのです。
優秀な人材はなぜ転職市場に出てこないのか
本当に優秀な人は、人づてで次の職場が決まってしまう
私の経験上、本当に優秀なWeb・マーケティング人材は、たいていこんな流れで動きます。
- 今の会社で高い評価を受けているので、そもそも会社が手放さない
- もし退職するとしても、同業者や取引先など「人づての紹介」で次が決まる
- そのため、一般的な転職サイトや人材市場に出てくる前に次の会社が決まる
結果として、普通に求人を出して待っていても、「すごい人」が応募してくる確率はかなり低いのが現実です。
実際に転職市場に出てくるのは、例えばこんな方が多い印象です。
- 特定の分野に強みがある(広告運用だけ、SEOだけ、など)
- プロジェクトマネジメントや全体管理の経験はあるが、実務は一部に偏っている
- 長く同じ会社にいたため、外部とのつながりが少なく、自分で転職市場に出て次を探している
もちろん、こうした方々がダメという話ではありません。ただ、「何でも一人でできるスーパーマン」を想定していると、いつまで経っても採用がうまくいかないということです。
「Webだから特別」という思い込みをいったん手放す
もう一つ、よくある思い込みとして、
- Webは専門性が高いから、そこで食べている人は「狭い世界のことは全部分かっている」はず
- だからWeb担当者なら、SEOも広告もSNSもコンテンツも、全部それなりにできるはず
という期待が無意識に乗っているケースがあります。
しかし実際には、Webもリアルも、「複数のチャネルの一つ」にすぎません。今はネット経由で情報を取る人もいれば、リアルでの接点を好む人もいる。その両方をどう組み合わせるかを考えるのがマーケティングです。
「Webだから特別な世界」「穴場が残っていて楽に成果が出る世界」という見方は、もう当てはまりません。むしろ、普通の営業・マーケティングと同じくらい、地味に積み上げていく世界だと考えてもらった方が現実に近いと思います。
本当に大事なのは「スーパーマン探し」ではなく「仕組みづくり」
ここまでを踏まえると、よくある悩みである
デジタルマーケティングの専門知識を持つ人材がいない。だから勝てない。
という問題の立て方には、少しズレがあります。
正しくは、
デジタルに限らず、何でもできるスーパーマンはそもそも取れない。
だから「すごい人がいなくても回る仕組み」を社内につくる必要がある。
という視点で考えた方が現実的です。
「良い人材がいないと勝てない会社」は、とても脆いです。良い人材ほどどこかに引き抜かれたり、独立したりする可能性が高くなります。
それよりも、
- ほどほどのスキルを持ったメンバー
- あるいは、今は知識がないけれど吸収が早いメンバー
といった人たちを組み合わせて、「チームと仕組み」で成果を出す会社の方が、長期的には強くなります。
良い人材が「ここで働きたい」と思う会社とは
環境が悪い会社ほど、優秀な人からは避けられる
WebやITに理解のない会社、あるいは活用に対して後ろ向きな会社は、正直なところ、経験のある人ほど行きたがりません。
理由はシンプルです。
- 社内の理解を得るために、文化づくりから始めないといけない
- 投資の重要性の説明や、部門間調整など「本来の仕事以外」の負担が大きい
- WebやITの価値が理解されていないため、給与や評価に反映されづらい
こういう環境では、スキルのある人ほど「やりがいはあるかもしれないが、消耗が大きい」と判断しやすくなります。
「ここなら自分の力を活かせる」と思える場をつくる
一方で、うまく回っている会社では、こんな動きもよく見かけます。
- 付き合いのある制作会社や代理店の担当者が、退職するときに
「御社の中で、Web担当として働かせてもらえませんか」と相談してくる - 外部の人から見ても、「ここなら自分が入ったらもっと伸ばせそう」と感じられる
- 結果として、事業会社のWeb担当として転職してくる人が増える
こうした状況は、会社として「Webやデジタルを活用する土台」を整えてきた結果として生まれます。
つまり、
- 良い人材が取れないのは当たり前
- 良い人材が「ここで働きたい」と思う環境を先に作る必要がある
という順番で考えることが、とても大事です。
まず目指すべきゴールは「発注」と「検収」ができる状態
では具体的に、社内でどこまでできるようになれば「一人立ちの第一ステージ」と言えるのか。
私は、一つの目安として「発注」と「検収」を自社でできる状態をお勧めしています。
発注ができるとは何か
ここでいう「発注」とは、単に「制作会社にお願いする」という意味ではありません。
- 今回の施策の目的は何かを整理する
- 誰に向けて、何を伝え、どういう行動を起こしてほしいのかを言語化する
- それをもとに、必要な成果物や機能、スケジュール、予算の枠を考える
- 複数社に相談し、提案を比較したうえで、どこに依頼するか判断できる
この一連のプロセスを、自社の中で回せるようになることが「発注ができる」状態です。
検収ができるとは何か
もう一つの「検収」は、できあがった成果物が目的や要件どおりかをチェックし、受け取ることです。企業研修の「研修」ではなく、「検査して収める」の方です。
例えば、ホームページ制作であれば、こうしたことを判断できる状態です。
- 制作会社から「完成しました」と納品されたときに、
それが本当に目的を満たす内容になっているかどうかをチェックできる - プロジェクトの途中で「ここはどうしますか?」と聞かれたときに、
自社のビジネスの視点から判断・指示ができる - 制作側や代理店側が気づいていないズレやリスクを、こちらから指摘できる
ここで大事なのは、HTMLを書ける必要はないし、システムの細かい仕様まで詳しくなる必要もないという点です。
Webの専門用語で会話できなくても構いません。むしろ、
- 「お客さんの立場だったらどう感じるか」
- 「これで本当に売れるのか」
- 「この導線だと途中で離脱しないか」
といった、ビジネス側の視点で疑問や意見を出せることの方が重要です。専門家同士のやりとりは、翻訳してもらえばよいのです。
外部パートナーと「二人三脚」で育てるという考え方
もちろん、最初から社内だけでここまでたどり着くのは、簡単ではありません。
新人を育てるときも、現場で仕事を教えるOJT(On the Job Training、実務を通じた教育)や、オンボーディング(受け入れ・立ち上げのプロセス)が必要になります。Web担当者を育てるのも同じで、教える側の人材が社内にいない場合は、外部の力を借りた方が効率が良いケースが多いです。
もちろん、
- 自分たちの中で試行錯誤するのが好き
- 外部の力に頼らず、とにかく自前でやりたい
という文化を持つ会社もあります。その場合は、その文化を尊重した方がうまくいきます。
ただ、平均的な会社であれば、「発注」と「検収」ができるようになるまでの期間だけでも、外部パートナーと二人三脚で進めることを一度検討してみてほしいと思います。
一緒に悩んでくれる外部パートナーを選ぶ
ここで大事になるのが、外部パートナーの選び方です。
極端な例ですが、
- こちらが何も言わなくても、とにかく「言われた通りに作って納品して終わり」でいいと考える会社
は、社内にノウハウを蓄積したい場合には向いていません。
対して理想的なのは、例えば次のようなスタンスを持つ会社です。
- 「本当にそれでいいのか」を一緒に検討してくれる
- ミーティングやチャットの中で、考え方やチェックポイントも含めて共有してくれる
- 最終的には、こちら側が自走できるようになることを歓迎してくれる
実際、今も生き残っているWeb制作会社や代理店には、こういうスタンスの会社がかなり多いと感じています。もちろん例外はありますが、以前に比べると、明らかに「これはまずい」という会社は減ってきた印象です。
そういう会社と1年くらい、OJT的に二人三脚で動いてみると、社内の見え方はかなり変わります。
属人化させず、チームでシェアしていく
ここで気をつけたいのは、一人だけにWebノウハウを集中させないことです。
- 担当者が一人だけだと、その人が辞めた瞬間にゼロに戻ってしまう
- 周りも「その人の仕事」と思ってしまい、関心が育たない
最初は中心メンバーが一人でも構いませんが、外部パートナーと一緒に進める中で、
- 関連部門の人も打ち合わせに同席してもらう
- 議事録やドキュメントを共通の場所に残し、チームで共有する
- 売上や成果が出たら、そのプロセスを社内で振り返る
といった形で、チームとしてノウハウを共有する仕組みを作っていくことが大事です。
そうして成果が出てくれば、
- Webまわりに投資できる予算も増えていく
- Web担当の評価や給与も上げやすくなる
- 結果として、外から見ても魅力的な職場に近づいていく
という良い循環が少しずつ回り始めます。
なぜ「人を丸ごと借りるモデル」をあまり勧めないのか
最近増えているのが、人材マッチング会社による「Web担当者の派遣・準委任」モデルです。
今のWeb・IT業界では、人材マッチングや中間マージンを取るビジネスモデルで利益を出している会社がかなり増えています。
もちろん、全てが悪いとは言いませんし、うまく使えている会社もあると思います。ただ、私自身の経験からすると、中小企業が「社内にノウハウを蓄積したい」という目的で使う場合、あまり相性が良くないケースが多いと感じています。
理由はいくつかあります。
- 社内に残るノウハウが少ない(人がいなくなればゼロに近づく)
- 中間マージンが入る分、コストの割に実働時間や内容が細くなりやすい
- 「人材を依存させる」方向に力が働きやすく、内製化が進みにくい
私も過去に、そういった会社経由で人を入れてみたことがありますが、正直に言うと、うまくいきませんでした。品質やコミュニケーションの面でお客さんに迷惑をかけてしまい、「これは続けられない」と判断したことがあります。
全部の会社がそうだとは思いませんし、良いサービスを提供しているところもあるはずです。ただ、売上や利益の源泉にあたる部分を、まるごと外部に預けるモデルを取るときには、慎重に考えた方が良いと思います。
「続ける会社」はごく一部、その分チャンスも大きい
5%・1%くらいしか「続けない」という体感
ここまで読むと、
- 3年とか5年とか時間がかかりそう
- 二人三脚でやって、社内の仕組みを整えて…と考えると、なかなか腰が上がらない
と感じる方もいるかもしれません。
ただ、ここには大きなチャンスがあります。
私の体感としては、セミナーや研修に参加した会社のうち、その内容をもとに何かしら行動するのは、せいぜい「5%くらい」です。さらに、その取り組みを1年間続けている会社となると「1%前後」という印象です。
(あくまで私の現場での感覚であって、厳密な統計データというわけではありません。)
つまり、「やる」と決めて、3年・5年と続けていくだけで、多くの会社と差がついていくということです。
時間がかかるからこそ、始めた時点で優位に立てる
この話をすると、多くの会社はこう考えがちです。
- 「そんなに時間がかかるなら、今は見送ろう」
- 「いい人が見つかるまで、外注で何とかしておこう」
その結果、ほとんどの会社はスタートラインに立たないまま時間だけが過ぎていくことになります。
一方で、「時間はかかるかもしれないが、今からやっていこう」と判断して動き出した会社は、その時点でかなり有利な位置にいます。少なくとも、私が関わってきた中小企業さんを見ていると、自分たちで頑張ろうと決めて動いた会社が、最終的には成果を出しているケースが圧倒的に多いです。
ラウンドナップWebコンサルティングとしてお手伝いできること
ここまでお話しすると、どうしても最後は、
「だから、うちのような会社をパートナーにしてください」という話ですね。
という流れになりますが、実際、私はそう思ってこのサービスをやっています。
オンラインコンサルを始めた頃は、ほとんど同業がいなかった
私がチャットを中心としたオンラインのコンサルティングサービスを始めた当時、こういった形態はほとんどありませんでした。対面か電話かメール、というのが一般的で、
- 「チャットでいつでも聞いてください」
- 「オンラインで継続的に相談を受けます」
というスタイルは、正直なところ、ほぼ見当たらなかった記憶があります。いわば、うちがパイオニアのような状態でした。
それから10年以上経って、今では同じような形態のサービスを提供する会社も増え、オンラインでのコンサルティングはかなり一般的な選択肢になってきたと感じています。
「とことん質問してもらう」方が、結果として伸びる
うちのオンラインコンサルは、基本的に質問は無制限です。チャットでいただいたものには、できる限り全部お答えしています。
見ていると、伸びる会社ほど、
- 毎日のように細かいことでも質問してくる
- こちらから水を向けなくても、自分からどんどん相談してくる
という傾向があります。
逆に、
- こちらから聞かないと質問が出てこない
- 「とりあえずお願いしたから、あとはお任せで」と丸投げになってしまう
というパターンでは、どうしても成果が出るまで時間がかかりがちです。
うちに限らず、同じようなスタイルの会社は他にもあると思いますので、外部パートナーを選ぶときは「一緒に考えてくれるか」「ノウハウを共有してくれるか」という視点を持ってもらえるといいのではないかと思います。
もちろん、これをもって「ぜひうちに来てください」と強く押し込むつもりはありません。ただ、もし二人三脚で社内にノウハウを蓄積していきたいと感じたときには、ラウンドナップWebコンサルティングの継続コンサルティングや診断サービスのページも、一度のぞいてみていただければうれしいです。
まとめ:人材の争奪戦ではなく、「人材が来たくなる会社」づくりを
最後に、今回のポイントを整理します。
- 「何でもできるデジタルのスーパーマン」は、そもそも転職市場にほとんど出てこない
- Web担当者に過剰な期待を乗せるより、「発注」と「検収」ができる仕組みを社内につくる方が現実的
- 良い人材ほど、WebやITに理解のない会社は避ける傾向がある
- 外部パートナーと二人三脚で、1年〜数年かけて社内のレベルを上げていく会社が、最終的に成果を出している
- 人を丸ごと借りるモデルは、社内にノウハウを残したい場合には相性が良くないことが多い
- 私の体感では、セミナー内容を実行する会社は5%くらい、その取り組みを1年続ける会社は1%前後しかいない
人材の争奪戦に参加するのではなく、「人材が来たくなる会社」になる。
そのために、外部パートナーと協力しながら社内にノウハウを蓄積していく。これが、中長期で見たときに、一番堅実で現実的なやり方だと考えています。
今回の内容が、社内のWeb担当者の育て方や、外部パートナーとの付き合い方を考えるきっかけになればうれしいです。
関連リンク
- ミラサポplus(中小企業庁の中小企業支援サイト)
- IT導入補助金2025 公式サイト
- Google 検索セントラル(公式SEO情報ポータル)
- 初心者や小規模ビジネスのための Google アナリティクス ガイド
- Google Search Console(検索パフォーマンス測定ツール)
よくある質問(FAQ)
- Q1. Web担当者を採用できない場合、まず何から始めるべきでしょうか。
-
いきなり「何でもできるWebのスーパーマン」を探すのではなく、まずは社内で「発注」と「検収」ができる状態を目指すのがおすすめです。外部パートナーと二人三脚で進めながら、目的の整理や要件定義、成果物のチェックを社内で判断できるようにしていくと、少しずつ自走できる土台が整ってきます。
- Q2. デジタルマーケティングの専門家を、必ず社内に一人置かなければいけませんか。
-
必ずしも「フルスペックの専門家」を一人採用する必要はありません。むしろ、ほどほどのスキルを持つメンバーや、吸収が早いメンバーを複数人集めて、外部の専門家と組み合わせて動く方が現実的な場合が多いです。社内では「お客さんの立場から見てどうか」を判断できれば十分で、専門的な部分は外部と協力しながら補っていくイメージです。
- Q3. 外部の制作会社や代理店に、Web周りを丸投げしてしまっても大丈夫でしょうか。
-
短期的に「とりあえず形を作る」だけなら丸投げでも動くことはありますが、社内にノウハウが残らないという大きなデメリットがあります。担当者が変わるたびにゼロからやり直しになりがちで、長期的には非効率になりやすいです。できれば丸投げではなく、「何をやっているのか」を理解しながら一緒に進めていく形を選んだ方が、最終的には安定した運用につながります。
- Q4. 外部パートナーと組むとき、どんな会社を選べばいいのでしょうか。
-
ポイントは、一緒に考えてくれるかどうかと、こちらが自走できるようになることを歓迎してくれるかどうかです。「言われたものを作って終わり」ではなく、「本当にそれでいいのか」を一緒に検討してくれる会社や、ミーティングの中で考え方やチェックポイントを共有してくれる会社の方が、社内にノウハウを残しやすくなります。
- Q5. 社内にWebのノウハウを蓄積するために、具体的にどんなことを意識すればよいですか。
-
まずは、外部パートナーと動くプロジェクトに複数人で関わることを意識してみてください。打ち合わせには関連部門の人も同席してもらい、議事録や資料は共通の場所に残し、成功事例や失敗事例を社内で振り返る場をつくります。こうしてチームで情報をシェアし続けることで、担当者が変わってもノウハウが残り、会社としての「Webの地力」が少しずつ高まっていきます。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ)
https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892 - YoutubePodcast(旧:GooglePodcast)
https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN - Spotify
https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj - Amazon Music
Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。
https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/