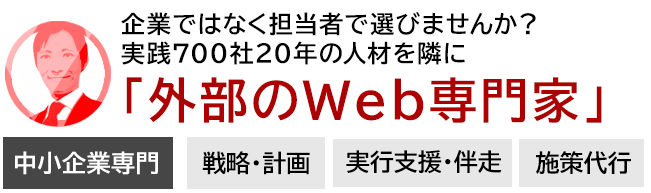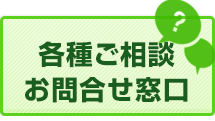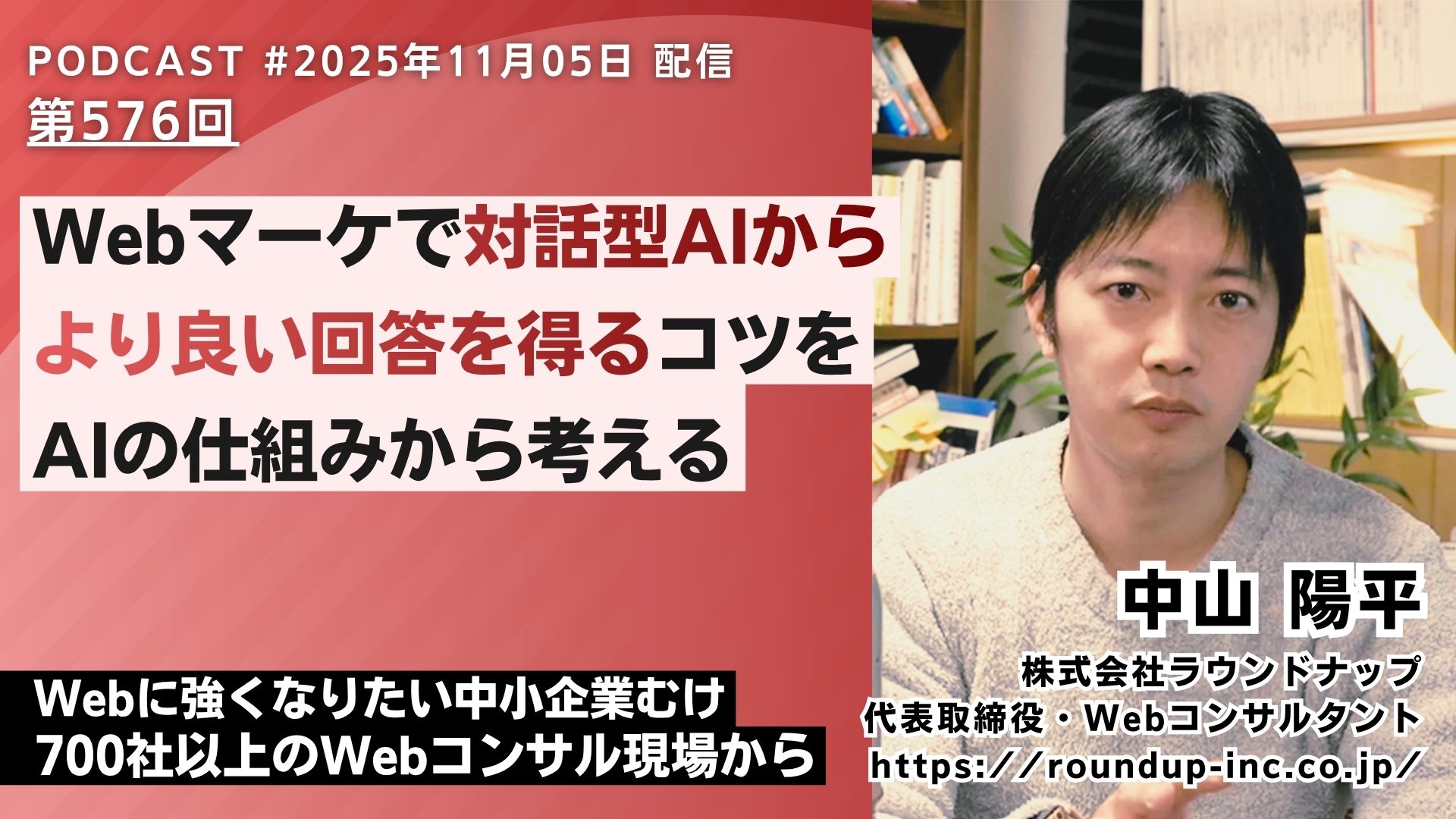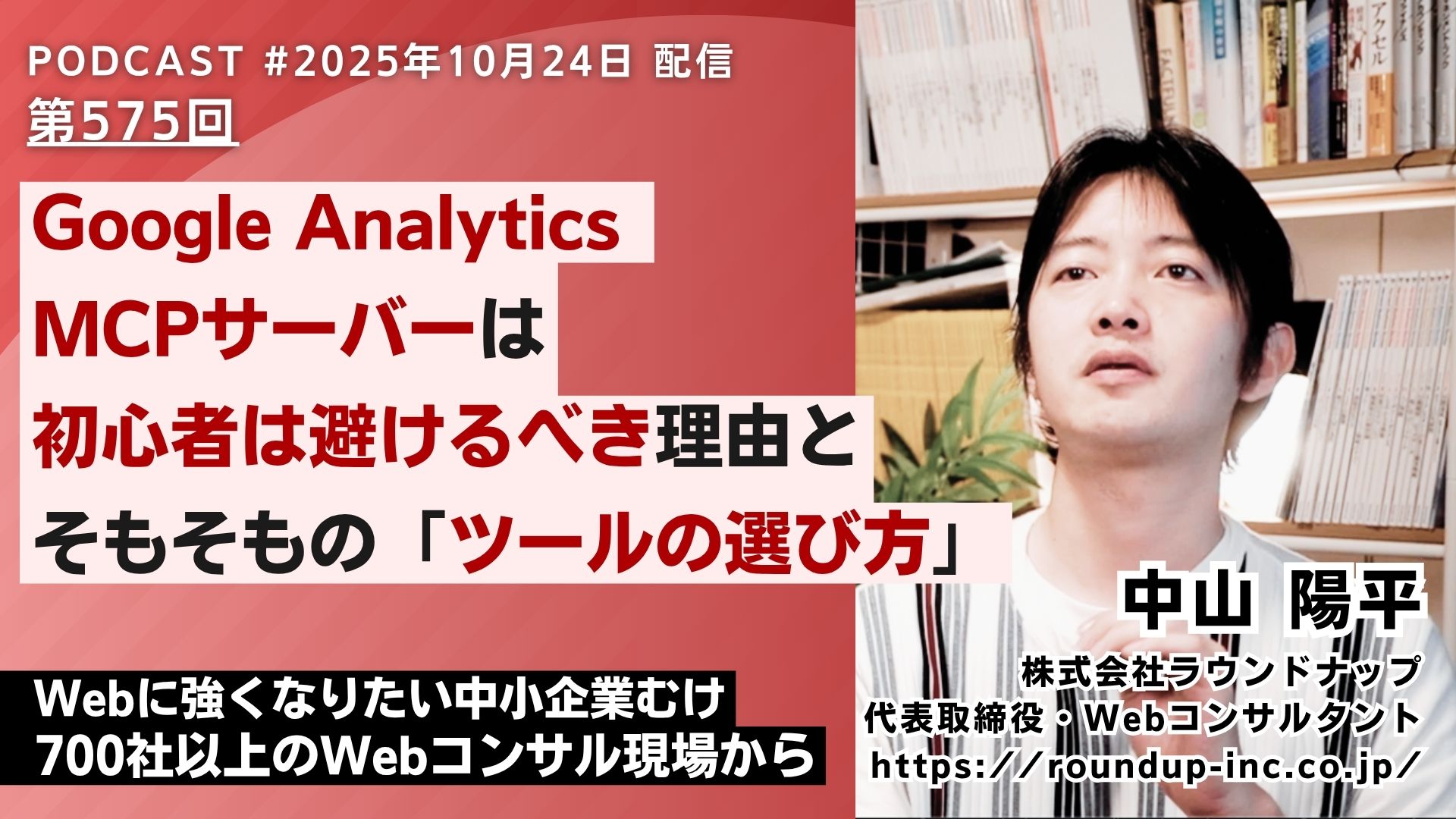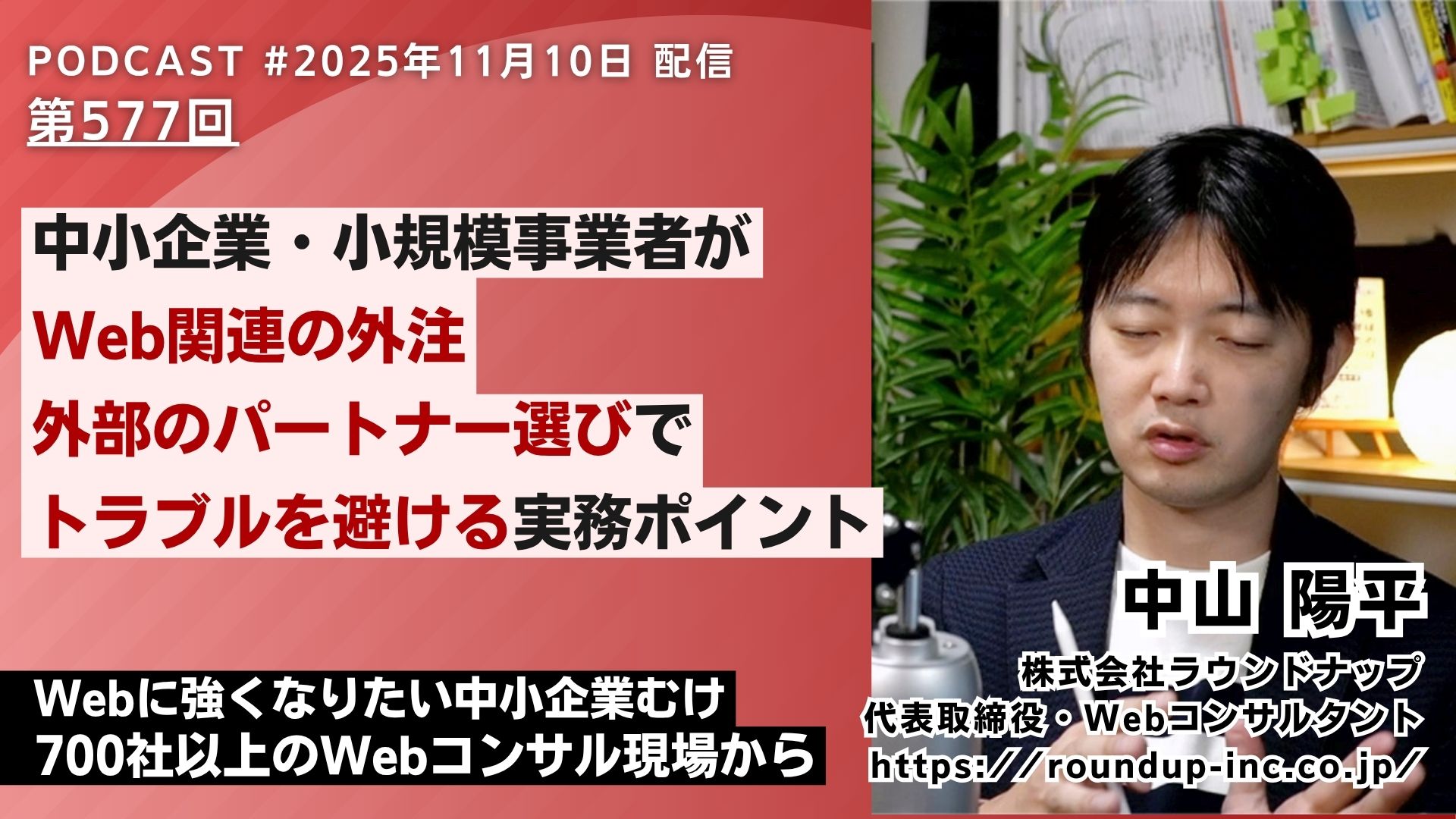Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
ChatGPTでがっかりした経験はありませんか?
今回は、対話型AI、特ChatGPTやGeminiについて、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。
ChatGPTのような文章生成AIを使った際に、「なかなか満足のいく回答が得られない」「思ったような品質にならない」と感じた経験はないでしょうか。
一度は軽い絶望感や、がっかりした気持ちを味わった方も多いかもしれません。その結果、「やっぱりまだ実用的ではないな」と感じ、使うのをやめてしまった方もいるのではないでしょうか。
このようなことが起こる大きな理由の一つは、私たちが対話型AIの「得意なこと」をきちんと把握していないからかもしれません。今回の内容を読んでいただくことで、ChatGPTやGeminiなどから、より質の高い、実用的な回答を引き出すヒントが得られるはずです。
そのためには、まずAIがどのようにして文章を生成しているのか、その仕組みを少しだけ知っておくことが近道になります。そこで本記事では、まずAIの仕組みを分かりやすさを優先して解説し、その上で「なぜ思った通りの回答が返ってこないのか」「どうすれば質の高い回答を引き出せるのか」について、具体的なポイントを解説していきます。
AIが苦手な「オープンクエスチョン」と得意な「条件付け」
生成AIから満足のいく回答を引き出せない方の使い方を見ていると、ある共通点に気づきます。それは、「オープンクエスチョン」をしてしまっているケースが非常に多いということです。
例えば、以下のような質問です。
- 「最高の〇〇を考えてください」
- 「我が社にとってベストで、他にないようなものを作ってください」
- 「最高の提案をしてください」
実は、AIはこのような漠然とした質問がとても苦手です。その理由は後ほどAIの仕組みの部分で詳しく説明しますが、まずはこの点を覚えておいてください。
では、逆にAIは何が得意なのでしょうか。それは、条件や関連情報を適切に与え、方向性を定めた上で、ゴールまでの道筋を模索させることです。つまり、入り口と出口がはっきりしている課題解決を得意としています。
「問いを立てる能力」の本当の意味
よく「AIを使いこなすには、問いを立てる能力が重要だ」と言われます。「問いを立てる能力」と聞くと、優れた質問をする力のように思われがちですが、本質は少し違います。これはむしろ、適切な「初期の条件付け」を行い、「どうなってほしいか」というAIにとってのゴールを明確に設計し、指示する能力だと捉えると、より具体的になります。
もちろん、考える過程をAIに手伝ってもらうことは有効ですが、すべてを丸投げして「とりあえず売上を上げるために一番やるべきことを教えて」のように質問すると、たいていは漠然とした、どこかで聞いたことがあるような一般的な内容が返ってくるだけです。
AIを使いこなすとは「丸投げ」ではない
「AI」と聞くと、どうしても「丸投げで答えを出してくれる魔法の道具」というイメージがあるかもしれません。しかし、本当にAIを使いこなす能力とは、丸投げする能力ではなく、AIが最も得意なことを、得意なやり方でやらせてあげる能力です。
これが上手な人は、AIから単なる情報ではなく、実務で本当に役立つ質の高いアウトプットを引き出すことができます。
なぜAIは平凡な回答しかできないのか?その仕組みを解説
では、なぜオープンクエスチョンではありきたりな答えしか返ってこないのでしょうか。その理由を理解するために、ChatGPTのような対話型AIが文章を生み出す仕組みを簡単に見ていきましょう。
文章生成の心臓部「自己回帰型トランスフォーマー(Transformer)」
少し専門的な言葉になりますが、ChatGPTなどは「自己回帰型トランスフォーマー(Transformer)」という技術がベースになっています。これは以下のような仕組みで動いています。
- トランスフォーマー(Transformer)
- 単語を、様々な特徴を持つパラメータの集合体(ベクトル)に変換する仕組みです。ゲームのキャラクターに「素早さ」「力」「特殊能力」といった多数のパラメータがあるように、一つの単語を多くの側面から数値化して捉えます。
- 自己回帰型
- 直前の文脈(一つ前や二つ前の文章)を踏まえて、「次にどの単語が来ると最も自然か」を予測し、言葉を紡ぎ出していく仕組みです。
つまり、AIは与えられた文脈や情報に基づいて、最も適切と思われる単語を確率的に繋ぎ合わせることで、文章を生成しているのです。
AIは「既存の知識のつながり」から答えを見つける
AIが単語を選ぶ際の根拠となるのは、「モデル」と呼ばれる膨大な知識データベースです。このモデルは、インターネット上のテキストなどを事前に学習(プリトレーニング)して作られた、いわばAIの脳みそです。AIの回答は、すべてこのモデルの中にある知識や単語同士のつながりが元になっています。
ここで重要なのは、AIはすでにある言葉と言葉の結びつきや、既存の概念を元にして答えを生成するという点です。「最高の提案」のようなオープンクエスチョンを投げかけると、なぜ平凡な答えが返ってくるのか。それは、特に条件が指定されていなければ、AIは世の中で「最高の提案」という言葉と一緒によく使われる、ごく一般的な単語の組み合わせを提示するしかないからです。「よくある質問」には「よくある答え」が返ってくるのは、ある意味で当然なのです。
「今までにないもの」が生まれない理由
「他社がやっていないこと」や「今までにないアイデア」を求めても、期待外れの結果に終わることが多いのも、この仕組みを考えれば理解できます。
「どこにもないもの」とは、言い換えれば「まだ言葉と言葉が結びついていないもの」です。AIは既存のデータのつながりを元に回答を生成するため、そもそもデータの中に存在しない、あるいは関連性が極めて薄い組み合わせを自発的に生み出すことは原理的に非常に困難です。
誰も思いつかないような突飛なアイデアは、AIのデータベース(モデル)の中では単語同士の関連性がないため、そもそも選択肢に上がってきません。このAIの基本原理を理解しておくことが、うまく付き合っていくための第一歩です。
AIから質の高い回答を引き出す3つのポイント
では、どうすればAIの能力を最大限に引き出せるのでしょうか。それは、AIが苦手なことをさせるのではなく、得意な土俵で仕事をさせることです。具体的には、以下の3つのポイントが重要になります。
ポイント1:具体的な「条件付け」で考える範囲を絞る
まず最も重要なのが、人間がAIのために適切な条件を与えることです。漠然と問いかけるのではなく、以下のよう考えるべき範囲を具体的に絞り込んであげましょう。
- 目的:何を得たいのか、何を実現したいのか、誰にどんな結果をもたらしたいのか。
- 制限・境界条件:予算の上限、使えるリソース(人員、時間)、関連する法律や規制、競合が強い領域など。
ここで欲張って条件を緩くするよりは、むしろ現実的な制約をできるだけ多く与える方が、AIは質の高い回答を出しやすくなります。絞り込みすぎたと感じたら、そこから一つずつ条件を緩めていく、というアプローチがおすすめです。これは、人間に仕事を依頼する時と同じだと考えると分かりやすいでしょう。
ポイント2:「うまくいった例」をデータとして蓄積する
AIに良いヒントを与えるために、成功事例や参考情報をデータとして蓄積していくことも非常に効果的です。これは社内のナレッジとしても財産になります。
- 社内の成功事例:過去にAIを使って良い回答が得られた質問(プロンプト)と、その回答をセットで保存しておきましょう。Googleフォームやスプレッドシートのような簡単な仕組みで十分です。
- 外部の参考情報:他社の事例や業界の動向、新しい組み合わせで成功した商品のニュースなど、参考になりそうな情報をテキスト形式でまとめておき、AIに読み込ませられるように準備します。
こうした「うまくいった例」をAIにインプットすることで、AIは「こういう観点で言葉のつながりを探せば、良い答えにたどり着きそうだ」というヒントを得ることができ、回答の精度が格段に向上します。
ポイント3:「探索」と「深掘り」のフェーズを分ける
一つの質問で、アイデア出しからプランニングまですべてを一度にやらせようとすると、AIの回答は散漫になりがちです。思考のプロセスをフェーズ分けすることをおすすめします。
- 探索フェーズ:まず、アイデアの種を見つけるために、あえてオープンクエスチョンを使い、幅広く情報を集めます。ここで出てきた回答はあくまでたたき台と捉え、人間が吟味し、方向性を絞り込みます。
- 深掘りフェーズ:探索フェーズで得られたいくつかの候補を元に、「ポイント1」で挙げたような具体的な条件付けを行い、実現可能性や具体的なプランニングをAIに考えさせます。
このように、アイデアを広げる「探索」の段階と、一つのアイデアを具体化する「深掘り」の段階を明確に分けることで、思考が整理され、最終的なアウトプットの質も高まります。
まとめ:AIとの上手な付き合い方
これまで見てきたように、AIから期待通りの回答が得られないと感じていた方は、無意識にAIの苦手なことをさせていたのかもしれません。自分の質問がオープンクエスチョンになっていないか、あるいは条件付けが非現実的でないか、一度見直してみてください。
人間とAIの役割分担を考える
AIは決して万能ではありません。少なくとも今のところは、得意な分野と苦手な分野がはっきりと存在します。AIを使いこなすとは、その特性を理解し、人間がやるべき「条件設定」や「最終判断」と、AIが得意な「膨大な情報の中から最適な組み合わせを見つける」作業をうまく分担することです。
この役割分担を意識するだけで、これまでのAIとの関わり方が変わり、仕事の進め方やアウトプットの質が大きく向上する可能性があります。
AIの仕組みを学ぶことが、一歩先を行くカギになる
今回お話しした「自己回帰型トランスフォーマー(Transformer)」のようなAIの裏側の仕組みは、少し難しく感じるかもしれません。機械学習などの専門用語に抵抗を感じるのも自然なことです。
しかし、こうした基礎知識は、AIをよりうまく使うための大きな助けになります。実際に現場を見ていても、やはりAIを最も使いこなしているのは、その仕組みを理解しているエンジニアの方々だと感じます。簡単な書籍や検定などを通じて基礎知識を得ておくことは、今後大きなアドバンテージになるでしょう。
今回の内容が、皆さんとAIとの付き合い方を見直すきっかけになれば幸いです。
Web活用の「最初の一歩」に関するよくあるご質問
- 対話型AIを使っても良い回答が出ないのはなぜ?
- 質問がオープンすぎて、対話型AIが既存の情報からありきたりな回答を出してしまうからです。
- 対話型AIが得意な質問方法とは?
- 具体的で明確な条件を設定し、対話型AIが探索しやすい状況を作ることです。
- 対話型AIはゼロから新しいアイデアを生み出せるの?
- いいえ、対話型AIは基本的に既存情報の組み合わせで回答を作るため、完全に新しい発想は苦手です。
- どうやって対話型AIに良い回答を出させるの?
- 成功事例や明確な目的、制限などの条件をしっかり伝えることが重要です。
- 対話型AI活用で結果が出ない時の改善方法は?
- 質問方法や条件設定を見直し、より具体的で絞り込んだ質問をすることです。
Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/