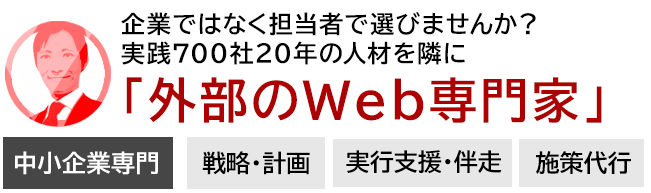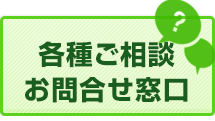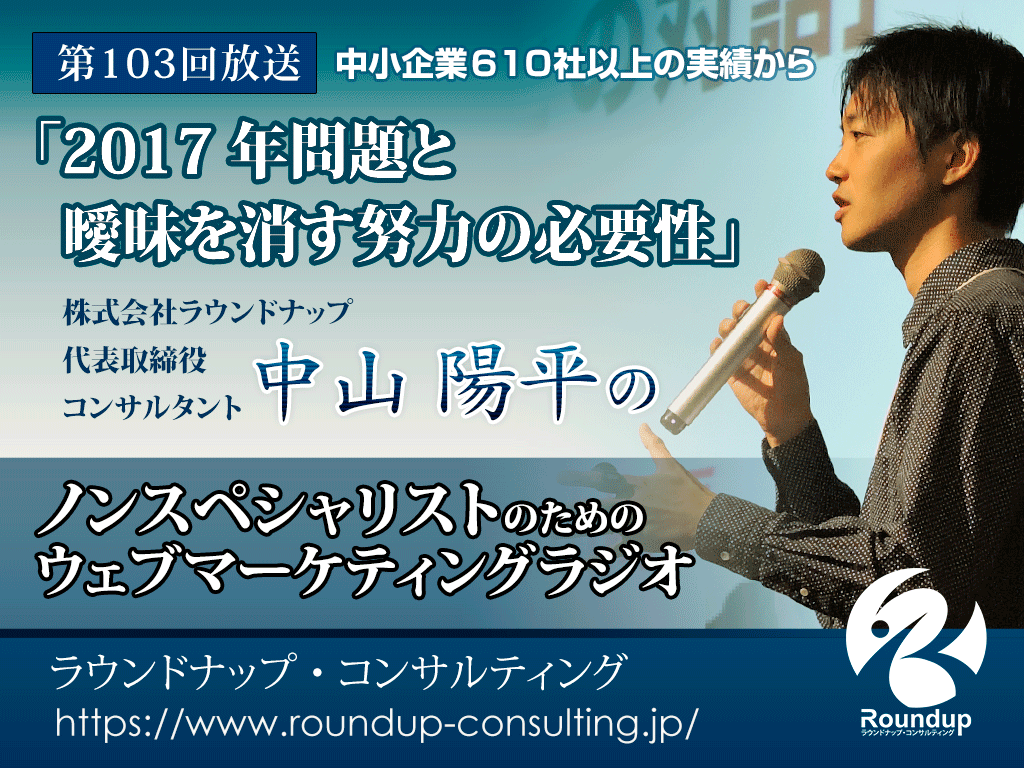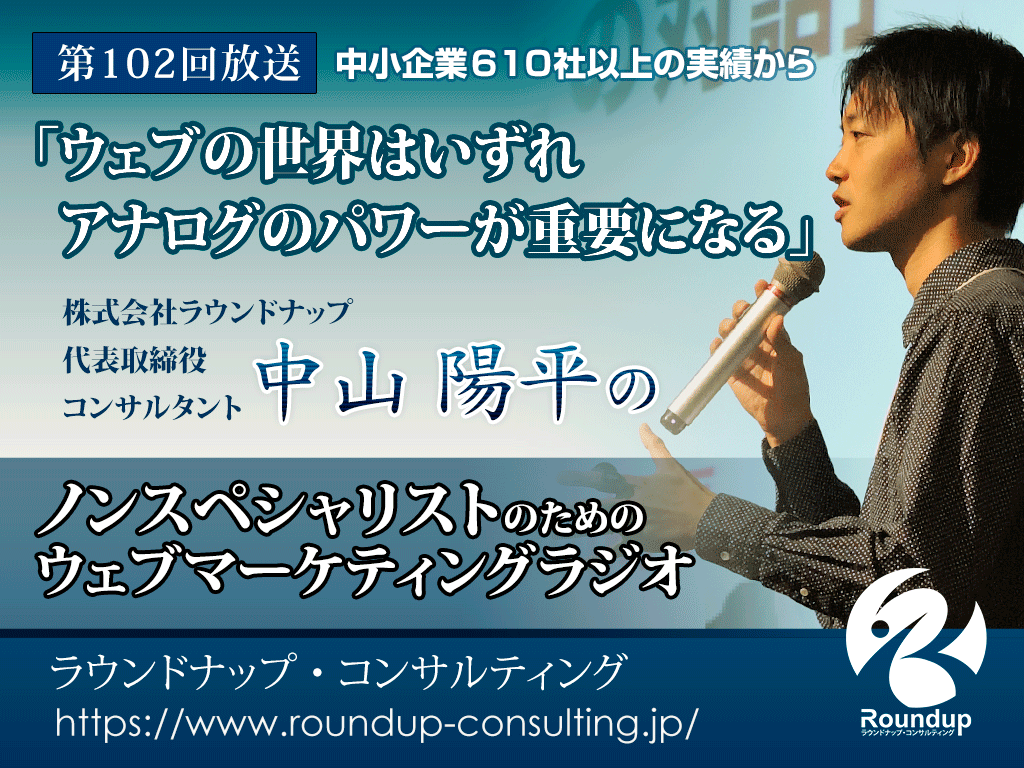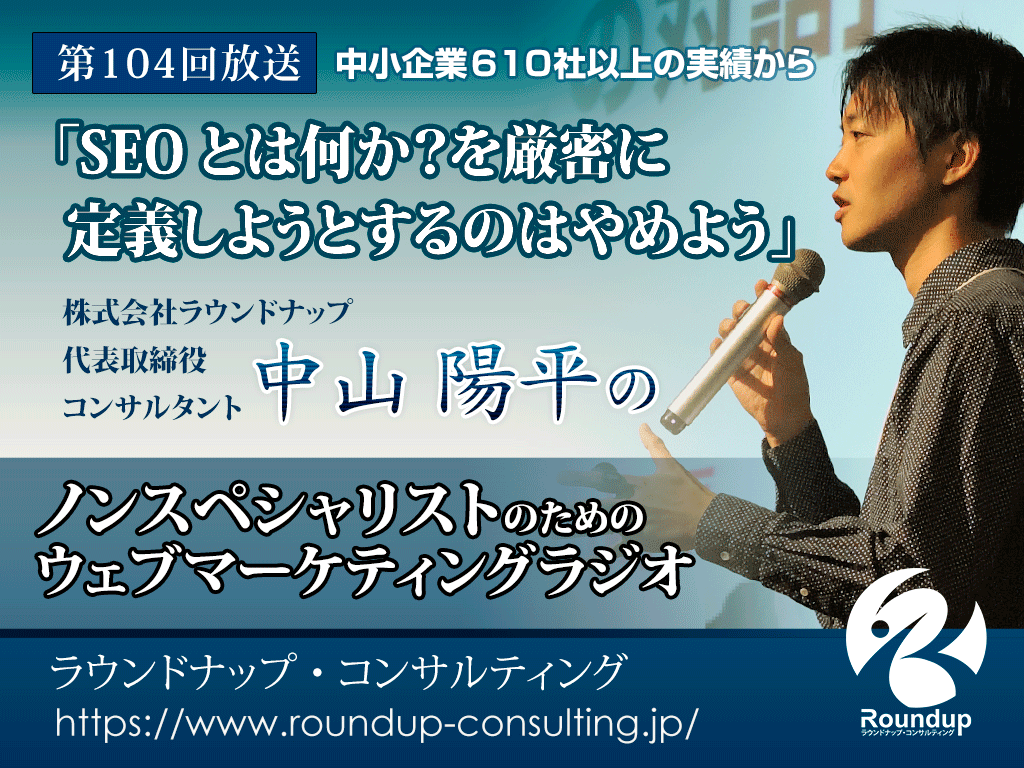PodcastはiTunesのPodcastディレクトリからダウンロード下さい。自動的にダウンロードされて便利です。
Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
今回の内容について
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
この記事は、2017年4月12日に配信したPodcast「SEOとは何か?を厳密に定義しようとするのはやめよう」をもとに、テキストとして再構成したものです。
読むことで、次のようなポイントが整理できます。
- 「SEOとは何か?」を厳密に定義しようとすることが、なぜ実務ではあまり意味がないのか
- 「どこまでがSEOで、どこからがコンテンツか」という線引きにこだわらない方が成果に近づきやすい理由
- 検索エンジン対策とコンテンツ制作を「一本の流れ」として捉える考え方
- よくある二つの極端な考え方(順位だけを見る/良いコンテンツなら勝手に見つかる)への注意点
- 自社サイトのボトルネックを見つけて改善していくための具体的な視点
なお、本記事の内容は2017年当時のPodcastで話している内容をベースにしています。一部、2025年11月時点で誤解を生みそうなところだけ「【2025年注記】」として補足を加えていますが、基本的な考え方は当時のままです。
この回の前提と背景
このPodcastは「ノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ」として、マーケティング専門職ではないけれど、ウェブをちゃんと活用していきたい方をイメージしてお届けしているものです。
ラウンドナップWebコンサルティングとして、当時すでに約450社・40業種のコンサルティングを行ってきた経験をもとに、「SEO」という言葉に振り回されすぎないための考え方をまとめています。
テーマは「SEOとは何か?を厳密に定義しようとするのはやめよう」です。
SEOを厳密に定義しようとするのは、あまり役に立たない
まず最初にお伝えしたいのは、「SEOとは何か?」を厳密に定義しようとすることは、実務の現場ではほとんど役に立たないということです。
なぜかというと、その議論は多くの場合、
- コンテンツ制作側の人たち
- いわゆるSEO専門業者や検索エンジン周りの人たち
のあいだで起きている「領域の取り合い」に近い話になりやすいからです。
「これはSEOか、コンテンツか」という宗教論争
よくある構図としては、次のようなものがあります。
- SEO側から見ると、「検索エンジンからの流入に関わることは全部SEOだ」と言いたくなる
- コンテンツ・インバウンド側から見ると、「これはもともとコンテンツ戦略の話であって、SEOではない」と言いたくなる
お互いに「それはうちの領域だ」「いやいや、それにSEOなんて名前を付けないでくれ」という形で、いわば宗教論争のようになってしまうことがあります。
その背景には、
- 自分たちのサービスのマーケットやリーチを広げたいというビジネス上の事情
- 自分が長く関わってきた領域が、別の名前で語られるのを受け入れにくい感情
といったものが混ざっています。
ただ、実際に自社のビジネスのためにウェブから反響を増やしたい方にとっては、こういった「名前の論争」はほとんど意味がありません。そこに時間を使うよりも、サイトやコンテンツを良くしていくことに時間を使った方がはるかに建設的です。
2010年前後の「SEO=上位表示テクニック」という時代
こうしたズレが生まれている背景には、少し過去の「SEOのイメージ」も影響しています。
だいたい10年前、まだYahooとGoogleが同じ検索エンジンを使っていなかった頃、SEOという言葉はほとんど「検索結果で上位表示するためのテクニック」と同じ意味で使われていました。
- Yahooで順位を上げるにはどうするか
- Googleで順位を上げるにはどうするか
- そのための技術的なテクニックを、有料・無料で配布する
そういった「上位表示テクニックのセット」が、ほぼそのまま「SEO」と呼ばれていた時代があります。
その頃からSEOに関わっていた人たちにとっては、「コンテンツ戦略」や「見込み客を育てる仕組み」の話までSEOの中に入ってくると、強い違和感が出るのも自然です。
一方で、コンテンツ側から見れば、
- サイトに来た人に、どのタイミングでどのコンテンツを見せるのか
- どの検索キーワードで、どのコンテンツを出すのが良いのか
といった話が主戦場なので、「それは単なる上位表示テクニックの話ではない」という感覚もまた自然です。
こうした背景があるため、「どこからどこまでをSEOと呼ぶのか」という話を真面目にやり始めると、終わりがありませんし、あまり実務の役には立ちません。
実務で考えるべきは「検索から来た人にどう応えるか」
では、何を考えるべきか。
結論から言うと、「検索エンジン経由で来てくれた人に対して、自分たちの価値をどう正しく伝えるか」という一貫した視点を持てば良い、ということです。
もっとシンプルに言えば、
- 検索でたどり着いた人が
- 自分たちの商品・サービスを正しく理解して
- 「ここなら自分の役に立ちそうだ」と判断できるようにする
この流れをどう設計するかを考えていけば、自然とやるべきことが見えてきます。
検索エンジン側への配慮:サイトの「土台」を整える
まず前提として、検索エンジン側への配慮が必要です。当時も、そして今も、検索エンジンとしてはGoogleがほぼ中心的な存在です。
そこで大事になるのが、「自分のサイトの中の情報を、Googleに対して漏れなく、重複なく、正しく伝えられているかどうか」です。
- クロールされやすい構造になっているか
- 重要なページがきちんとインデックスされているか
- ページごとにテーマがはっきり伝わるようになっているか
そのうえで、Googleがどのような形で情報を整理しているのか、どのようなサイト構造やマークアップを求めているのかを、最低限は把握しておく必要があります。
たとえば、構造化データ(検索結果で意味を理解してもらうためのマークアップ)をどう扱うか、といったテーマです。
当時の文脈では、モバイル向けの高速表示を意図したAMP(Accelerated Mobile Pages)のような話題も「やるべきかどうか」を検討すべきものとして挙がっていました。
【2025年注記】 現在(2025年)では、AMPが検索結果で必須という位置づけではなくなっていますが、「Googleがどのような形式で情報を出してほしいと思っているかを理解し、それに合わせてサイトを整える」という考え方自体は変わっていません。
どのキーワードでどのページを出すかを設計する
次に必要なのが、「どの検索キーワードで、どのページを出したいのか」を考えることです。
これは単にキーワードをたくさん並べるという話ではなく、
- この検索キーワードの人は、どんな状況・どんな悩みで検索しているのか
- その人に最初に見せるべきページはどれか
- その後、どのようなコンテンツの流れで理解を深めてもらうか
といった設計の話です。
ここは、一般的には「コンテンツマーケティング」や「インバウンドマーケティング」と呼ばれている領域と重なりますが、実際には検索エンジン対策と密接に結びついています。
キーワードとページの対応を、きちんと設計しておくことで、
- 適切なタイミングで
- 適切な人に
- 適切なコンテンツを見てもらう
という流れを作りやすくなります。
コンテンツそのものの役割:欲しい人にきちんと届くように
そして、その先にあるのがコンテンツそのものです。
コンテンツについて考えるべきことは、例えば次のようなポイントです。
- そのページで何を伝えたいのか(テーマ)
- どのようなストーリーで話すと、読み手が理解しやすいか
- 読み終わった後、次にどんな行動をとってもらいたいか
たとえば、
- 「まずは悩みの整理」→「解決の全体像」→「自社サービスの位置づけ」
- 「よくある失敗例」→「それを避けるための考え方」→「具体的な提案」
といった流れを考えながらコンテンツを組み立てていくことで、サイトに来てくれた人が「自分の欲しいものはここにありそうだ」と気づいてくれる可能性が高まります。
Search Consoleやアクセス解析で「ボトルネック」を見つける
そして、その全体を見直すための道具として、
- Googleサーチコンソール
- Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツール
が登場します。
サーチコンソールでは、どの検索クエリでどのページがどのくらい表示・クリックされているのかが分かります。
アクセス解析ツールでは、
- どのページから入ってきているのか
- どこで離脱してしまっているのか
- 問い合わせや購入など、成果につながっているのはどの流れか
といったことを確認できます。
【2025年注記】 現在は、Googleアナリティクスのメインは「Googleアナリティクス4(GA4)」になっていますが、「検索からコンテンツ、そして成果までの流れの中で、どこがうまくいっていないのか(ボトルネック)を探す」という使い方の方向性は変わっていません。
「どこまでがSEOか」を気にしすぎる必要はない
ここまで見てきたように、
- 検索エンジンに正しく理解してもらうための技術的な部分
- キーワードとページの対応を設計する部分
- コンテンツそのものの中身やストーリー
- サーチコンソールやアクセス解析でボトルネックを見つける部分
これらは、本来は一本の線でつながっているものです。
そのため、
- 「ここから先はSEOではない」
- 「これはコンテンツだからSEOとは関係ない」
といった線引きにあまりこだわりすぎない方が、実務としては動きやすくなります。
むしろ、
- 検索をして情報を探している人が
- 自分たちのサイトにたどり着いて
- きちんと価値を理解してもらい
- 結果としてビジネスにつながる
という一連の流れを、「ビジネスの仕組み」としてどう設計するか。その中で必要なことを、名前にこだわらず淡々とやっていく方が、本質的です。
ありがちな二つの極端な考え方
ここで、よくある二つの極端な考え方について触れておきます。
1. 「上位表示さえできれば何とかなる」という考え方
一つは、「SEOで上位表示さえできれば、あとは何とかなる」という考え方です。
検索順位の向上自体は大切ですが、
- その裏側にあるコンテンツの中身
- サイト全体の導線や、問い合わせ・購入への流れ
といった部分を軽視してしまうと、結局は成果につながりにくくなります。
検索結果で1位を取れていたとしても、
- ページの内容がニーズとズレている
- 読み終わった後の次の一歩が分からない
という状態では、ビジネスの数字は動きません。
もし「さらに目標に届いていないのは、もっとたくさんのキーワードで上位表示していないからだ」とだけ考えているとしたら、一度立ち止まって、ページの中身やその後ろの導線に目を向けてみる価値があります。
2. 「良いコンテンツなら、いつか誰かが見つけてくれる」という考え方
逆の極端な例が、「良いコンテンツを出していれば、そのうち誰かが見つけてくれて、気づけば集客できるようになっているはずだ」という考え方です。
コンテンツの質を大事にすること自体は、とても良いことです。ただ、どれだけ内容の良いコンテンツでも、
- Googleに対してそのテーマや価値が正しく伝わっていない
- そもそもインデックスされていない
という状態であれば、その価値は検索ユーザーに届きません。
つまり、
- 技術的な意味で、検索エンジンにきちんと理解してもらう
- そのうえで、コンテンツの中身を磨いていく
という二つの視点がそろって初めて、コンテンツが集客に結びついていきます。
「良いコンテンツを作っていれば、自然と見つけてもらえるだろう」と期待しすぎず、検索エンジンに対してもきちんと「伝える努力」をすることが現実的です。
検索エンジン対策からコンテンツ活用までを「一本の流れ」で見る
ここまでの話をまとめると、取り組むべきことは次のような一連の流れとして整理できます。
- サイトの技術的な土台を整える
- クロール・インデックスされやすい構造にする
- ページごとのテーマをはっきりさせる
- キーワードとページの対応を設計する
- どの検索キーワードの人に、どのページを見てもらうか決める
- コンテンツをストーリーとして組み立てる
- 悩みの整理→解決の方向性→自社サービスという流れを考える
- Search Consoleやアクセス解析でボトルネックを見つける
- どこで離脱が多いか、どのキーワードからの流入が少ないかを確認する
- ボトルネックを一つずつ解消していく
この流れ全体を、「名前」で分断せずに、一つの仕組みとして考えていくことをおすすめします。
自社の取り組みを振り返るときのチェックポイント
最後に、自社のこれまでの施策を振り返るときに役に立つ視点をいくつか挙げておきます。
- 検索順位ばかりを見ていて、コンテンツの中身や導線をあまり見ていない部分はないか
- 逆に、コンテンツの中身にだけ集中して、Search Consoleなどで検索からの入り口をあまり見ていない部分はないか
- 検索結果→ランディングページ→サイト内回遊→問い合わせ・購入という流れを、一度通しで眺めたことがあるか
- どこがボトルネックになっているのかを、ツールを使って定期的に確認できているか
もし「どこかに偏っていたかもしれない」と感じるところがあれば、一度全体を通しで眺めてみて、「検索から来た人のおもてなし」という視点で改善していく体制に切り替えていくと、成果が出やすくなります。
まとめ:定義よりも「検索から来た人へのおもてなし」を考える
改めてまとめると、
- 「SEOとは何か?」を厳密に定義しようとすること自体は、実務ではあまり生産的ではない
- 「これはSEO」「これはコンテンツ」と線引きするより、「検索から来た人にどう応えるか」という一貫した視点で考えた方が動きやすい
- 検索エンジンへの配慮、キーワードとページの設計、コンテンツの中身、分析による改善は、本来すべて一本の流れの中にある
- 検索順位だけを見る/コンテンツだけを見て検索を無視する、といった極端な考え方はどちらも成果から遠ざかりやすい
あまり「定義」にこだわりすぎず、検索エンジンから来てくれた方に対して、きちんとおもてなしができているかどうか。その視点で、自社サイト全体を見直してみていただければと思います。
この回で触れているお知らせ(2017年当時)
このPodcast回では、最後に次のようなお知らせもしています。
- 組織の作り方についての「組織ガイドブック」のダウンロードの案内
- 4月号ニュースレター(製本版+質問への回答を含んだ注釈版)のお届けについて
- 月に一度、池袋での対面無料相談会のご案内
いずれも2017年当時のご案内です。
【2025年注記】 現在の提供状況や内容は当時と変わっている可能性があります。最新の情報については、ラウンドナップWebコンサルティングの公式サイトをご確認いただければと思います。
関連リンク
この記事の内容と関連する、公式ドキュメント・ヘルプへのリンクです。詳しい仕様や最新情報を確認する際の入り口としてご活用ください。
- Google 検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド
- 構造化データ マークアップとは | Google 検索セントラル
- Search Console の概要
- [GA4] 次世代のアナリティクス、Google アナリティクス 4 のご紹介
- Google 検索とは何か、その仕組みとは
FAQ:このPodcast回に関してよくありそうな質問
- Q1. 「SEOとは何か?」という定義は、決めておいた方が良いですか?
- A1. きっちりした定義を決めること自体は、実務ではあまり役に立ちません。むしろ、「検索から来た人にどう応えるか」という視点で、必要なことを一つの流れとして考える方が現実的です。
- Q2. 「どこまでがSEOで、どこからがコンテンツか」といった線引きは気にするべきでしょうか?
- A2. 線引きにこだわりすぎると、「これは自分の担当範囲ではない」といった発想になりがちです。検索エンジンへの配慮からコンテンツの中身、分析までを一つの仕組みとして捉える方が、結果として成果に繋がりやすくなります。
- Q3. 良いコンテンツを作っていれば、そのうち自然と集客できるようになりますか?
- A3. コンテンツの質はとても重要ですが、それだけでは不十分です。Googleに対してテーマや価値が正しく伝わるようにしておかないと、せっかくのコンテンツが検索ユーザーに届きにくくなります。
- Q4. 検索順位だけを追いかけていれば大丈夫でしょうか?
- A4. 検索順位は大事な指標の一つですが、ページの中身やサイト全体の導線を見ないままだと、ビジネスの数字にはつながりにくいです。Search Consoleやアクセス解析を使って、検索から成果までの流れ全体を確認することが大切です。
- Q5. 2017年当時の考え方は、今でも通用しますか?
- A5. ツールや具体的な仕様は変わってきていますが、「検索から来た人に価値を正しく伝える」「検索エンジン対策とコンテンツを一本の流れとして考える」という基本的な考え方は、今でも通用します。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/