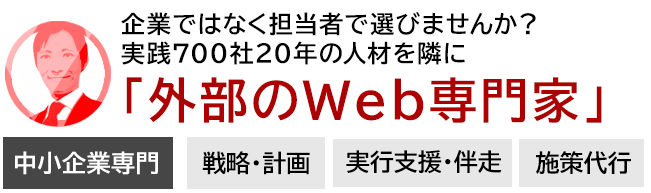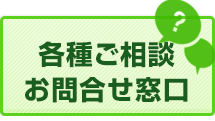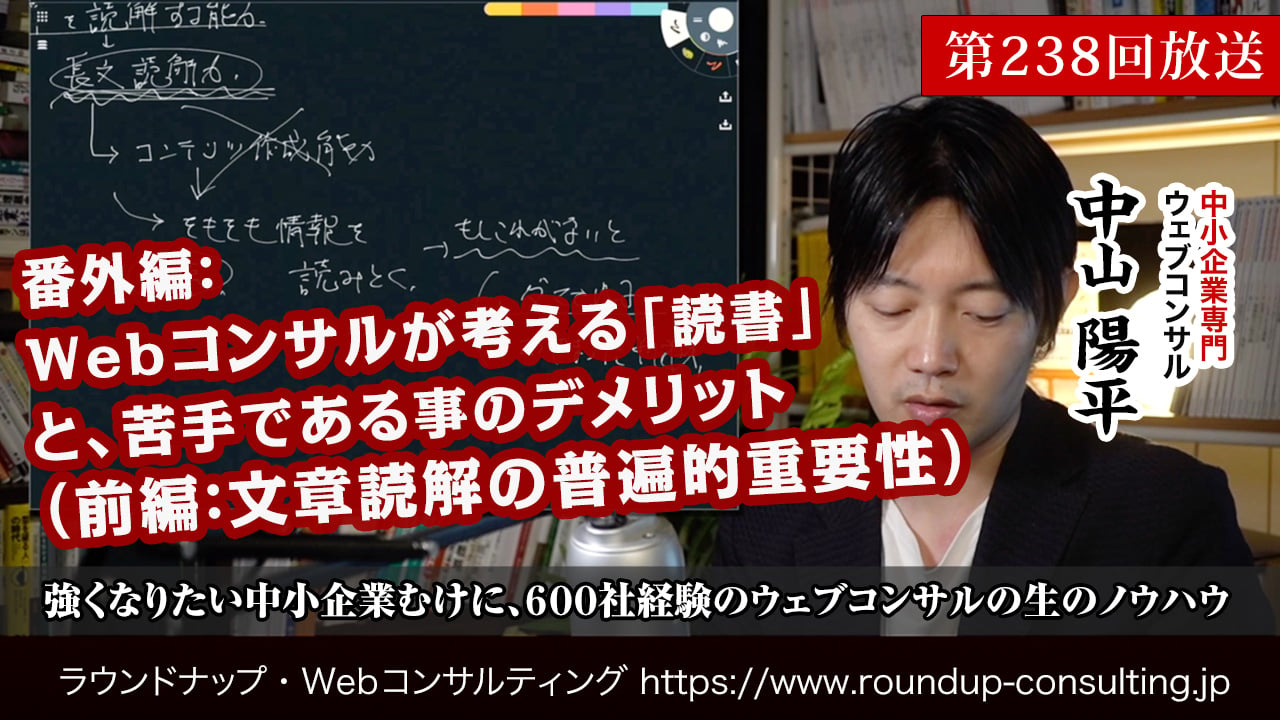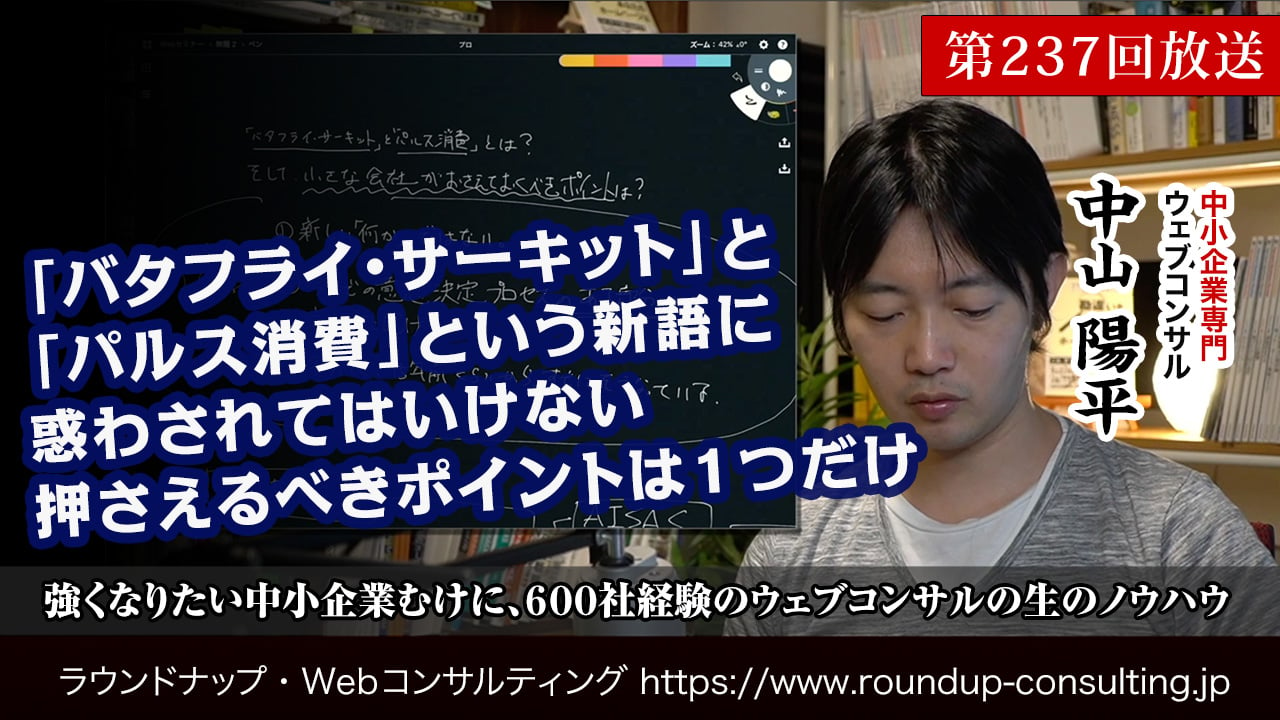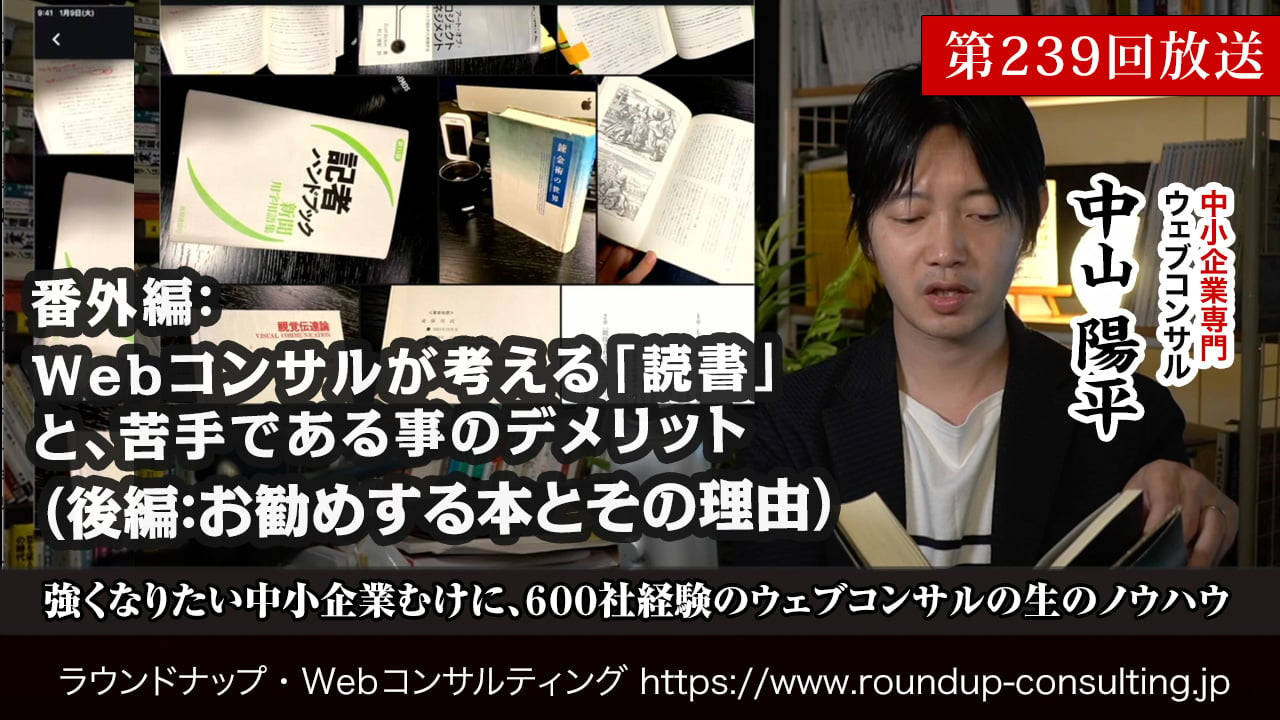Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
この記事では、ある種の「読書」、つまり文章を読み解く力が、なぜ今のウェブ時代でもビジネスにとって普遍的に重要なのかを、現場のコンサルティング経験を交えながらお話しします。
この記事で分かること
- 動画や音声コンテンツが主流になりつつある今でも、「文章読解力」がビジネスに不可欠な理由
- 読解力が弱いと、なぜ「騙されやすくなる」「判断を誤りやすくなる」のか
- デザイナーから中小企業向けWebコンサルティングへと至った経験から見える、「読書」とマネジメント・マーケティングの関係
- 小さな会社が自走するための「アクションとフィードバックのループ」と、その土台としての国語力
- コンサルに依存しすぎず、自分たちでインプットとアウトプットを回せる組織になるための考え方
音声で話している内容を、そのまま文章として読めるように整えていますので、ポッドキャストを聞いていない方でも、ひとつの読み物として読んでいただけます。
Facebookの「好きな本」バトンから考えた、読書とビジネス
もともとのきっかけは、Facebookで回ってきた「好きな書籍を紹介する」バトンのようなものです。ミクシィの時代からのインターネット文化に馴染みがある方なら、こういった「バトン」が回ってくる感覚を、何となく覚えているかもしれません。
ただ、Facebookで1冊ずつ丁寧に紹介していく時間をなかなか取れなかったので、「自分の考え方を形作っている本の一部」を紹介する前段として、そもそも なぜ今の時代でも読書や文章読解がこれほど重要なのか を整理しておきたいと思いました。
同時に、これからの時代に、中小企業が情報をきちんと活用していくためには何が必要なのか、そのための仕組みやイメージも併せてお伝えしたい、というのがこの回のテーマです。
情報発信の民主化とテキストコンテンツの位置づけ
マスコミだけの特権だった「発信」が、誰でもできるようになった
昔は、一般の人が多くの人に向けて情報を発信しようと思っても、せいぜい対面での話や紙の資料などに限られていました。テレビや新聞、専門誌など、いわゆるマスメディアや専門家だけが「一般向けの情報発信」を本格的に行える世界だったわけです。
そこに登場したのが、ウェブサイトやPDF、ブログ、そして今ではSNSです。これによって、 情報発信の民主化 が起こりました。つまり、マスコミや一部の専門家だけでなく、誰もが自分の考えやノウハウを世の中に向けて発信できるようになった、ということです。
この流れの中で、最初に広がったのはテキスト中心のコンテンツでした。ウェブページ、PDF、メールマガジンなど、基本は「文章を読む」ことが前提の媒体です。そこに、今は動画や音声コンテンツが一気に広がってきた、という流れになります。
動画の時代でも、文章を読めないと厳しい理由
今は動画や音声コンテンツが非常に充実しています。YouTubeを見れば、あらゆるジャンルの情報があり、ポッドキャストでも多くの話が聞けます。
そのため、 「文章って、そこまで必要ないのでは」 と感じる場面もあるかもしれません。しかし、私は 文章を読み解く力がないと、これからの時代はかなり厳しい と考えています。
ここで言っているのは、単に文字が読めるかどうかではなく、 長い文章を読み、背景や文脈、意図まで含めて理解する力、 いわゆる「長文読解力」です。
本を読むのがあまり得意ではない、ほとんど本を読まずに来た、といった話を耳にすることがあります。軽い自己紹介のようなノリで話す方もいれば、本当に困っていて口にしている方もいると思います。
ただ、これは いつからでも鍛え直せる部分 ですし、ビジネスという観点で言えば、 読解力が弱いことは、かなり大きなディスアドバンテージであり、欠点と言ってしまって差し支えない と考えています。
もちろん、さまざまな事情で、長文を読むこと自体が難しい方もいらっしゃいます。そのケースはまた別の配慮が必要になりますので、ここでは 「読もうと思えば読めるけれど、あまり読んでこなかった」 という方を前提に話を進めます。
読解力が弱いと、なぜ「騙されやすくなる」のか
文章を読む力が弱いままだと、どうなるでしょうか。
表面的に気持ちよく聞こえるキャッチコピーや、扇動的な言葉に引っ張られやすくなります。論理が破綻していたり、前提条件があやふやな話でも、その場のノリで納得してしまい、冷静に見ればおかしい内容を見抜けないまま受け取ってしまうことが増えます。
結果として、 情報の解釈を間違え、誤った判断をしやすくなる わけです。
特に、映像や動画は、その性質上、見る人の感情や印象に強く働きかけます。歴史を振り返ると、映像というメディアは娯楽や記録だけでなく、 政治的な扇動の場面でも巧みに利用されてきました。 「映像を巧みに利用する権力者」のイメージを持っていただくと分かりやすいと思います。
こうした映像の強い力に対して、 中身のロジックを言葉として読み解く力 がないと、知らないうちに「言われるがまま」になってしまう危険性が高まります。
読解力とビジネスの関係:デザイナーから中小企業支援へ
DTPデザイナーからWebデザイナー、そしてトータルサポートへ
私自身のキャリアの話をすると、もともとは紙媒体のレイアウトや入稿データを作る DTP(紙のデザイン制作) のデザイナーからスタートしました。それからWebデザイナーになり、Webの世界のいろいろなことを経験していきました。
当時は、 「よく切れる刃(は)ナイフのように、腕の良いデザイナーであれば、それだけでやっていけるだろう」 と考えていた時期もあります。とにかく技術を磨くことで精一杯で、あまりそれ以上のことを深く考えていなかったわけです。
しかし、仕事の範囲が広がり、関わる企業の課題が複雑になるにつれ、 デザインの技術だけでは、変えられることに限界がある と感じるようになりました。
- 社内の人を動かすには、マネジメントの知識が必要
- お客さんの先にいる「そのまたお客さん」を動かすには、マーケティングの考え方が必要
人の行動がどう変わるのか、自分自身がどう動かされるのか、そういったことを含めて理解しなければ、企業の成果にはつながっていきません。そこで今は、 小さな企業をトータルにサポートする という形でコンサルティングを行っています。
「依存させない」コンサルティングというスタンス
ここで少し、コンサルティングのスタンスについてもお話しします。
一般的なコンサルティングは、 「ずっとそばにいて、困ったら相談する存在」 というイメージが強いと思います。顧問契約という形で、企業のある領域に長く関わり続けるスタイルですね。
一方で、私が目指しているのは、少し違う姿です。
もちろん、最初のうちはこちらが関わる割合が高くなります。ただ、そこから時間をかけて、 できるだけ自分たちの関与を減らしていく ことを前提にしています。
言い換えると、 依存されない・依存させないコンサルティング です。最終的には、 自分がいなくなっても会社がきちんと回っている状態 をゴールにしています。
もちろん、例外はあります。長く一緒に頑張ってきた会社さんから、 「ちょっと相談に乗ってほしい」「ざっくばらんに話を聞いてほしい」 という形で、費用を抑えながらお付き合いを続けているケースもあります。
ただ基本線としては、 「いつまでもいなければ成り立たないコンサル」ではなく、 いずれ自走できるようになってもらうことを前提としたコンサル を目指しています。今の言葉で言えば、 カスタマーサクセス(お客さんの成功をゴールにして、継続的に支援する考え方) にも通じる部分があるかもしれません。
中堅以上の企業では、その後もやるべきことがどんどん増えていくため、結果として長く伴走するケースも多いのですが、小さな会社の場合は 「まずはここまでやって、しばらく体力を蓄えたい」 といったニーズも多いです。
そういうときは、 「ここまでできるようになったら、あとは本当に困ったときだけ随時相談してください」 という形で、私の関与の比率を1割程度まで落としていきます。
アクションとフィードバックのループと、国語力
ビジネスが回る会社に共通する「4つのステップ」
では、会社が自分たちで動けるようになるために、何が必要なのでしょうか。
私がよくお勧めしているのが、 アクションとフィードバックのループ を回すことです。より具体的に言うと、次の4ステップです。
- 適切な場所からの情報を集める(インプット)
- それをもとに施策を決めて動く(アクション)
- その結果として実際に起きた変化を観察する(オブザベーション)
- 得られた気づきを次のインプットとして活かす(フィードバック&インプット)
このループを、社内・社外の情報を組み合わせながら、ぐるぐると回していきます。
社内と社外、どちらの情報も「コレクト」に解釈できるか
1つ目のステップである「インプット」には、大きく分けて2種類あります。
- 社内からの情報(カスタマーサポート、営業、アンケート、社内からの要望や苦情など)
- 社外からの情報(お客さんの声、事例やノウハウ記事など外部のコンテンツ)
ここで重要になるのが、 情報をコレクト(correct=正確・適切)に解釈できるかどうか です。
誰が、どの立場から、どんな背景でその情報を発しているのか。何が事実で、何が解釈なのか。そこを読み分けていく力が必要になります。
つまり、ここで効いてくるのが、 文章を読み解く国語力 です。単に「文字が読める」だけでなく、
- 文脈を追い、
- 因果関係をつかみ、
- 前提と結論を切り分けて理解する
といった力が問われます。
インストラクションとしてのアウトプットも、国語力の一部
インプットができたら、次はアクションです。ただ、ここでいきなり 「じゃあやろう」 と号令だけかけてもうまくいきません。
現実には、ほとんどの場合、 人に動いてもらう 必要があります。自分自身が手を動かす場面もありますが、チームや外部パートナーに依頼することも多いはずです。
このとき重要になるのが、 インストラクション(具体的な指示・伝達) です。つまり、 得られた情報を、相手にとって分かりやすい形のアウトプットに変換して伝えられるかどうか ということです。
やるべきことが頭の中にはあっても、
- 誰に、
- 何を、
- どの順番で、
- どこまでのレベルでやってほしいのか
が言語化されていないと、相手は正しく動けません。
ここでもやはり、 国語力=情報を言葉に変えて伝える力 が効いてきます。
世の中には、 「インプットは苦手だが、アウトプットだけはうまい人」 もいれば、 「読むのは得意だが、人に伝えるのが苦手な人」 もいます。
しかし、企業としてスピード感を持って動いていくためには、 インプットとアウトプットの両方を、一定レベル以上で回せる人 がいることがとても重要です。
自分で情報を集めてコレクトに解釈し、それをインストラクションとしてアウトプットし、周りに動いてもらう。この一連の流れはすべて、 文章を読み書きする国語力から直結している部分 だと考えています。
フィードバックこそ最重要のインプット:ラウンドナップという社名の意味
アクションを起こしたら、必ず何かが返ってくる
アクションを起こすと、その結果として必ず何かしらの反応が返ってきます。ここを私は、 フィードバック と呼んでいます。
ここで大事なのは、 「アクセス解析の数字をなんとなく眺める」 といったレベルではありません。
自分たちが行ったアクションに対して、 具体的にどんな変化が起きたのかを把握しようとする態度 と、 その変化を意味づけて次に活かす視点 が重要です。
このフィードバックは、そのまま次のインプットになります。そして、実はこの フィードバックからのインプットが、インプットの中で最も重要 だと考えています。
巷のノウハウよりも、自社のフィードバックが圧倒的に重要
世の中には、「こうすればうまくいく」といったノウハウ記事や成功事例がたくさんあります。そういったものも、もちろん参考にはなります。
ただ、私の感覚としては、 巷のノウハウや事例コンテンツといったインプットは、そこまで重要ではない と感じています。
なぜかというと、
- 第三者の事例であり、自社とは前提が違う
- 背景や細かい条件がすべて開示されているとは限らない
- 自分たちで結果を追いかけて検証することが難しい
といった理由があるからです。
それよりも優先すべきは、 自分たちが実際に行ったアクションに対して、目の前のお客さんがどう反応したのかというフィードバック です。
私が提案している「アクションとフィードバックのループ」は、 皆さんとお客さんとの間で、このサイクルをぐるぐる回していく ことで、
- マーケティングの仕組み
- 商品・サービスそのもの
- 社内の動き方
などが、螺旋を描くように少しずつ良くなっていくイメージです。
この「螺旋を描きながら上がっていく」イメージから、 ラウンドナップ(Round+Up) という社名をつけています。
大きなツールがなくても、ループが回れば成長できる
このループをしっかり回せるようになると、実はそれほど大きなリソースは必要ありません。
- 高価なツールを無理に導入しなくてもよい
- 費用対効果が見えた段階で、必要なものだけ入れればよい
小さな会社にとって、これは非常に効率の良いやり方です。まずは 自社とお客さんとの間で、アクションとフィードバックのループを回せるようになること が、Webの世界に本格的に入っていくための前提条件だと考えています。
小さな会社がWebの世界で「騙されず、自走する」ために
ここまでお話ししてきたように、私がコンサルティングを通じてやりたいのは、 小さな会社がWebの世界に入り、そこで騙されずに、自分たちの力で頑張っていける状態をつくること です。
アクションとフィードバックのループを、自分たちで回せるようになる。インプットもアウトプットも、国語力を土台として自前でできるようになる。
そこまで行けば、あとはWebの世界には良い会社さんやプレイヤーがたくさんいますから、
- ノウハウも
- 資金も
- リソースも
ある程度そろってきた段階で、そういった会社さんに任せていけばよい、という考え方です。
私自身は、 Webの世界にスムーズに入っていけるようにエスコートする役割 をメインの仕事だと捉えています。
その前提にあるのが、今回のテーマである 読書=文章読解の普遍的重要性 です。文章を読み、文脈をつかみ、情報をコレクトに解釈し、インストラクションとしてアウトプットし、フィードバックをインプットとして回していく。
この一連の流れの土台にあるのが、国語力だと考えています。
まとめ:読解力は、読書だけでなく事業そのものを支える
最後に、改めてポイントを整理します。
- WebサイトやSNSによって、情報発信は「情報発信の民主化」が進み、誰でもできるようになった
- 動画や音声がどれだけ広がっても、長文読解力=文章を読み解く力は、ビジネスにとって欠かせない
- 読解力が弱いと、扇動的なメッセージや論理破綻した情報を見抜けず、判断ミスや「騙される」リスクが高まる
- インプット(情報収集)とアウトプット(インストラクション)の両方を言葉で扱える国語力が、アクションとフィードバックのループを回すエンジンになる
- 巷のノウハウよりも、自社のアクションに対するお客さんのフィードバックこそ、最優先のインプットとして大切にすべき
- 小さな会社が自走できるようになることをゴールに、「依存させないコンサル」としてWebの世界へのエスコートを行っている
音声のほうでは、このあと実際に私自身の考え方を形作っている書籍の話に入っていきます。この文章では、 その前段となる「読書(文章読解)の普遍的重要性」 の部分を中心にお届けしました。
関連リンク
読解力や読書、デジタル活用、情報リテラシーに関連する公的機関の情報へのリンクです。あくまで参考資料としてご覧ください。
- 令和5年度「国語に関する世論調査」の結果概要(文化庁)
- 子どもの読書活動に関する調査(国立国会図書館・国際子ども図書館)
- デジタル・IT化支援(経済産業省 中小企業庁)
- 教育・学習(一般向け)|ここからセキュリティ!(独立行政法人情報処理推進機構 IPA)
よくある質問
- Q1. なぜ今の時代でも、文章読解力がそんなに重要なのですか。
-
動画や音声コンテンツが増えても、情報のもとになっているのは多くの場合テキストです。文章を読み解く力が弱いと、 表面的なキャッチコピーや扇動的なメッセージに流されやすくなり、論理の破綻や前提条件の違いを見抜きにくくなります。 その結果、ビジネス上の判断を誤りやすくなるため、長文読解力は今でもビジネスの基礎体力の一つだと考えています。
- Q2. 読解力が弱いと、ビジネスでは具体的にどんな不都合が起きますか。
-
一番大きいのは、情報の解釈を間違えやすくなることです。間違っているロジックや前提のズレに気づけず、 間違った施策を選んでしまったり、扇動的な言葉に影響されて判断してしまったりします。 特に映像や動画のような感情に訴えかけるメディアに対しては、言葉としてのロジックを読み解く力がないと、 知らないうちに意図された方向に引っ張られやすくなります。
- Q3. 小さな会社でも実践しやすい「アクションとフィードバックのループ」とは何ですか。
-
私が提案しているのは、次の4つのステップをぐるぐる回す方法です。
- 適切な場所からの情報を集める(インプット)
- それをもとに施策を決めて動く(アクション)
- その結果として実際に起きた変化を観察する(オブザベーション)
- 得られた気づきを次のインプットとして活かす(フィードバック&インプット)
特別なツールがなくても、自社とお客さんとの間でこのループを回せるようになれば、商品やマーケティングの質は少しずつ良くなっていきます。
- Q4. 「依存させないコンサルティング」とは、どういうゴールを目指しているのですか。
-
一般的な顧問コンサルは、長くそばにいて相談相手であり続けるスタイルが多いと思います。 私の場合は、最終的に「自分がいなくなっても会社が回る状態」をゴールにしています。 最初は関与の割合が高くても、インプットとアウトプットのやり方を一緒に作り、アクションとフィードバックのループを回せるようになったら、 徐々にこちらの比率を下げていきます。結果として、本当に困ったときだけ随時相談してもらう形に近づけていくイメージです。
- Q5. 読書があまり得意ではないのですが、今からでも鍛えられますか。
-
読解力は、いつからでも鍛え直せる部分だと考えています。事情によって長文を読むこと自体が難しい場合は別ですが、 「読もうと思えば読めるが、あまり読んでこなかった」という状況であれば、 まずは書籍などのテキストを通じて情報を吸収し、内容を自分の言葉で説明してみる、というところから始めるのがおすすめです。 ビジネスでは、読解力の弱さは大きなディスアドバンテージになりやすいため、今からでも意識的に鍛えていく価値があります。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/