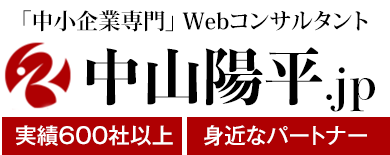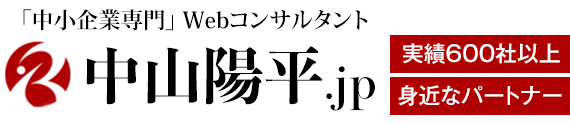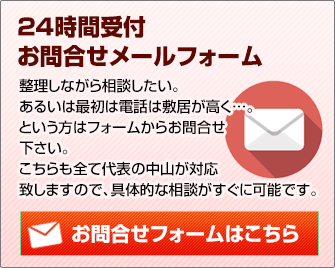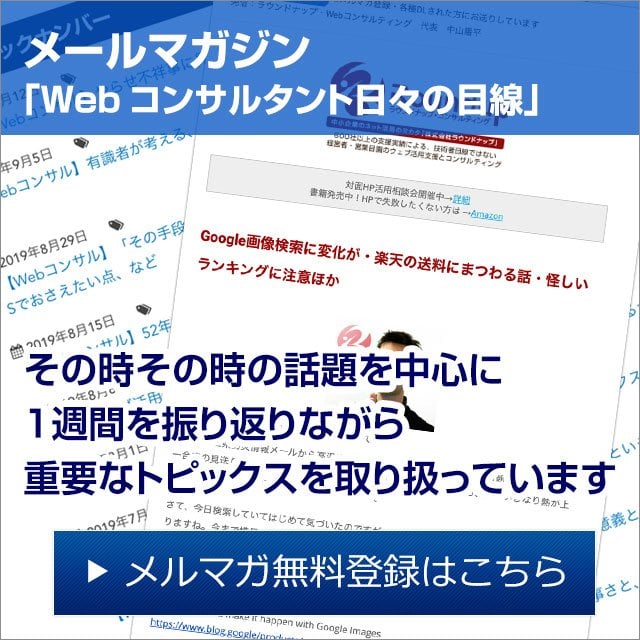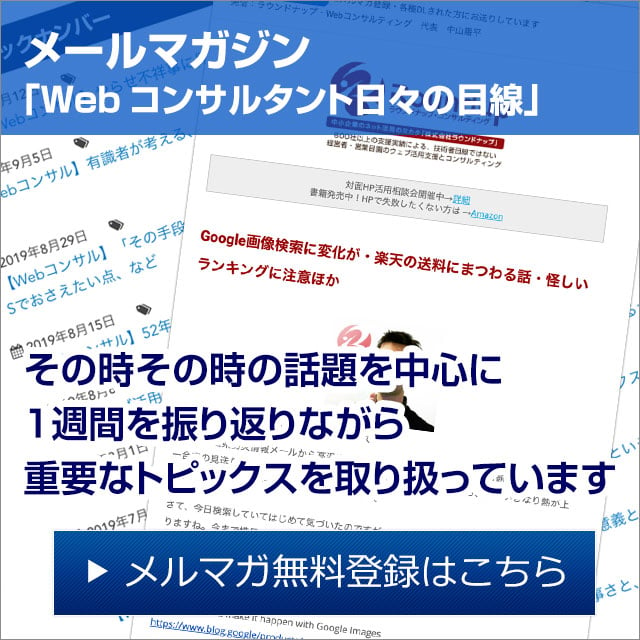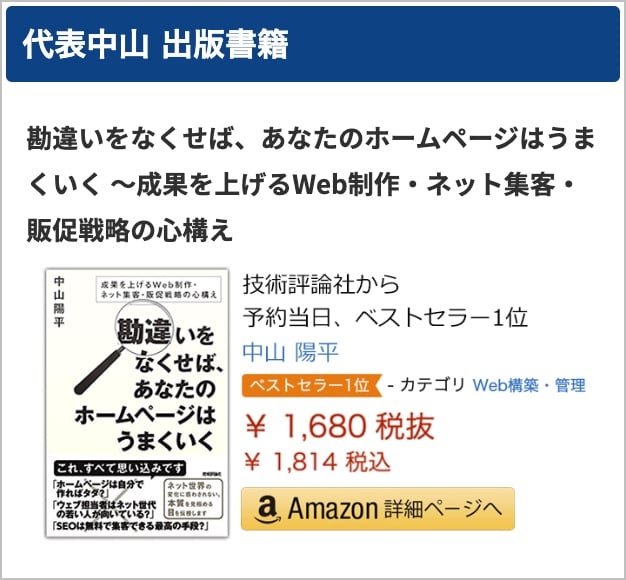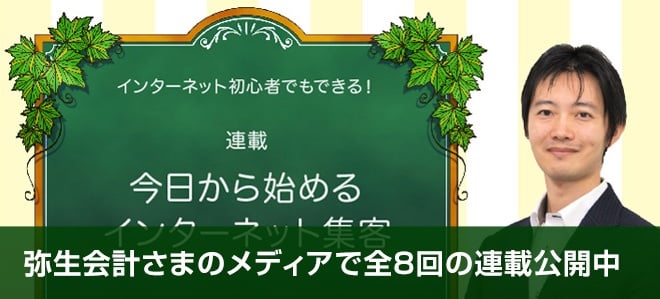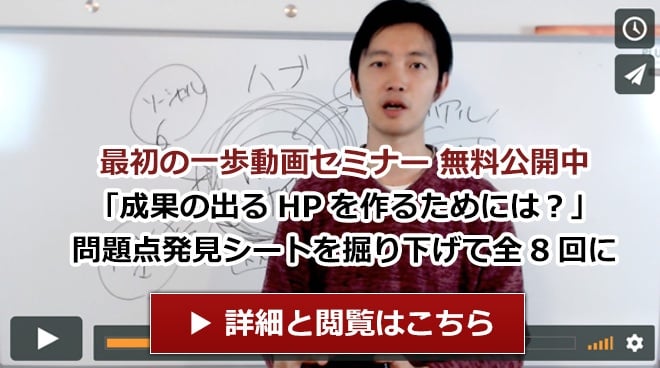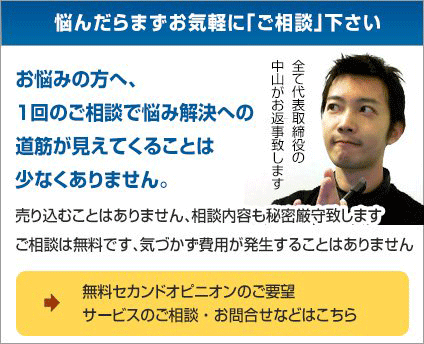このサイトで聞く
Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Android | RSS | More
内容について
こんにちは、ラウンドナップWebコンサルティングの中山です。
競合サイトの流入キーワードや人気ページがわかる便利なツール。しかし、表示される数字を鵜呑みにすると、Web戦略の方向性を見誤る危険があります。なぜなら、それらはあくまで参考値だからです。今回は、ツールの数字とどう向き合うべきか、本当に見るべきポイントはどこなのかを、具体的なツールを例に挙げて解説します。
- 例としての競合調査ツールの正しい見方と注意点
- 数字の根拠の重要性と検証の必要性
- AhrefsやSEM Rushなどのツールの信頼性と良くも悪くもの限界
- 数字以外のデータの有用性と活用方法
- ツールのヘルプやブログの確認の重要性
このPodcastが解決できるFAQ
- Q1. 競合調査ツールが示すDR(ドメインレーティング)などのスコアは、どれくらい信頼できますか。
- A1. 参考程度に留めるべきです。多くのツールのスコアは、主に外部リンクの量や質を基に算出された「外部要因指標」です。サイトのコンテンツ品質などの内部要因は加味されていないため、スコアが低いサイトでも検索上位に表示されることは十分にあり得ます。
- Q2. 競合調査ツールのトラフィック予測が、実際の感覚とずれているのはなぜですか。
- A2. ツールが全ての検索キーワードを網羅しているわけではなく、検索順位の変動も激しいため、あくまで「推定値」だからです。特にニッチな業界では、データ母数が少なくなるため誤差が大きくなる傾向があります。正確な数値ではなく、大まかな傾向を把握するために使いましょう。
- Q3. ツールで表示されるCPC(クリック単価)が高いキーワードを狙えば、売上につながりやすいですか。
- A3. 必ずしもそうとは言えません。ツールが示すCPCは、様々な要因で常に変動する広告単価の、ある一時点を切り取った概算値に過ぎません。そのキーワードが本当に成果に繋がるかは、実際に広告をテスト出稿したり、コンテンツを公開してユーザーの反応を見たりして判断することが重要です。
- Q4. ツールが示す数字が参考程度なら、どうやって競合を調査すればよいのでしょうか。
- A4. 数字以外の情報を活用することが有効です。例えば「どのようなキーワードで流入しているか」「どのページの人気が高いか」といった情報は参考になります。最も重要なのは、ツールだけに頼らず、実際に競合のサイトを自分で見て、サービスを利用した顧客に話を聞くなど、本質的な調査を行うことです。
- Q5. 高額な海外製のSEOツールは、やはり契約したほうがよいのでしょうか。
- A5. 必須ではありません。まずはGoogleが提供している無料の純正ツール(サーチコンソール、キーワードプランナー等)を最大限活用することをお勧めします。そこで得られる一次データを分析し、基本的な施策をやりきった上で、必要性を感じれば検討するのがよいでしょう。
配信内容の詳細
はじめに:競合調査ツールのデータ、正しく見れていますか
多くのWeb担当者の方が、競合の動向を知るために競合調査ツールを活用しています。競合がどんなキーワードで集客し、どのページに人気があるのか。こうした情報はビジネス上、非常に魅力的です。
しかし、そこで表示される数字の根拠を正しく理解していないと、施策の方向性を見誤る可能性があります。ツール上のデータと、実際の競合の状況が大きく乖離していることも少なくありません。今回は、こうしたツールの注意点と、データとの正しい向き合い方について解説します。
結論:ツールの「数字」は参考程度に。「数字以外」の情報を活用する
結論から言うと、競合調査ツールで表示される各種の「数字」は、検証した上で参考程度に捉えるのが賢明です。一方で、流入キーワードや人気ページのURLといった「数字以外」の情報は、自社の施策を考える上で参考にできます。このように、情報の種類によって信頼度を切り分けて考えることが重要です。
注意すべきツールの指標とその理由
指標1:DR (ドメインレーティング) などのサイト評価スコア
Ahrefsなどのツールに表示されるDR(ドメインレーティング)やUR(URLレーティング)といったスコア。これらを基に自社と競合を比較している方も多いかもしれません。しかし、これらのスコアが何を表しているかを理解することが大切です。
Ahrefsのヘルプにも明記されていますが、DRは、サイトのバックリンク(被リンク)の全体的な強さを示す「外部要因指標」です。つまり、サイトのコンテンツ品質といった内部的な要因は、評価の対象に含まれていません。
- DR (ドメインレーティング):ドメイン全体の外部リンクの強さを評価する指標。
- UR (URLレーティング):特定のURL(ページ単位)の外部リンクの強さを評価する指標。
DRが高いからといって必ずしも競合に勝てないわけではなく、逆にDRが低くても上位表示は可能です。これらのランキングは、あくまで外部リンクに関する評価であると認識しておきましょう。
指標2:オーガニックトラフィック (自然検索からの流入数)
ツールの「推定トラフィック」を参考に、施策を検討することもあるでしょう。しかし、これもあくまで推定値であり、特にニッチな業界ほど実際の数値との誤差が大きくなる傾向があります。
ツール提供元も、その精度が限定的である理由を次のように説明しています。
- サイトがランクインする可能性のある全ての検索キーワードを把握しているわけではない。
- 検索ボリュームのデータ自体が、Googleでさえ概算値しか公開していない。
- 検索順位は常に変動しており、クリック率もあくまで推定でしかない。
こうした理由から、トラフィックの見積もりは文字通り「見積もり」として捉え、一喜一憂しないことが大切です。
指標3:CPC (クリック単価)
「CPCが高いキーワードは購買意欲が高く、狙い目だ」という話を耳にすることがあります。しかし、ツールが示すCPCデータの正確性は、他の指標よりもさらに低いと考えた方がよいでしょう。
実際の広告運用では、クリック単価は様々なターゲティング条件や入札戦略によってリアルタイムで変動します。ツールが表示するCPCは、その複雑な状況を単純化した概算値に過ぎません。特にニッチなキーワードでは、数値が突然跳ね上がったりゼロになったりすることも頻繁にあります。
「この業界は単価が高い」「このキーワードは安い」といった大まかな傾向を見るのには役立つかもしれませんが、その瞬間のデータだけで重要な戦略を決定するのは避けるべきです。
では、どうすれば良いのか:本質的な調査への回帰
数字の出どころはGoogleの一次データ
では、信頼できるデータはどこにあるのでしょうか。基本的には、Googleが提供するサーチコンソールやキーワードプランナーなどの一次データを正しく見ることが最も確実です。高額なサードパーティーツールに夢を見るのではなく、まずは純正ツールを使いこなすことから始めましょう。
データだけでなく「現実」を見る
最も重要なのは、ツールが示すデータだけに頼らないことです。優れた店舗が競合を調査する際、データ分析だけでなく、実際に店舗へ足を運ぶはずです。Webサイトも同じです。
- 競合のサイトを実際に隅々まで見てみる。
- 競合のサービスを利用したことがある顧客に話を聞いてみる。
- 自社のサイトと比較して、何が違うのかを考える。
こうした地道な調査こそが、商売の原点であり、本当に価値のある洞察に繋がります。
まとめ:ツールと賢く付き合い、自ら考える力を養う
競合調査ツールは、使い方を間違えなければ強力な味方になります。しかし、その数字に振り回されてはいけません。ツールの特性を理解し、あくまで参考情報として活用する姿勢が求められます。
そして最終的には、外部のパートナーに任せきりにするのではなく、自社でもデータを読み解き、対等に議論できる知識を身につけることが不可欠です。そうした姿勢が、未来のビジネスを強くしていくのだと思います。
続きはPodcastをご覧下さい。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ)
https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892 - YoutubePodcast(旧:GooglePodcast)
https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN - Spotify
https://open.spotify.com/show/0yBHyUelJHFtby5uD06UxU?si=fL7RT_T9RPivEu7cAjhqFA - Amazon Music
https://amzn.to/3uV8vT7
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。
https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/