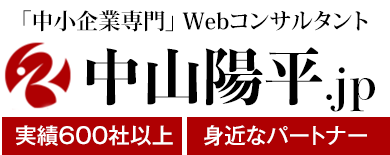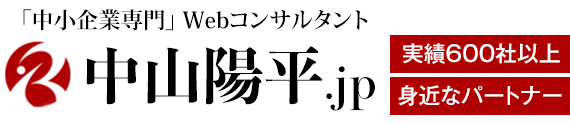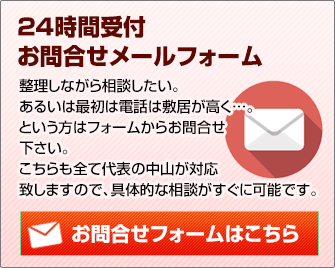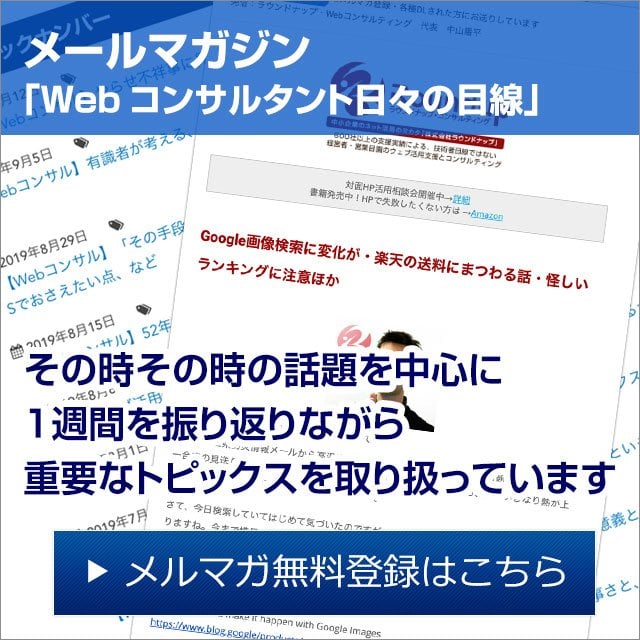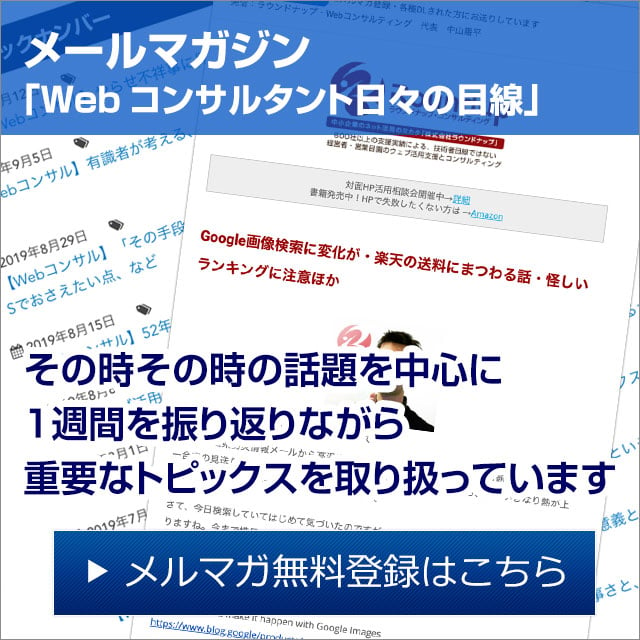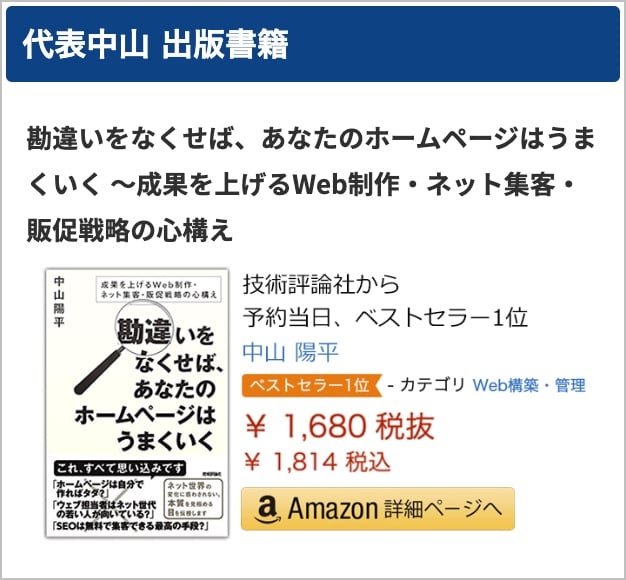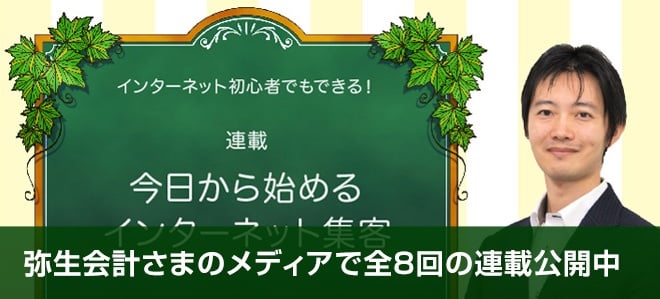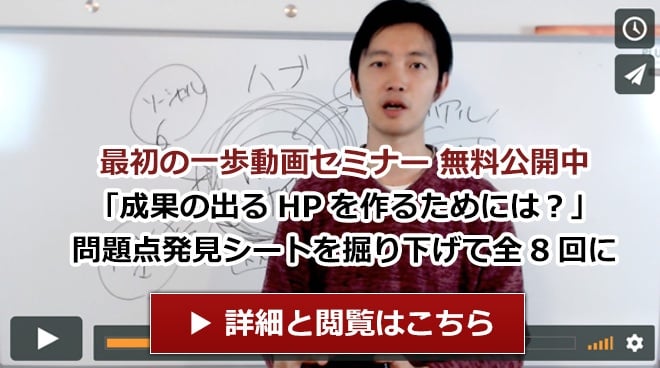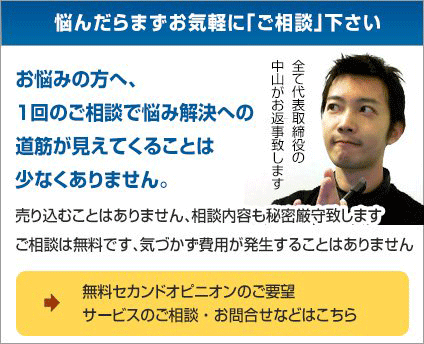このサイトで聞く
Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Android | RSS | More
内容について
テレビ、新聞、SNS。どの情報が本当に信頼できるのか。この問い自体に、実はあまり意味はないのかもしれません。情報過多の時代、中小企業の経営者が事業の意思決定を誤らないための、情報との健全な付き合い方、情報のフィルタリング方法について解説します。溢れる情報に振り回されず、自分なりの判断軸を持つためのヒントをお届けします。
- オールメディアという言い方の恣意性
- 今すぐ自分が何か判断すべき状況なのか?
- いっちょ噛みしたいという欲望から離れる
- 映像メディアの威力には注意した方が良い
- 一貫性と自分の価値基準を持つことは重要か
今から始めるべき準備と心構えとは?
このPodcastが解決できるFAQ
- 情報が多すぎて、どのメディアを信じればいいかわかりません。どうすれば良いですか。
- 特定のメディアを盲信するのではなく、すべての情報には何らかの意図(バイアス)があると理解することが重要です。情報をすぐに判断せず、一旦「そういう考え方もある」と受け止め、ご自身の事業で意思決定が必要なタイミングで、改めて多角的に見直す姿勢が求められます。
- SNSの情報は信頼しても良いのでしょうか。
- SNSの情報は、多くの人の意見が可視化されやすいため、心理的な影響を受けやすい側面があります。周りの評価に流されず、ご自身の判断軸で考える訓練が必要です。信頼できる専門家をフォローし、情報を限定的に収集するなど、使い方を工夫することをおすすめします。
- 効率的に質の高い情報を集めるコツはありますか。
- 情報を冷静に判断する訓練として、まずは「文字情報」を中心に接することをおすすめします。映像や音声は無意識に影響を与えやすいため、新聞、雑誌、Web記事など、自分のペースで批判的に読める媒体から始めるのが良いでしょう。
- 情報収集で気をつけるべきことは何ですか。
- あらゆる情報に対して、その場で性急に自分の意見を持つ必要はないということです。特に、ご自身の事業に直接関係のない事柄にまで意見を発信することは、将来的なリスクになる可能性もあります。情報をストックしておき、必要な時に取り出すという考え方が大切です。
- 自分の考えが偏らないか心配です。どうすれば防げますか。
- 自分一人で情報を処理し続けると、考えが偏るリスクがあります。最も効果的なのは、信頼できる他者と対話(ディスカッション)することです。異なる視点に触れることで、自身の価値基準を客観的に見直し、思考の偏りを修正する機会になります。
配信内容の詳細
はじめに:どのニュースメディアを信頼していますか
ある調査によると、情報の信頼度はテレビが最も高く、次いで新聞という結果が出ています。一方でSNSも雑誌などと変わらない水準にあるようです。
しかし、どのメディアが信頼できるか、という議論自体にあまり意味はないかもしれません。今回は、Webマーケティングの専門家として、情報の捉え方についてお話しします。
情報収集の現実:特別な情報源は存在しない
私自身、特別な情報源を持っているわけではありません。ニュースサイトや中小企業向けの雑誌、一部のポッドキャストやSNSなど、皆さんがアクセスできる情報と大差ないものです。
データに基づいたツールを使うことはありますが、出来事や論評に関する情報源はごく普通です。大切なのは、どこから得るかではなく、どう捉えるかだと考えています。
情報収集の目的
中小企業向けの雑誌を読む目的の一つは、お客様が今何に関心を持っているかを知ることです。これは、自分のためだけでなく、顧客を別の角度から理解するための情報収集と言えます。
メディアごとの信頼度を問うことの無意味さ
私は、メディアごとに信頼できる、できないと区別することに意味はないと考えています。その理由は、情報処理の方法にあります。
情報の「一時保管」という考え方
私は、PRやポジショントーク、憶測記事などを除き、ほとんどの情報を一旦「そうなんだ箱」に入れます。その場で情報の価値を判断することはしません。
なぜなら、普通に仕事をしている中で、今この瞬間の意思決定に影響する情報は、それほど多くないからです。後で必要になった時に、その箱から取り出して再評価すれば十分だと考えています。
思考を鍛えるためのメディア選び
情報を自分なりに検証する習慣をつけたい場合、どのメディアから始めるのが良いでしょうか。私は「文字情報」から始めることを推奨します。
なぜ動画より文字情報が推奨されるのか
動画やテレビは、映像と音声によって無意識に働きかけ、視聴者を特定の印象に誘導しやすいメディアです。人を動かすのに向いている分、フラットに物事を考える訓練には注意が必要です。
YouTubeは、興味を持った分野の動画が次々と表示され、思考が偏りやすい環境を生み出します。その点、文字情報は自分のペースで読み、批判的に考える余裕を与えてくれます。
SNSとの付き合い方で注意すべき点
SNSは、多くの人が「良い」と言うものが良く見えるなど、心理的な影響を強く受けやすい場です。人に影響されやすいと感じる方は、情報の摂取を避けるか、使い方を工夫した方が良いかもしれません。
例えば、以下のような使い方が考えられます。
- 信頼できる専門家のアカウントのみをフォローする
- 不特定多数の意見が表示される「おすすめ欄」などは時々参考にする程度に留める
- 「いいね」の数などで情報の価値を判断しない
Yahoo!ニュースなどで、記事を読むより先にコメント欄を見てしまう方は、他人の意見に影響されすぎている可能性があり、注意が必要です。
まとめ:情報との健全な向き合い方
今回の内容をまとめます。
- 媒体ごとに信頼度をランク付けするのは、あまり意味がありません。情報はまず受け止め、判断が必要な時に再評価しましょう。
- 情報を批判的に捉える訓練は、自分のペースで考えられる文字情報から始めるのがおすすめです。
- 自分の考えが偏らないよう、信頼できる他者との対話を通じて、常に価値基準を見直すことが重要です。
情報過多時代の本質
現代は、情報そのものよりも、それに対する「解釈」が爆発的に増えている時代です。他人の解釈に振り回されるのではなく、自分自身の解釈を見つけ、それを元に検証していくことが、何よりも大切なのではないでしょうか。
続きはPodcastをご覧下さい。
#情報収集 #メディアリテラシー #中小企業 #ウェブマーケティング #インフォデトックス
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ)
https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892 - YoutubePodcast(旧:GooglePodcast)
https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN - Spotify
https://open.spotify.com/show/0yBHyUelJHFtby5uD06UxU?si=fL7RT_T9RPivEu7cAjhqFA - Amazon Music
https://amzn.to/3uV8vT7
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。
https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/