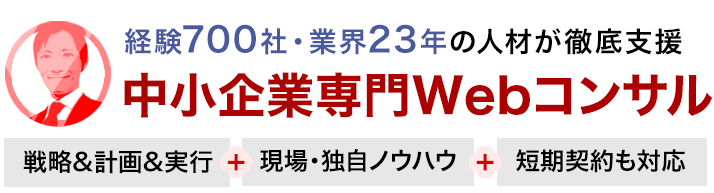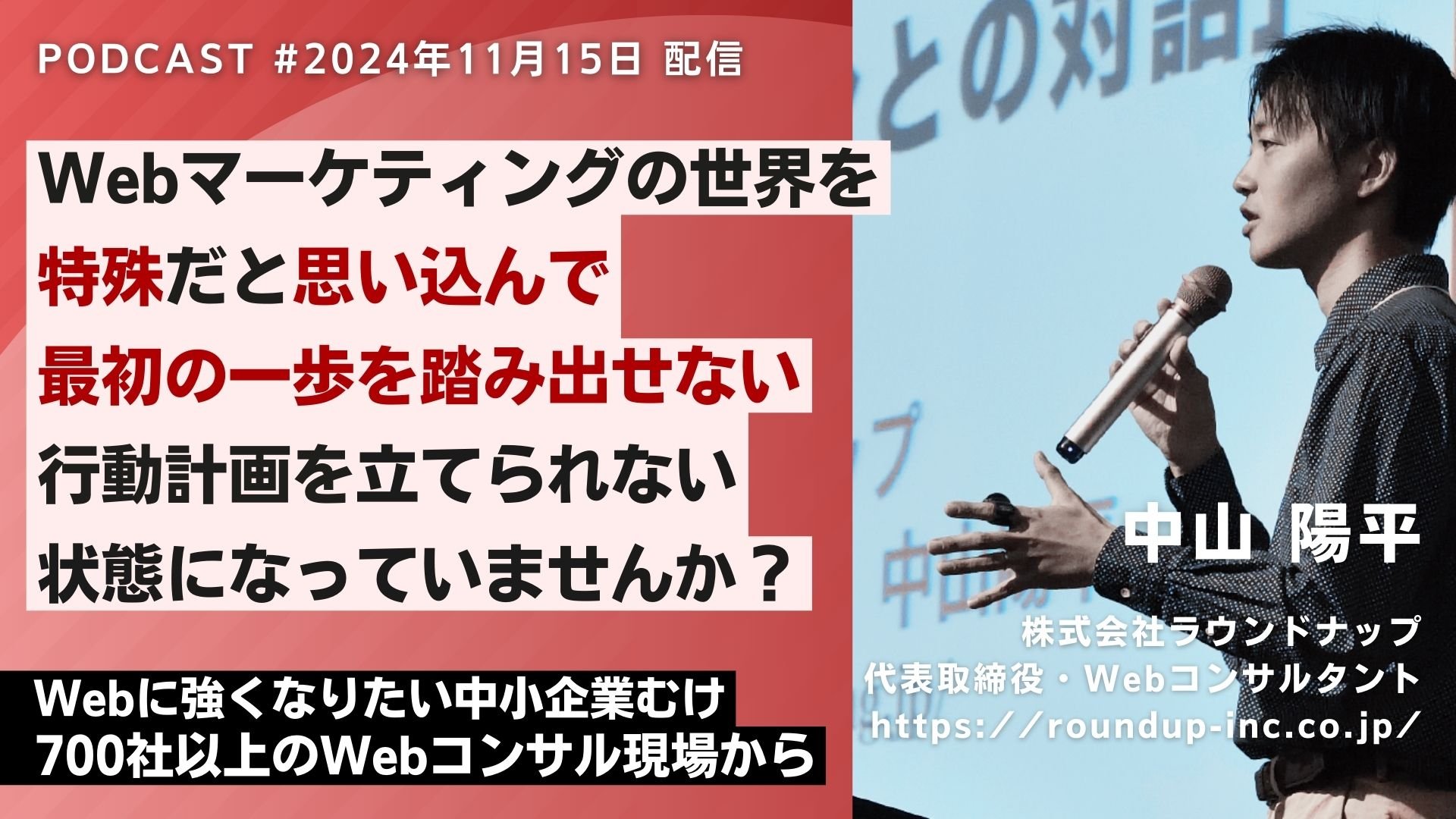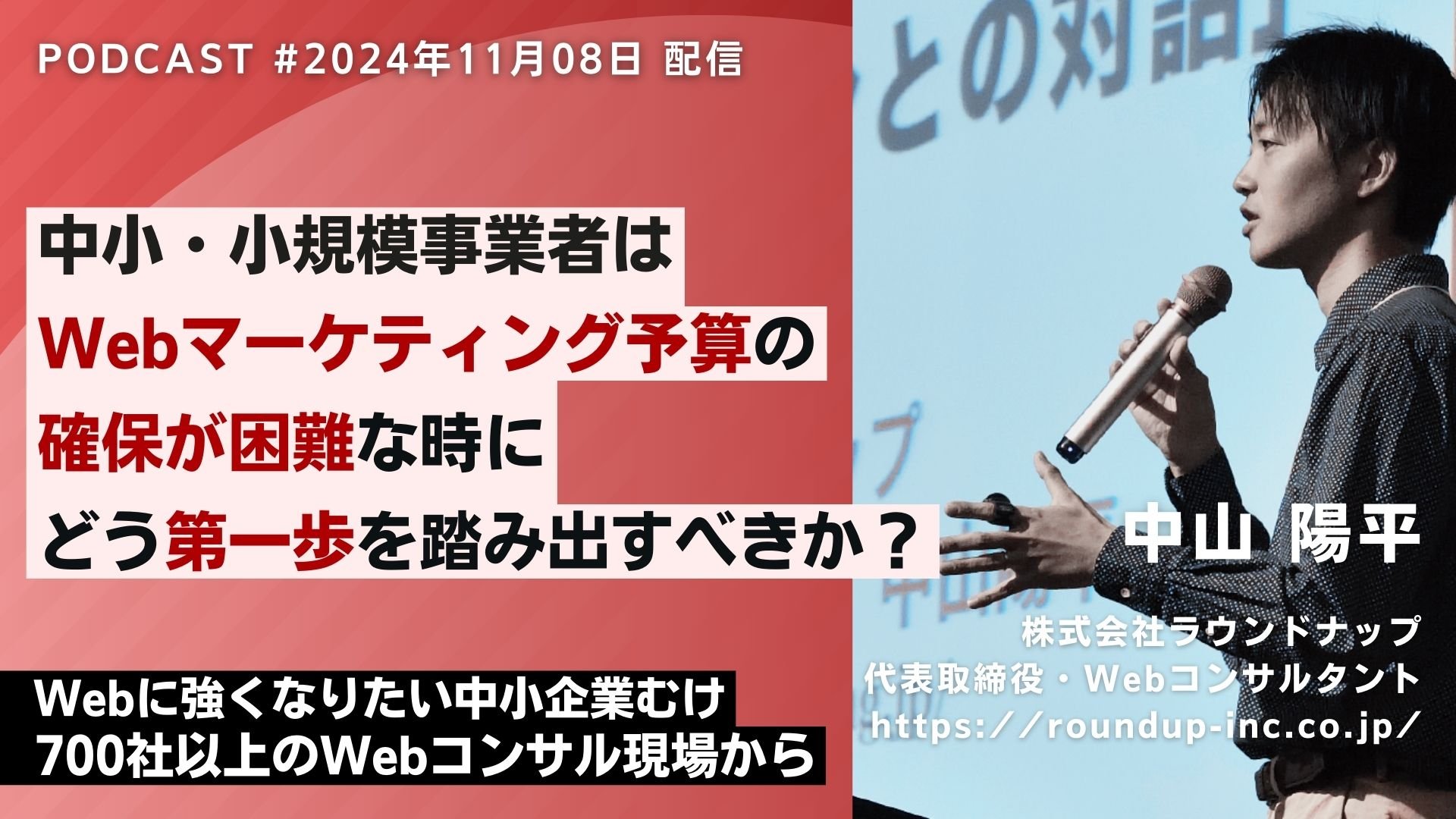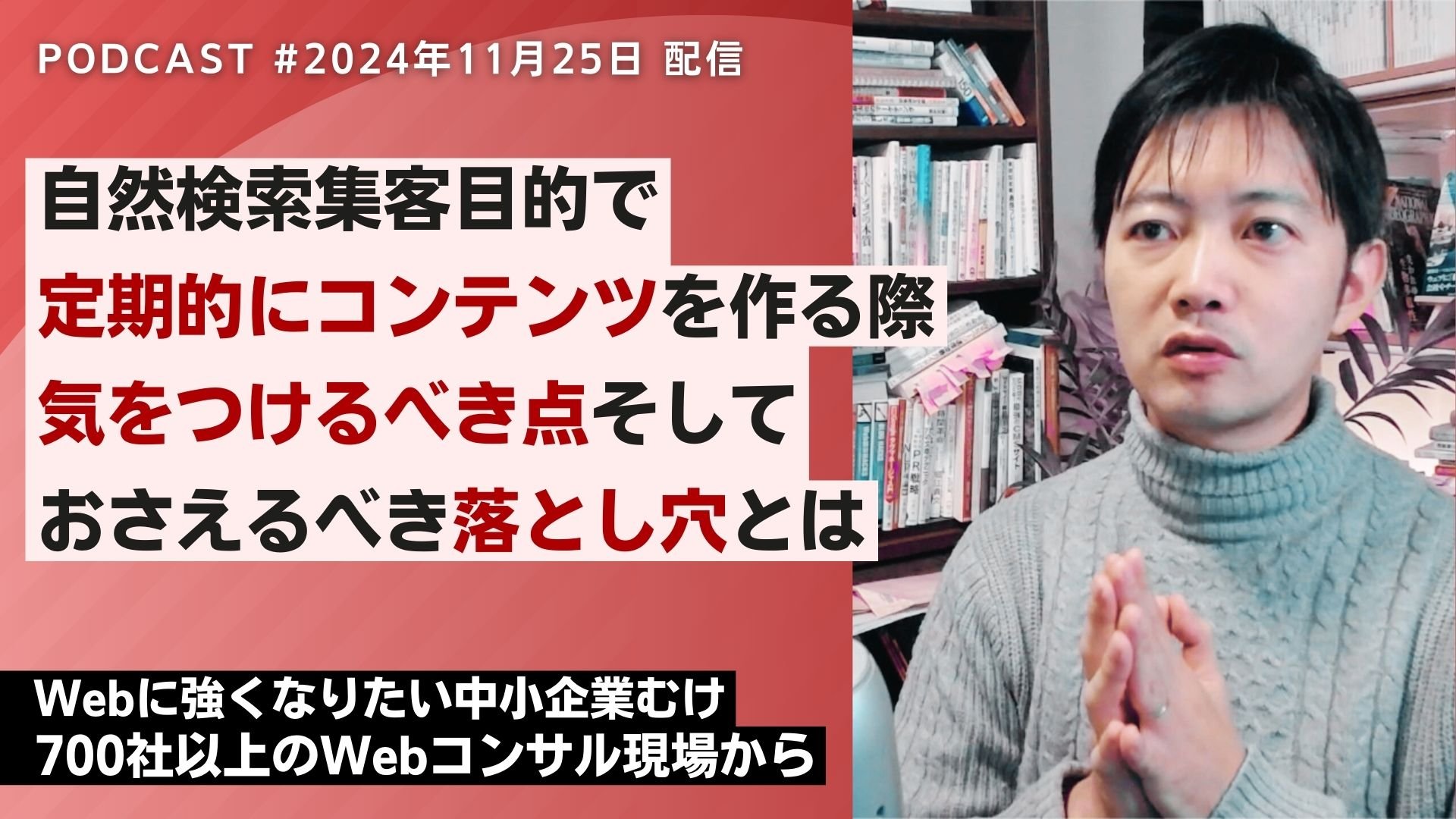Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
内容について
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
このページでは、「Webマーケティングの世界を特殊だと思い込んでいることが、足踏みの大きな原因になっている」というテーマでお話ししたPodcastの内容を、読みやすい形に整理してお届けします。
前回は「予算」や「リソース」の話、特にマーケティング予算の確保の考え方についてお話ししました。今回はそこから一歩進んで、「そもそも戦略や計画をどう立てたら良いのか」という相談にお答えしていきます。
まとめ
まとめると、今日お伝えしたかったポイントは次の通りです。
- 「戦略や計画が立てられない」には、「Whatは分かるがHowが分からない」タイプと、「WhatもHowも分からない」タイプの二つがある
- リアルのマーケティングやセールスの経験は、そのままWebにも活かせる。「特殊な世界だ」と思い込んで捨ててしまうのはもったいない
- WhatもHowも分からない状態で両方を同時に進めると、ほぼ確実にパンクする。その結果、アリバイ作りの仕事が増え、本質的な成果が出にくくなる
- うまくいく会社は、最初から複数の人が関わり、「会社としての取り組み」としてWebを位置づけている
- Webサイトは「もう一つの店舗」のような存在であり、会社全体のタスクとしてノウハウを蓄積していくことが重要
もし、今の状況がうまく回っていないように感じたら、
- 自分は「Whatは分かるがHowが分からない」のか
- それとも「WhatもHowも分からない」のか
を一度整理してみるところから始めてみてください。その上で、
- 社内の誰を巻き込めそうか
- どこまでを自分たちで学び、どこを外部パートナーに頼るのが良さそうか
といったことを、少しずつ考えていくと、今までよりも進みやすくなるはずです。
なぜ「戦略や計画が立てられない」と感じてしまうのか
日々、相談や企業研修の場でよくいただく声として、次のようなものがあります。
- 自社の強みや市場でのポジションがうまく言語化できない
- お客さまのニーズが分からない、見えてこない
- 長期的な計画を立てられず、短期的な施策ばかりになってしまう
- そもそも「戦略」や「計画」というものをどう作ればいいのか分からない
ここで押さえておきたいのは、「計画が立てられない」と感じている人には大きく二つのタイプがある、ということです。
- 何をやるべきか(What)は分かるが、どうやればいいか(How)が分からない人
- 何をやるべきか(What)も、どうやればいいか(How)も分からない人
自分がどちらのタイプに近いのかを一度整理してみると、この先何から手を付けるべきかがかなり変わってきます。
戦略・計画を考えるときの3つの層(Why / What / How)
まず、戦略や計画の話は、ざっくりと次の3つの層に分けて考えると整理しやすくなります。
- Why(なぜやるのか)
- 事業の目的や存在意義。なぜそのビジネスを続けるのかという根っこの部分。
- What(何をするのか)
- どの市場を狙い、どの顧客に、どんな価値を届けるのか。戦略や計画の大きな方向性。
- How(どうやるのか)
- 具体的な手段やチャネル、施策の組み合わせ。いわゆるマーケティングミックスなどの世界。
ゴールデンサークル理論と呼ばれる考え方と近いものですが、ここでは難しい理論としてではなく、「話を整理するための3階建ての構造」として捉えていただければ十分です。
ご興味がある方はこちらのTED動画がオススメです。
さて、多くの企業では、Web担当やマーケティング担当がゼロからWhyを考えるというより、「会社としての方針」がある程度決まっている場合が多いと思います。その意味では、現場の担当者が実際に手を動かして悩むのは主に次の二つです。
- 自社として「何をするべきか」(What)
- それをWebで「どう実行するか」(How)
この二つのうち、どちらでつまずいているかによって、取るべきアクションはかなり変わります。
タイプ1:「Whatは分かるがHowが分からない」ケース
まず一つ目のタイプです。これは、リアルの世界では何度も計画や戦略を作ってきた経験がある方に多いパターンです。
- 営業戦略や販売計画を立てた経験はある
- どんなステップを踏めば成果につながるかは、何となくイメージできている
- ただ、「Webになるとやり方が分からなくなる」ので止まってしまう
こういう場合、実は「戦略が立てられない」のではなく、「WebのHowが分からないだけ」ということがほとんどです。
リアルの経験を「無効化」しないこと
ここでとてももったいないのは、
「Webはまったく別世界だから、今までの経験は役に立たない」
と自分で自分の経験を否定してしまうことです。
Webマーケティングの世界は、営業やマーケティングの歴史と比べれば、まだせいぜい数十年程度の歴史しかありません。リアルの営業や販促に比べれば、経験者が少ないという意味では「若い分野」ではありますが、根本の考え方は大きく変わりません。
実際、私がご一緒してうまくいっている企業の多くは、次のような流れで成果を出しています。
- まずリアルの営業や販促でうまくいっている「考え方」や「段取り」をしっかり洗い出す
- それをWeb向けに「翻訳」するつもりで、手段だけを置き換えていく
- 足りないHowは、勉強や外部パートナーで補う
つまり、「今までの経験を土台にして、その上にWebのHowを乗せていく」という発想に切り替えるだけで、かなりスムーズに計画を立てられるケースが多いのです。
Howは「自分で学ぶ」か「パートナーを得る」か
では、足りないHowはどう補えばよいでしょうか。大きく分けると選択肢は二つです。
- 自社内で担当者が学び、試しながら身につけていく
- コンサルティング会社や制作会社、広告会社など、外部パートナーに一部を任せる
どちらが正解という話ではありません。大事なのは、
- リアルの経験やノウハウは「そのまま財産」として活かす
- Web特有の手段やツールの部分だけを補うつもりで動く
という姿勢です。
自社サイトから自分で反響を取っている中小企業の経営者の方々を思い浮かべると、多くの方がまさにこのパターンです。リアルでのマーケティング・セールスの経験を土台にしながら、Webならではの手段を少しずつ広げていくことで、「Webも自分たちの得意領域」に変えていっています。
タイプ2:「WhatもHowも分からない」ケース
次に、より苦しいのがこちらのケースです。
- 何をしたらよいか(What)も分からない
- どうやって進めたらよいか(How)も分からない
実は、このタイプの方のほうが現場では多いと感じます。典型的なパターンは、次のようなものです。
「パソコンに詳しそうだから」で任される現場
社内でこんなことが起きていないでしょうか。
- なんとなくパソコンに強そう、ネットに詳しそうという理由でWeb担当に任命される
- 実際には、社内の人間関係や部署間の力学、営業の現場などの情報はあまり持っていない
- にもかかわらず、「新しいホームページを何とかして」「Web集客をなんとかして」と丸ごと任される
本来、会社全体の方針を踏まえた戦略や計画(What)を考えるのは、ある程度の経験と権限を持った層の仕事です。いきなり任命された担当者に、
- 戦略や計画を考える(What)
- 具体的なWebの施策を組み立てる(How)
この両方をいっぺんに要求するのは、かなり無理のある状態です。
WhatとHowを同時にやろうとしてパンクする
タイプ2で一番避けたいのは、「WhatもHowも分からない状態で、両方を同時に片付けようとする」ことです。
実際、次のような相談をよくいただきます。
- 社内での立場的に、他部署を動かすのが難しい
- でも、Webで成果を出さなければならないとプレッシャーはかかる
- 手段も分からないまま、とりあえずセミナーに出たり、ツールを導入したりしてみる
この状態が続くと、ほぼ間違いなくどこかでパンクします。さらに厄介なのは、責任が重い分だけ「自分を守るための動き」が増えてしまうことです。
「アリバイ作りの仕事」が増えてしまうメカニズム
よく現場で見かけるのが、いわゆる「アリバイ作りの仕事」が増えてしまうパターンです。
- 上からは「ちゃんとやっているのか」と問われる
- 成果が出ているかどうかより、「動いている形」が求められる
- その結果、「分かりやすい報告のための施策」が増えていく
例えば、
- とにかく毎月のアクセスレポートを作ることが仕事の中心になる
- 小さなキャンペーンを頻繁に立ち上げて、「取り組み実績」として並べる
- 社内向けの見栄えを優先した施策が増える
しかし、こうした「アリバイ作り」の仕事は、外向けの成果にはあまりつながりません。しかも、やっている本人も「これは本当に意味があるのか」と薄々感じているので、心身ともに消耗しやすい構造です。
この状態に陥るのは、担当者本人の能力の問題ではなく、そもそもの「任せ方」「体制の作り方」に原因があるケースが多い、と私は感じています。
Webマーケティングは「特殊な世界」ではない
ここで一度、前提を整理したいと思います。
Webマーケティングの世界は、しばしば「リアルとはまったく別の特殊な世界」と語られてきました。その背景には、Web業界側の営業トークもあったと思います。
ただ、現場で数多くの企業を見てきた立場から言うと、基本的な考え方はリアルのマーケティングやセールスとほとんど変わりません。
- ターゲットとなるお客さまは同じ人間
- 検討のプロセスも、大枠ではリアルと共通している
- 違うのは「使う道具」「接点となる場」がWebかリアルか、という点だけ
特に現在は、多くの人が当たり前のようにオンラインとオフラインを行き来しながら購買行動をしています。ある時期までは「Web上での購買行動が特殊だった時代」もありましたが、今はその境目がかなり薄くなっています。
だからこそ、リアルの世界で積み上げてきた経験やノウハウを、
- 「Webには通用しない」と捨ててしまうのではなく
- 「どうWebに翻訳するか」を考える材料として、きちんと活かす
という発想が、とても重要になります。
うまくいく会社・うまくいかない会社の違い(現場で見てきたパターン)
コンサルティングの現場で、私は多くの企業のWeb活用に関わってきました。その中で、正直にお伝えすると、「うまくいくパターン」と「なかなかうまくいかないパターン」があると感じています。
うまくいかないパターンの典型
うまくいかないケースで共通しているのは、次のような状況です。
- 会社の中でWebの優先度が低い
- リソース(人・予算・時間)がほとんど割かれていない
- それでも「目に見える結果」だけは求められる
- しかも、WhatもHowもよく分からない担当者に丸投げされている
この状態だと、
- 担当者はアリバイ作りの仕事で疲弊する
- 一定期間やっても成果が見えず、「予算を使ったのに結果が出ない」で打ち切られる
- ノウハウや経験も社内に残らない
という、非常にもったいない終わり方をしてしまいがちです。
うまくいく会社に共通していること
一方で、うまくいっている企業には、次のような共通点があります。
- 最初の段階から、複数の人が関わっている
- 経営や現場のキーマンが、「自分たちはこう考えている」と真剣に意見を持っている
- その上で、「Webの世界ではどう進めるべきか」を一緒に考えようとしている
つまり、
- What(何をするか)を考えられる人が、ちゃんとプロジェクトに入っている
- 担当者一人に背負わせず、「会社として取り組むもの」として扱っている
という構図です。
コンサル側としても、このような体制が整っていると、提案やサポートがしやすくなりますし、結果として成果につながりやすくなります。
では、具体的にどう進めればよいのか
ここまでの話を踏まえて、「じゃあ現場では何をしたらいいのか」というところを、少し整理します。
1. Whatを考えられる人を巻き込む
まず一つ目は、「Whatを考えられる人」を必ず巻き込むということです。
ここで言う「Whatを考えられる人」とは、例えば次のような方です。
- 事業全体の方向性をある程度把握している人
- 営業やサービス提供の現場をよく知っている人
- 部署間の調整や根回しができる立場の人
新しくアサインされたWeb担当者が、いきなり他部署にお願いに行っても、なかなか話が進まないことが多いと思います。だからこそ、
- 上位職の方に、後ろ盾として入ってもらう
- 部署間調整や社内合意の部分をサポートしてもらう
こうした体制づくりがとても重要です。
2. Howを学ぶ期間とWhatを考える期間を分ける
二つ目は、「Howを学ぶ期間」と「Whatを考える期間」を意識的に分けることです。
現場としては、「すぐに成果を出したい」という気持ちが強くなりやすいのですが、
- Whatも分からない
- Howも分からない
この状態で、両方を同時に解こうとすると、ほぼ確実に無理が出ます。
そこで、あえて次のように段階を分けてしまうのも一つの方法です。
- まずはHow(Webの手段やツール)を、浅く広くで良いので把握する期間を取る
- その後に、会社としての強みやポジション、市場や顧客のニーズと向き合う期間を設ける
Howは、座学や独学、あるいは小さなサイトや一部ページでの試行などを通じて、比較的短期間で「全体像の地図」を頭の中に描けるようになります。
例えば、
- 広告、コンテンツ、メール、SNS、検索エンジン対策など、どんな手段があるのか
- それぞれの手段にはどんな特徴と注意点があるのか
- 今後伸びそうな領域はどこなのか
といった「俯瞰的な把握」ができるだけでも、後からWhatを考えるときに、
- 「この目標なら、この手段が合いそうだ」
- 「ここを伸ばしたいなら、まずこのチャネルを強化しよう」
という連想がしやすくなります。
もちろん理想を言えば、「OJT的に、小さく試しながら学ぶ」のが一番ですが、現実的にはそうした環境が整わない会社も多いはずです。その場合でも、まずはHowの全体像を押さえる期間を意識的に作るだけで、後の動きやすさはかなり変わります。
3. 市場分析や自社分析に「近道はあまりない」と受け止める
一方で、What(何をすべきか)を考える部分には、あまり近道がありません。
自社の強みやポジショニングを明確にするには、
- 市場や競合の状況をきちんと見て
- 自社の過去の成功・失敗を振り返り
- お客さまの声を集めて、解釈する
という、どうしても時間のかかるプロセスが必要です。
Webを絡めたからといって、それが劇的に楽になるわけでもありませんし、むしろ情報量が増える分だけ、整理が大変になるケースもあります。
だからこそ、
- この部分には一定の時間と人をかける前提で考える
- 「とりあえず外に丸投げすれば何とかなる」とは考えない
という意識が大事です。
この前提を持たないまま、表面的な施策だけを繰り返してしまうと、結果としてアリバイ作りの仕事が残り、実際には何も進んでいない、という状態に陥りやすくなります。
Webサイトを「もう一つの店舗」として扱う
少し昔の表現ですが、今でもしっくりくる考え方があります。
Webサイトは「インターネット上のもう一つの店舗」「もう一つの拠点」である
リアルに新しい店舗や拠点を出すとき、
- 出店場所やターゲットをどうするか
- どんな商品構成でいくか
- どのくらいの投資をするか
といったことを、かなり慎重に検討すると思います。
一方でWebになると、「レンタルサーバー代は安いし、とりあえず作ってみよう」と軽く見られてしまうことが少なくありません。しかし、実際には、
- Webサイトは多くのデジタル施策の「ハブ」になる存在である
- 広告やSNS、メールなど、あらゆるWebの入り口が最終的に集まる場所である
という意味で、非常に重要なチャネルです。
だからこそ、Webサイトの運用は、
- 会社全体のタスクとして位置づける
- ノウハウや知見が社内に蓄積されるように取り組む
という視点を持ってもらえると、結果として成果につながりやすくなります。
コンサルティング現場で感じていることと、こちらのジレンマ
少し本音に近い話も共有しておきます。
「なんとか頑張りたいけれど、社内の体制も知識も整っていない」という相談を受けることが、実際にはとても多いです。そういうとき、こちらとしてはできる限りサポートしたいのですが、現実問題として、
- コンサルティングとして一定の費用をいただく以上、無制限に関わることはできない
- こちらがいくら動いても、会社側の体制が動かないと成果につながらないケースがある
というジレンマが常にあります。
多くの「うまくいかなかった事例」を振り返ると、
- 会社としてWebに対する優先度が低い
- 担当者が孤立していて、社内で動かせる範囲が極端に狭い
- それでも短期的な成果だけは求められる
という構図に行き着くことが多いと、経験上感じています。
だからこそ、私自身も、
- 社内で説明しやすくなるためのツールやテンプレート
- 提案書の書き方や、稟議を通しやすくするための工夫
といった部分を、もっと支援できるようにしたいと常に考えています。その一方で、最終的に一番効くのは、やはり「会社側の考え方が変わること」だとも感じています。
もし、「現場がなかなか動いていない」「担当者が孤立しているように見える」という感覚が少しでもあるなら、一度立ち止まって、
- どうすれば、その人たちを会社として支えられるか
- どうすれば、Webを「一人の担当者の仕事」ではなく「会社全体の取り組み」として扱えるか
という視点で考えてみてもらえると、状況が変わるきっかけになるかもしれません。
Webの世界とリアルの世界を分けすぎない
最後にもう一度だけ、前提の話に戻ります。
きちんと振り返ってみると、
- 今や誰もが当たり前のように、オンラインとオフラインを行き来している
- 情報収集はWebで、実際の購買はリアル店舗で、という行動も普通になっている
- 逆に、リアルで見たものをWebで詳しく調べてから購入する、というケースも多い
つまり、人の行動としては、すでにWebとリアルを切り分けてはいません。
それなのに、企業側だけが「Webは特殊だから、若い人に任せておけば何とかなる」と考えてしまうと、
- 本来は経営戦略や販売戦略として議論すべき内容が、担当者一人の肩に乗ってしまう
- 結果として、戦略や計画が「立てられない」「進まない」という状態になる
というギャップが生まれます。
本来、経営戦略や販売戦略は、
- 関係する部署やメンバーが集まって議論する
- 何度もすり合わせを行って形を整えていく
という、時間のかかるプロセスを経て作られるものです。Webだからといって、そのプロセスをすべてショートカットしてしまうのは、やはり無理があります。
おわりに:考え方を少しだけ変えてみる
ここまでお読みいただいて、「結局、近道はあまりないんだな」と感じた方もいるかもしれません。ただ、これはネガティブな話ではなく、「ちゃんと取り組めば、きちんと前に進む」という意味でもあります。
まとめると、今日お伝えしたかったポイントは次の通りです。
- 「戦略や計画が立てられない」には、「Whatは分かるがHowが分からない」タイプと、「WhatもHowも分からない」タイプの二つがある
- リアルのマーケティングやセールスの経験は、そのままWebにも活かせる。「特殊な世界だ」と思い込んで捨ててしまうのはもったいない
- WhatもHowも分からない状態で両方を同時に進めると、ほぼ確実にパンクする。その結果、アリバイ作りの仕事が増え、本質的な成果が出にくくなる
- うまくいく会社は、最初から複数の人が関わり、「会社としての取り組み」としてWebを位置づけている
- Webサイトは「もう一つの店舗」のような存在であり、会社全体のタスクとしてノウハウを蓄積していくことが重要
もし、今の状況がうまく回っていないように感じたら、
- 自分は「Whatは分かるがHowが分からない」のか
- それとも「WhatもHowも分からない」のか
を一度整理してみるところから始めてみてください。その上で、
- 社内の誰を巻き込めそうか
- どこまでを自分たちで学び、どこを外部パートナーに頼るのが良さそうか
といったことを、少しずつ考えていくと、今までよりも進みやすくなるはずです。
今後のコンテンツや相談の場について
このPodcastは、基本的にノーカットで収録しています。その分、同じ話を何度か繰り返してしまっているところもあったかもしれませんが、その「生っぽさ」も含めて、現場で感じていることをそのままお届けしたいと思っています。
最近は、今回のようにPodcastの内容をテキストコンテンツとして整理して、ブログでも読めるようにする取り組みも少しずつ始めています。X(旧Twitter)などでも更新情報を出すことがありますので、あわせてチェックしてもらえると嬉しいです。
また、企業研修や社内勉強会の形で、
- 社内メンバーと一緒にWebのHowを整理する場
- 経営層も含めて、Webの位置づけを見直すワークショップ
などを行うことも増えてきました。オンラインでの実施や、複数社合同でコストを抑えながら行う形も可能です。
具体的な状況や課題感は会社ごとに違いますので、
- 「今の進め方で良いのか少し不安になってきた」
- 「社内の体制をどう整えればよいか整理したい」
といったモヤモヤがあれば、ひとつの選択肢として、ラウンドナップWebコンサルティングへのご相談も検討してみてください。
関連リンク
本文の内容と関連が深く、公式情報として参考になるページをいくつか挙げておきます。
- デジタル・IT化支援(中小企業庁)
- デジタル化をしたい(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
- IT導入補助金2025 公式サイト
- Google 検索セントラル(SEO関連ドキュメント一覧)
- Google アナリティクス4(GA4)でより有用なデータを取得するためのチェックリスト
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/