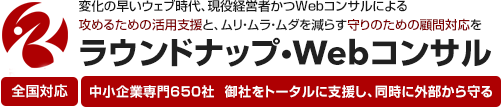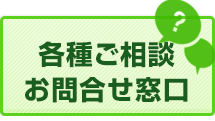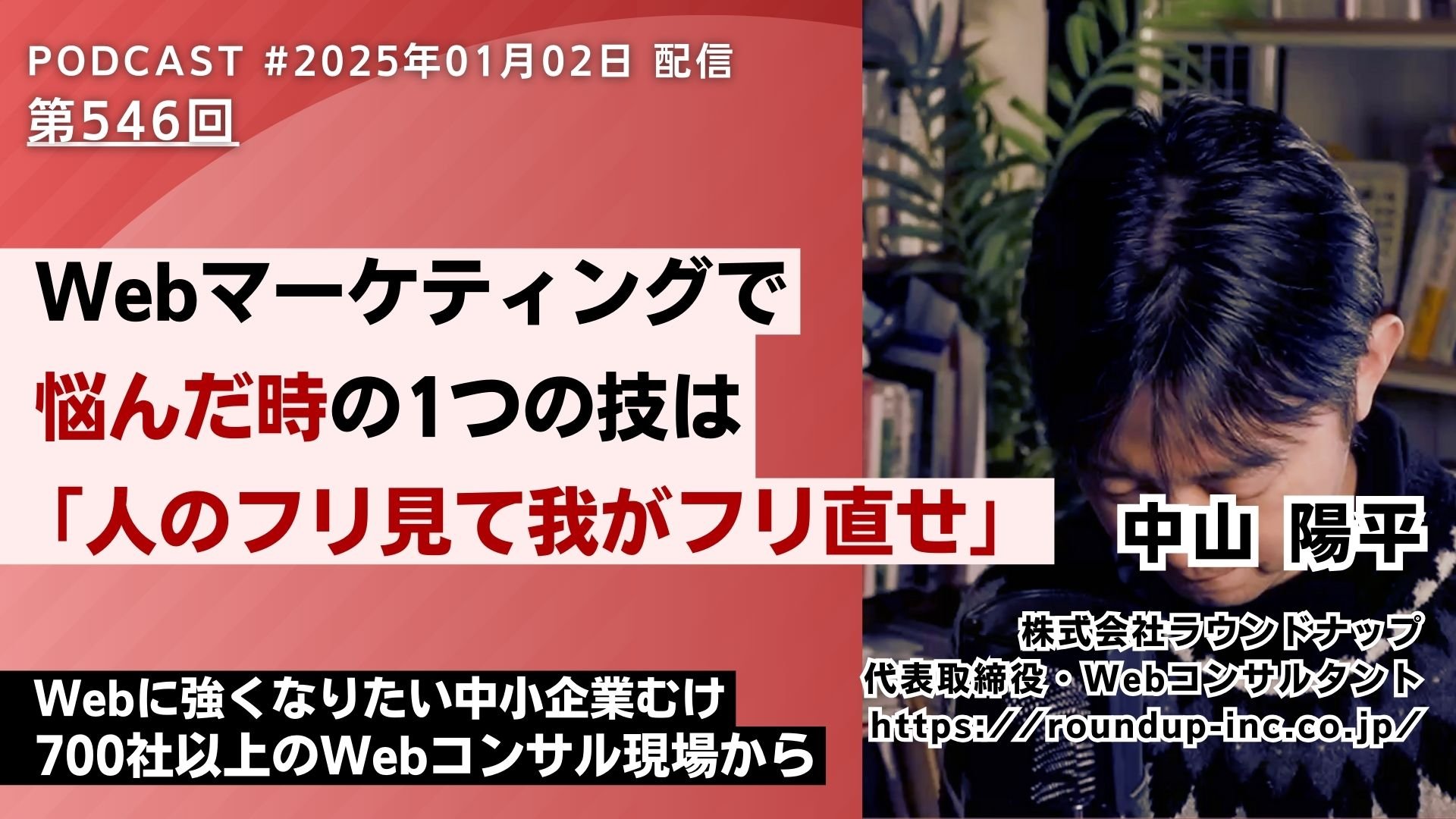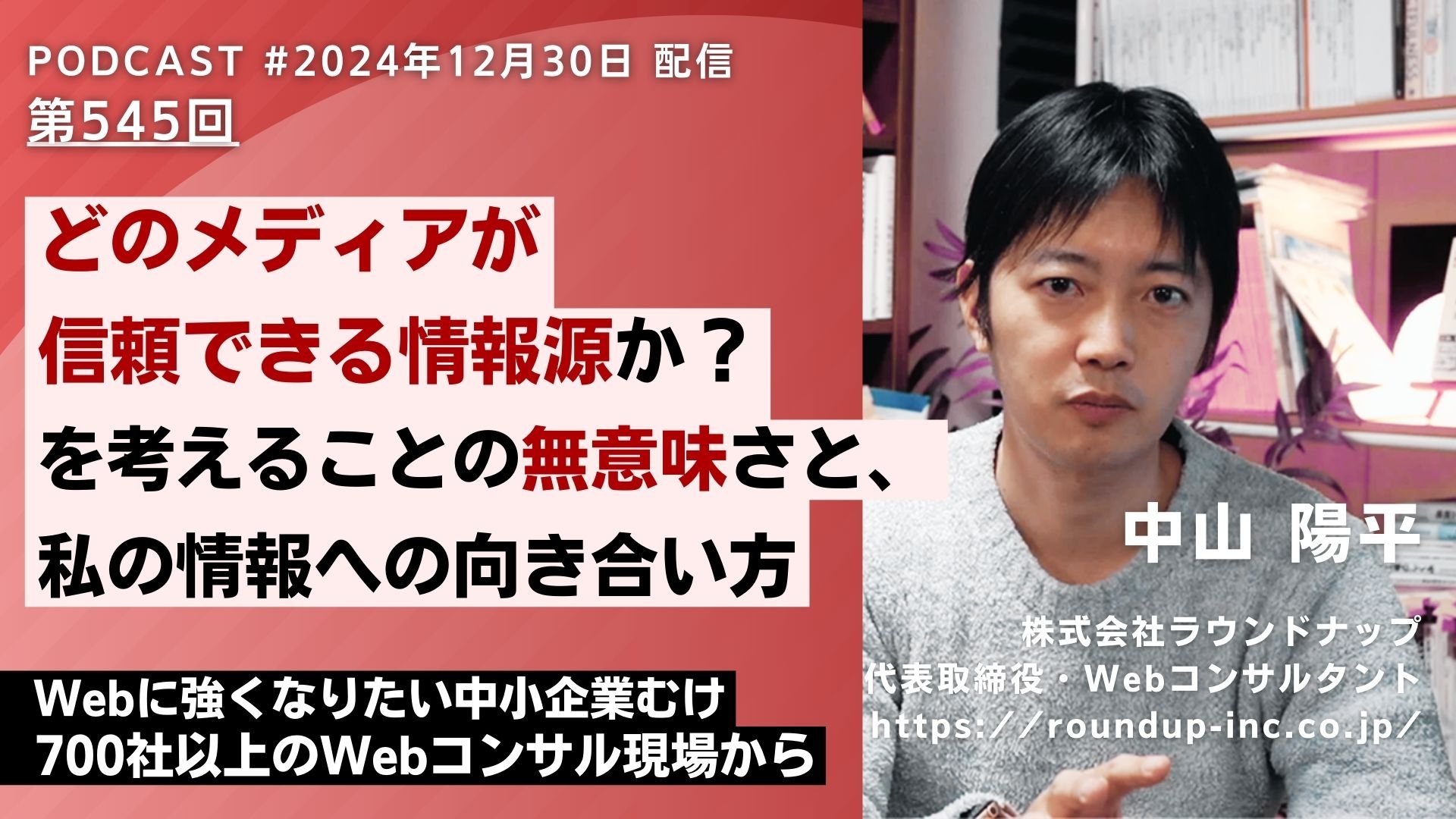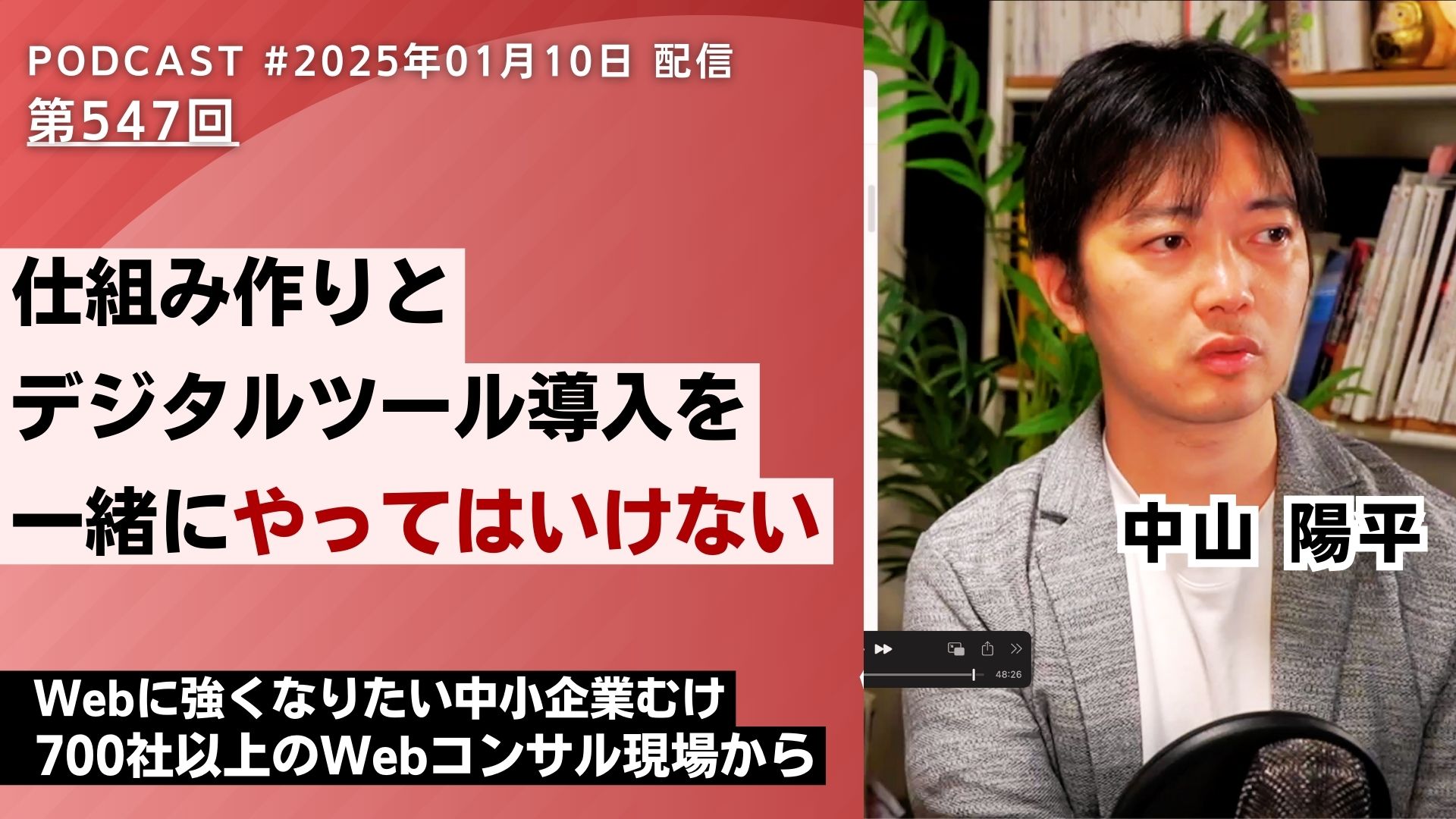Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
Webマーケで悩んだ時の1つの技
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
年末になり、多くのメディアで2024年を振り返る記事が公開されています。そういった記事を眺めながら、今回はWebマーケティングにおける「CX(カスタマーエクスペリエンス)」について、特に中小企業の皆さんがどのように取り組むべきか、というテーマでお話しします。今回のテーマは、Webマーケティングで悩んだ時のための一つの技、「人のフリ見て我がフリ直せ」です。
大企業のCX事例は、本当に参考になるのか
先日、ITmediaさんの振り返り記事を読んでいました。ITmediaさんでは2024年の夏頃から「CXエキスパート」という連載を始められたようで、その人気記事ランキングが公開されていました。私自身も、同社の「オルタナティブ・ブログ」というコーナーに籍を置かせてもらっているため、よく拝見しています。
しかし、その人気記事のランキングを見て感じたのは、中小企業や小規模事業者の方々が自社のビジネスに直接活かすのは難しいかもしれない、ということです。例えば、ランキング1位は入場料2,530円の蔦屋書店さんの話でした。他にもSuicaの記事など、取り上げられている事例はコールセンターや大規模な来客施設といった、大きな資本を持つ企業が対象のものがほとんどです。これらはITmediaエンタープライズという媒体の一部なので、ターゲット層を考えれば当然のことではあります。
では、私たち中小企業は、顧客理解、つまりCXを考える上で、何から手をつければ良いのでしょうか。そのための、誰でもすぐに踏み出せる第一歩をご紹介します。
「脳内お客様」が施策を阻害する
それが、今回のタイトルでもある「人のフリ見て我がフリ直せ」です。
自分自身のこと、あるいは自社のサービスについては、案外わからないものです。なぜなら、良くも悪くも自分たちのサービスを熟知しているからです。そして、「うちのお客さんはこういう人たちのはずだ」「こういう悩みを抱えているに違いない」といった、顧客に対する固定観念がいつの間にか積み上がっていることが少なくありません。
経営者の方に「お客様はどんな人ですか」と尋ねると、すぐに答えが返ってくることがあります。しかし、その顧客像が更新されないまま、「脳内お客様」に向けて施策を打ち続けても、なぜか効果が出ない、という事態に陥りがちです。そして、「何かが悪かったのかな、手段が悪かったのかな」と考え、SEO(Search Engine Optimization)や広告、SNSといった各手法の専門家に依頼するという流れになりがちです。
しかし、問題は手段の前にあります。そもそも、ターゲット顧客に情報をどのような順番で伝えるべきか、最初にどの心理的なハードルを解消してあげなければメッセージが響かないのか。そういった根本的な部分が見直されないまま、手段の議論に走ってしまうのです。特に、過去の成功体験があると、そのやり方が今も正しいはずだと思い込んでしまい、見直しはさらに難しくなります。時代は変わり、顧客の価値観も、あるいは顧客層そのものも変化している可能性があるにもかかわらずです。
改善のヒントは「買い手としての自分」の中にある
そこで実践していただきたいのが、「人のフリ見て我がフリ直せ」です。皆さんは売り手であると同時に、一人の消費者として、あるいは一企業として、日常的に何かを買う「買い手」でもあります。お金が世の中を巡っている以上、売り手と同じだけ買い手が存在するはずです。その「買い手としての体験」に、改善のヒントが隠されています。
自分たちのサービスの課題は、見えにくい、あるいは無意識に見て見ぬフリをしてしまいがちです。しかし、他社のサービスであれば、良くも悪くも「ここは良かったけれど、ここはちょっと…」といった点が客観的に見え、指摘しやすいものです。
他社のサービスから自社の課題を見つける具体的なステップ
まずは、自分自身が買い手として体験したサービスについて、「良かった点」「良くなかった点」「嫌だと感じた点」を書き出してみてください。できれば複数人で行い、意見をまとめていくと良いでしょう。ミーティングが悪口大会にならないよう、進行役(ファシリテーター)を立てることをお勧めします。
次に、なぜその体験が良かったのか、あるいは悪かったのかを考えます。例えば、「昔利用した時は良かったのに、最近はそうでもなかった」と感じたなら、何が変わったのでしょうか。その変化の裏には、人材の問題や、経営方針の転換といった、様々な背景があるかもしれません。確定はできなくても、その背景を類推することが重要です。そのプロセスを通じて、顧客がサービスに何を求めているのか、あるいは求めていないのか、といった提供者側との「ズレ」が明確になってきます。
そして最後に、その気づきを自社のサービスに照らし合わせてみてください。「私たちも、お客様が求めていないことを良かれと思ってやっていないだろうか」「自分たちが決めたサービスの提供順序は、本当にお客様のためになっているだろうか」。他社のサービスを通して得た視点で自社を振り返ることで、メンテナンスすべき点が見えてくるのです。
「他者の鏡」がなくても自己分析できるようになる
この取り組みに慣れてくると、他社という鏡を借りなくても、常に自分たちのサービスに対して良い意味での疑いの目を持ち、「自分がお客さんだったらどう感じるか」という視点に切り替えて物事を考えられるようになります。そうなれば、常に顧客にとって最適な対応は何かを判断し、行動できるようになるでしょう。
中小企業が今すぐできる顧客理解とは
メディアで紹介されるCXの事例は、大規模なシステム導入や多額の予算を前提としたものが大半です。しかし、中小企業や小規模事業者が今取り組むべき顧客理解は、そういったものではなく、もっとアナログなアプローチの方が効果的だと私は考えています。ターゲットが異なる情報を鵜呑みにして、身の丈に合わない予算を組んでしまうことは避けるべきです。日常の中にこそ、改善のヒントは転がっています。
新入社員や他社の経営者という「鏡」
この「買い手としての視点」を活用する方法は他にもあります。例えば、新しく入社した社員は、まだ自社のサービスを何も知らない、いわばゼロベースの状態です。その状態で自社のサービスを体験してもらい、感想を聞く「顧客体験研修」は非常に有効です。もちろん、新入社員が率直な意見を言うのはハードルが高いかもしれませんが、「この書類は、もっと前の段階で欲しかった」「後から知ったこの情報は、最初に知りたかった」といった具体的なフィードバックは、貴重な財産となります。
また、商圏が異なる親しい経営者同士で、お互いのサービスを体験し、フィードバックし合うという方法もあります。やはり、自分では気づけないことの方が多いのです。
データ分析よりも「現場の肌感覚」が重要な理由
Webサイトの行動データから顧客を理解しようとすることも一つの手ですが、中小企業のサイトのアクセス数(月間数千〜1万数千PV程度)では、統計的に有意な判断を下すのは難しいのが実情です。得られたデータも、解像度が高いとは言えません。
それならば、「N=1(サンプル数1)の話だ」と言われるかもしれませんが、一人の顧客とのやり取りから得られる現場の肌感覚の方が、よほど精度が高く、ビジネスにインパクトを与える一撃となる可能性を秘めていると、私自身は感じています。
まとめ:気づきを共有できる組織が、時代を乗り越える
年末年始は、普段とは少し違う購買行動を取る機会も多いかと思います。この機会に、ぜひ買い手としての体験を意識的にストックしてみてください。様々な業界のサービスに触れ、家族など年代の違う人の意見を聞いてみるのも良いでしょう。
そして年始に、それらの気づきを社内で持ち寄り、共有する会を開いてみてはいかがでしょうか。個々のスタッフが「他社のあのサービスを見て、うちのこれが改善できると気づいた」といった発見ができるようになると、会社は大きく変わります。そのような気づきを受け入れ、サービスを常にアップデートしていける企業風土を育てることが、変化の激しい時代に取り残されないための鍵となるのではないでしょうか。
このPodcastが解決できるFAQ
- Q1. CX(カスタマーエクスペリエンス)改善は、専門知識や予算がない中小企業には難しいのではないでしょうか。
- A1. 大規模なシステム導入や専門的な分析は必ずしも必要ありません。まず自分自身が「買い手」として体験したことを基に、自社のサービスを見直すことから始められます。これは予算をかけずに今日からできるCX改善の第一歩です。
- Q2. 自社の顧客について、どうすればもっと深く理解できるのでしょうか。
- A2. 「人のフリ見て我がフリ直せ」という考え方が有効です。自身が様々なサービスを顧客として利用した際の体験(良かった点、悪かった点、感じたこと)を記録し、それを自社サービスに置き換えて考えることで、顧客視点が得られます。
- Q3. Webサイトのアクセスデータを見ても、具体的な改善点がよく分かりません。
- A3. アクセス数が限られる中小企業の場合、統計的に有意なデータを取るのは難しいことがあります。データ分析に固執するより、顧客と接する現場の肌感覚や、新入社員など第三者のフレッシュな意見の方が、有効な改善のヒントになることが多いです。
- Q4. 過去に成功したマーケティング手法が、最近なぜか通用しなくなってきました。
- A4. 時代と共に、顧客の価値観や顧客層そのものが変化している可能性があります。過去の成功体験は貴重な資産ですが、それに固執せず、現在の顧客視点でサービスや情報提供のあり方を見直すことが重要です。
- Q5. サービスの改善点を見つけたいのですが、社内の人間だけだと良いアイデアが出ません。
- A5. 自分たちのことを客観的に見るのは難しいものです。新入社員に顧客としてサービスを体験してもらう、あるいは商圏の違う経営者仲間と互いのサービスを誠実に評価し合うなど、意識的に「第三者の視点」を取り入れることをお勧めします。
続きはPodcastをご覧下さい。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ)
https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892 - YoutubePodcast(旧:GooglePodcast)
https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN - Spotify
https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj - Amazon Music
Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。
https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/