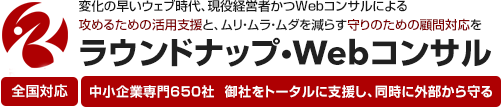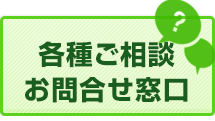更新日:2025年 9月 8日 作成日:2019年 9月 11日
「ウェブ解析はむずかしそう…」と感じていませんか?
ウェブ解析という言葉に対して「いろいろなことを覚えなきゃいけない、難しそう」といったイメージを持ってはいませんか?
その理由の多くは「ウェブ解析=Googleアナリティクス様なアクセス解析ツールのことを想像するから」ではないでしょうか。
しかし実際、ウェブ解析を行えるようになる最も重要なことは、アクセス解析などのツールを使えるようになることではありません。
大切なのはツールの操作ではなく、どう考え、どう進めるかという型です。ツール(アクセス解析など)は、型に沿って数字を集めたり、状況を確かめるための道具です。
では何を最初にやるべきか
解析とはどういうものか、どういうステップで進めていけばいいのか?その考え方を知ることが最優先です。
ウェブ解析ツールは、あくまでその中で状況を確認するためのものにすぎません。
この入門では、まず覚えるべき4つの流れを軸にしています。具体的には
- 現状把握:目的・KPI・計測する項目を決める
- 問題点の発見:数字から課題を見つける
- 改善案の発案と実行:小さく試し、実装→確認→公開
- 結果の確認と次策:前後比較で次の一手を決める
この4つを覚える前提で、まずは①の「現状把握」から始めていきましょう。
最初から Google アナリティクスなどのツールに触る必要はありません。むしろ見ない方が良いです。解析に対する考え方が分かって、全体像と目的が決まってから見て下さい。
目的や全体像が分かった状態であれば、ツールははるかに分かりやすくなります。
この考え方は、2010年にまとめたPDFをベースにしていますが、ツールや時代が変わっても使える基本の考え方に絞っています。はじめてウェブ解析に触れる方、触れ始めたばかりの方にたくさんダウンロードしていただいた内容です。ぜひ、今すぐ第一章にお進みください。
コンテンツ一覧・目次
1.はじめに
- 第1章:はじめに
- 第2章:読み始める為に必要なスキル
目標の立て方・学び方・調べ方を押さえ、兼業担当でも自走するには
2.現状把握
- 第3章:解析の第一歩
何をすべきかを整理。目的の言語化、関係者整理、キーマン特定の手順で、初動の迷いをなくす - 第4章:歴史を調べる
過去の運営履歴から挫折要因を見抜き、CMSや体制を最適化。再スタートで同じ失敗を繰り返さない土台を - 第5章:指標を確認・決定する
成果を数字で判断するKPI設計の基本。具体例とGAの考え方で、上司に伝わる評価軸と運用基盤を整える
3.問題点の発見
- 第6章:現状の確認
現状の数値を棚卸しし、問い合わせまでの行動を分解。離脱点を特定し、改善の優先順位づけ - 第7章:アクセス解析で洗い出し
アクセス解析で離脱箇所を特定。必要な用語と見方を押さえ、効果の大きい箇所からテコ入れする勘所 - 第8章:具体的なステップ1
検索→クリックの壁を突破。キーワード設計・タイトル最適化・CTRの考え方で、流入数を計画的に伸ばすには - 第9章:具体的なステップ2
“最後の一押し”を最適化。導線やフォーム項目、必須指標の見方を整え、問い合わせ率(CVR)を底上げ - 第10章:その後
Webの役割を商談プロセスに接続。上流からの優先順位付けで、限られた時間でも成果を最大化 - 第11章:ユーザーテスト
数字だけでは見えない“つまずき”を可視化。低コストで始める進め方と、改善点の絞り込みを
4.改善案の発案と実行
- 第12回:改善案の発案のコツ
少人数で速く回す発案法。やり過ぎを防ぐ設計と計測前提の考え方で、再現性のある改善 - 第14回:施策の実行
施策実行前後の“記録と証跡”の作り方。変更意図・日時・スクショ・注釈を残し、学びを資産化 - 第13回:気をつけたいこ
検証で迷わない心得。必要サンプル数・小さな積み上げ・計測設計の三本柱で、ブレない意思決定 - 第15回:結果はすぐには分からない
統計的な差の見極め方を理解。十分な件数まで“待つ”判断や代替手段。
5.結果の確認と次策
- 第16回:待つしか無いのか?
検証待ちの間にできる攻めの手を提案。先出しコンテンツや競合観察で、次の成果への布石を。 - 第17回:他の要因策
季節・社内施策など外部要因を織り込む視点を獲得。現場の声を取り入れ、解析に偏らない判断 - 第18回:新たな施策を打つ
結果を踏まえた次の一手の選び方。ユーザー基準の優先順位と体制強化で、継続改善を加速 - 第19回:情報収集は欠かさずに
変化の早いWebで迷わない情報収集術。ニュースの捉え方やRSS・共有の仕組み化で、学びをチームの力に
おわりに
- 第20回:終わりに
解析は手段、目的は改善。部門横断で改善を回す担当者の役割を確認し、現場で生きる指針を。