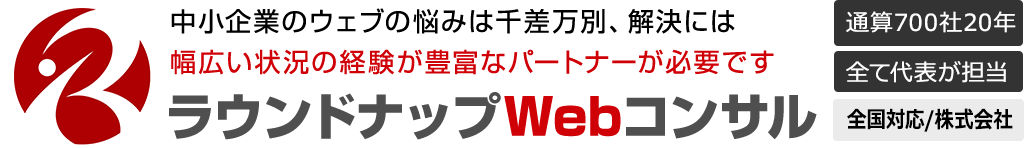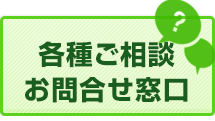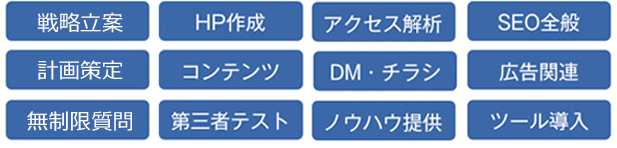サンプル数を確保すること
 また、一つ一つ行うとしても、それらの間隔に注意した方がよいです。
また、一つ一つ行うとしても、それらの間隔に注意した方がよいです。
正確には、サンプル数がある程度取れるまでは次の策を打たない、ということです。やはり最低500PV、統計学的にはその倍の1000はないと、有意な判断ができません。
まとめると
どんなにはやる気持ちがあっても、一回に行う策は一つだけ、
そして最低でも500PV位のサンプル数が集まるまでは次策を打てない、判断できないと思うべし
といった言葉になります。
細かい所の積み重ねが効果を生むことを忘れない
先ほどの項目と似ていますが、ホームページを解析して改善していく課程は、大きな石をのけていくと言うよりも、細かい所を修正して積み上げていくものです。
サイトを改善する初期の段階なら、明らかなる改善点がたくさんあるので、一発でそれなりの変化を感じられますが、その後の安定運用期になると「良くなったような気がする…」レベルの変化が大半になります。
そこをなるべく正確に判断して、少しづつ平均滞在時間や平均ページビュー、そしてCR・コンバージョンレートを上げていくというのが実際です。
「神は細部に宿る」という言葉がありますが、ウェブサイトも全くその通りです。
こんな小さな所の変更がこんなに大きな変化をもたらすんだなんて!ということが往々にしてあります。
そういった意味でも、細かい所の積み重ねが効果を生むということを忘れないで下さい。
結果を計測できるようにしておくこと
施策は、それ自体が目的ではありません。それによってなんらかの目標及びそれの成功と失敗を測る「指標」を上げることが目的です。
ですので、策を打つ時には
「この施策の正否はきちんと数字で測れるようになっているか?」
ということを再確認することが大事です。
例えば、
広告からのランディングページの反応が悪い。ページ遷移(次にどのページを見に行っているか)から考えると、一番下にある最も押して欲しい資料請求のボタンまで、アクセス者はスクロールしていないのではと考える。
そこで、スクロールしてもらえるように、目線を邪魔する横棒を取り払ったり、下の方に自然とスクロールしてくれるような文章レイアウトにしてみた。
しかし、結果としてあまり反応は上がらなかった。
この場合考えられるのは
- まだページの下の方までスクロールしてくれていない
- スクロールしてくれてはいるものの、資料請求の周りの文章が魅力的でなかった
などです。
この二つのどちらが原因なのかは、GoogleAnalyticsのようなアクセス解析だけでは判別できません。
なので、その場合はこのランディングページにCrazyEggやClickTalesのようなマウストラッキングツールを入れておこう、あるいはUserHeatのようなヒートマップを入れておこう、といったことをあらかじめやっておかないと、確度の高い判断ができません。
やってみてサンプルが集まってから「しまった!このデータだけじゃ何も分からない!」というのは、とてももったいないですよね。
ですので、何かを変更してテストする前に、できる範囲で、きちんと計測できるような環境を整えてから行うことをおすすめ致します。
コンテンツナビゲーション
コンテンツ一覧・目次
- 第1章:はじめに
- 第2章:読み始める為に必要なスキル
- 第3章:解析の第一歩 – 現状把握
- 第4章:歴史を調べる – 現状把握
- 第5章:指標を確認・決定する – 現状把握
- 第6章:現状の確認 – 問題点の発見
- 第7章:アクセス解析で洗い出し – 問題点の発見
- 第8章:具体的なステップ1 – 問題点の発見
- 第9章:具体的なステップ2 – 問題点の発見
- 第10章:その後 – 問題点の発見
- 第11章:ユーザーテスト
- 第12回:改善案の発案のコツ – 改善案の発案と実行
- 第13回:気をつけたいこと – 改善案の発案と実行
- 第14回:施策の実行 – 改善案の発案と実行
- 第15回:結果はすぐには分からない – 結果の確認と次策
- 第16回:待つしか無いのか?- 結果の確認と次策
- 第17回:他の要因 – 結果の確認と次策
- 第18回:新たな施策を打つ – 結果の確認と次策
- 第19回:情報収集は欠かさずに – 結果の確認と次策
- 第20回:終わりに