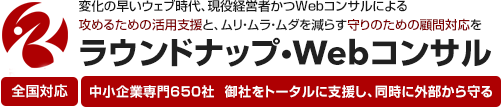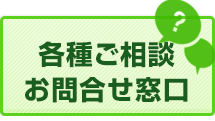まずやるべきは「現状把握」!
それではさっそくウェブ解析を始めましょう!
…と言いたいところですが、「どこから手をつければいいのか」「まず何をすべきなのか」迷うことも多いでしょう。言われたことをなんとなくやっているけれど、その意味がよくわからないという状況もあるかもしれません。
なぜこのようなことが起こるかというと、どんな仕事でもまず自分の役割や立ち位置を理解しないと、本当に何をすべきかが見えてこないからです。
そのための第一歩は、HTMLなどの技術的な知識よりも先に、会社内での自分の役割や立場を把握することです。
具体的には、
「なぜあなたはウェブ解析を担当することになったのか」
を明確にする必要があります。
あなたにその仕事を任せた人が明確にその理由を理解しているなら、直接聞いてみるとよいでしょう。
しかし、その人自身もさらに上の人から依頼を受けている場合、本来の目的や具体的な作業内容があいまいなことも珍しくありません。その場合は、自分で積極的に目的や目標を設定して、自分が行動する際の指針を作りましょう。
解析ツールやSEO、広告は「手段」に過ぎない
ウェブ解析やSEO、SEM、広告などはすべて、何かの目的を達成するための「手段」にすぎません。
ウェブサイトを解析すること自体が目的なのではなく、それを活用して特定の目標を達成することが目的なのです。
必ずその背後には、期待される効果や目的があるはずです。仮に「みんながやっているから」という理由で始めたとしても、「ウェブサイトを通じて問い合わせを増やしたい」「企業の信頼感を高めたい」といった具体的な目的が隠れているはずです。
本来、ウェブサイトはお客様と接するための多くのチャンネルの中の一つに過ぎません。それを通じて何を実現したいのか、まず明確にしていきましょう。
「手段の目的化」を絶対に避ける!
これを怠ると「手段が目的化」してしまい、仕事をしているふりをするためだけの作業を繰り返し、会社にとって実質的な利益を生まないことになります。
ウェブ解析は難しいと思われがちで、周囲が理解してくれないこともよくあります。そのため、説明の仕方によっては自分の立場を簡単に守れてしまうこともあるでしょう。しかしそれは誰のためにもなりません。
関係者を把握する、人が何よりも重要
まず鍵になるのは「人」なんです
自分が何をすべきかを明確にするためには、まず「人」が鍵になります。
まずはあなたに仕事を任せた人に確認を取りましょう。そこで答えが得られなければ、さらに上の人に確認して、会社の大きな経営的要望を掴みましょう。
この作業を通じて、誰が最終決定者であるか、社内の関係図も自然に把握できます。
次に、実務的な関係者を明確にしましょう。
ウェブサイトに関わる利害関係者をリストアップします。
例えば、小売店の場合なら
- 店舗の売場責任者
- 仕入担当者や責任者
は必ず関わってきますし、採用担当者や契約農家なども関係するかもしれません。
細かくなりすぎないように、簡単なスケッチでA4用紙に収まる程度にまとめれば十分です。ビジネスモデルや業務の流れを図式化するイメージです。
特に「買い手」に近い人は必ず押さえる
次に、リストアップした関係者と直接会話しましょう。
挨拶程度でも構いませんが、「ウェブサイトの担当になりました」と認識してもらうことが重要です。
企業規模が大きい場合、新しいウェブプロジェクトを知らない社員も多いため、まず認知してもらいましょう。
あまり良くない反応をする人がいれば、特に注意して覚えておきましょう。
知識よりも機動力や人間力が重要
ウェブサイトやインターネット自体に抵抗感がある人がいると、それが原因でプロジェクトが進まないことがあります。そうした抵抗は後になるほど大きな障害となるため、最初から無理に説得せず、軽い世間話を通じて関係を築いておくのがおすすめです。
人間関係を良好に保つことや社内の勢力図を理解しておくことも重要です。そのため、ウェブの知識よりもコミュニケーション能力や機動力がある人がこの役割には向いています。
自分には向いていない…と思ったら、そういう人に手伝いってもらえるように掛け合うのが良いです。無理にやると病みます。
重要なキーマンを見つける
次に、重要人物「キーマン」を特定しましょう。
キーマンには、最終決定を下す「意思決定者」と、社内で影響力がある「ご意見番」の2種類がいます。
ここで、誰に確認を取ればいいか、誰の承認が必要かを明確にしましょう。キーマンを把握せずに動くと、意図しない結果を招くことがあります。
現場のキーマンに目的を確認する
次は、キーマンを中心に現場の声を聞きます。
経営戦略とは別に、現場の意見を聞くことが重要です。なぜなら、実際に協力してくれるのは現場の人たちだからです。人間関係を良好に保ちながら、上層部と現場のバランスを取って進めましょう。
コンテンツナビゲーション
- 前のページ:第2章:読み始めるために必要なスキル
- 今のページ:第3章:解析の第一歩 – 現状把握
- 次のページ:第4章:歴史を調べる – 現状把握
目次・コンテンツ一覧
- 第1章:はじめに
- 第2章:読み始める為に必要なスキル
- 第3章:解析の第一歩 – 現状把握
- 第4章:歴史を調べる – 現状把握
- 第5章:指標を確認・決定する – 現状把握
- 第6章:現状の確認 – 問題点の発見
- 第7章:アクセス解析で洗い出し – 問題点の発見
- 第8章:具体的なステップ1 – 問題点の発見
- 第9章:具体的なステップ2 – 問題点の発見
- 第10章:その後 – 問題点の発見
- 第11章:ユーザーテスト
- 第12回:改善案の発案のコツ – 改善案の発案と実行
- 第13回:気をつけたいこと – 改善案の発案と実行
- 第14回:施策の実行 – 改善案の発案と実行
- 第15回:結果はすぐには分からない – 結果の確認と次策
- 第16回:待つしか無いのか?- 結果の確認と次策
- 第17回:他の要因 – 結果の確認と次策
- 第18回:新たな施策を打つ – 結果の確認と次策
- 第19回:情報収集は欠かさずに – 結果の確認と次策
- 第20回:終わりに