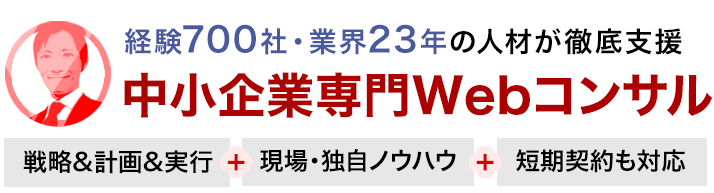次は、状況を数字で把握するためのチェック指標を決めよう
ここまでで、状況を把握したら、その上で「なにを目標として」「それの改善・悪化を把握するためにどの数字を見るか」を次は考えます。つまりは「何を目指して、それをどの数字で判断するか」です。
状況を把握するためには、定量的な指標を設定し、その数値を基準に評価できるようにすることが重要です。そして、それをまわりも含めて「納得」「OK」をもらう事が大事です。
前提:明確な指標が取れない場合もある
ウェブ解析というと、解析ツールで簡単に定量的な数字が取れると思いがちですが、実際にはそう簡単ではありません。
個人情報保護の規制が強化され、解析ツールで取れるデータは減っています。
また、Web上のコンバージョンが最終的なゴールではなく、その先の商談や契約、LTVなども考慮する必要があります。しかし、これらは解析ツールだけでは捉えきれない部分も多いため、営業やカスタマーサポートなどと連携し、業務全体で数字を把握することが大切です。
指標は既存の数値を当てはめるのではなく、成果に関連するであろう指標を自分で見つけ出し続けることが重要です。また、その指標は周囲の人にも理解しやすいものを選び、分かりやすい説明ができるよう準備しましょう。
指標は2つのレベルで考える
1.会社としてのKGIを意識する
会社全体の重要目標(KGI)は常に意識しておくべきです。ウェブ担当者が自分のタスクに集中しすぎると、手段が目的化してしまう恐れがあります。会社の目標に対してどのように貢献するかを常に意識することが重要です。
2.部門のKPIと個人のKPI
部門としてのKPI(重要業績評価指標)と個人としてのKPIは分けて考えることを推奨します。
会社が求める部門のKPI(リード数、見込み客の数、反響数など)は重要です。ただ、それだけをそのまま個人の指標としてそのまま採用すると、精神的に負担が大きくなりがちです。
以下の様なことはあるはずです。
- 施策を打ったけれど、結果につながるまでには絶対タイムラグがあります。
- 今日一日で終わらせることを、結局できなかった、でもそれは未来に繋がります
- 期日までに、いろいろな事情でできなかった、でも次の期間に実を結ぶこともあります
こういう時に結果ばかり見ていると、自分はこれができなかったというふうに自分を追い込んでしまいがちなんですね。
もちろんそれは会社という中の人間としては重要なんです。
でも、それだけ見ているとやっぱり人間とても追い詰められてしまう。
なので、もう一つ指標を持った方がいいです。それが「努力したというプロセス」に対する指標です。それを自分の中だけでいいので持っておくことをお勧めします。
自分自身を評価するための「自分KPI」
どれだけトライしたか、どれだけ諦めなかったか。
自分がどれだけ頑張ったかというプロセスに関するKPIを自分の中で持つことを強くお勧めします。
できれば、こうしたプロセスのKPIについては上司や管理者も理解してあげることが望ましいです。なぜなら、ウェブ担当者やデジタル担当者は、精神的に疲弊しやすい立場だからです。
そのため、会社としても担当者自身としても、プロセスを含めたマネジメントが必要です。
具体的な部門KPIの例
- メールマガジン登録数
- Webサイト経由の電話問い合わせ数
- 資料請求数
- 顧客単価
これらの指標は定量的に数値化できることが大切です。
定性的な印象ではなく、明確な数値を指標としてください。解析ツールや機関システムなどのデータを活用し、必要に応じてシステム部門と連携してデータを取得しましょう。
当然、上司へのレポートはこの指標の変化がメインになります。
解析ツールや機関システムを活用することが一般的ですが、必要なデータが取れないこともあるため、事前にシステム部門などと調整しておくことが重要です。解析ツールの数字だけに頼るのは避けるべきですし、そもそもビジネスプロセスを網羅なんて出来るものではありません。
このタイミングで「軽く」アクセス解析に触れておこう
ここで、おすすめなのが一度アクセス解析ツールに触れておくことです。ここまでの流れで、全体としてどのような目的を持ち、どんな数字を取っていくかは決まってきたと思います。
しかし、ここで「じゃあその数字は取れるのか?」「そもそも適切なのか?」「ツールでどれくらい細かく分析できるんだ?」等をおさえておかないと、いざこの先進んでいったときに、採れると思っていたデータが分からなかった、事前に設定をしないと分からない物があり、時既に遅しといったことが起きてしまいます。
また、この段階は知りたいことが最もはっきりしている段階なので、アクセス解析ツールの項目などに最も興味が湧きやすく、学習に最適です。自分の知りたい数字はどこから分かりそうか?その数字の周辺のさまざまな用語含めて
「この数字はどういう意味なんだろう」
「あ、こんな切り口でも分かるのか」
「こういうデータは分からないんだな」
といった、地に足のついた真名を得やすいタイミングなのです。ここを逃す手はありませんし、ここで一度触れておくなり、外部講師にセミナーを開いてもらうべきです。
一般的な解析ツールとして絶対導入したい物
これら3つのツールは最低限押さえておくべきです。また、興味のあるツールがあれば積極的に試してみてください。好奇心は最大の武器の1つです。
とは言え…まずは始めることが大事
ここまで、利害関係者とキーマンの把握、サイトの目的や指標の設定、そして過去のWebサイトの変遷を確認しました。これでウェブ解析と改善活動のスタート地点に立ったことになります。
実際にWebを活用しながら見えてくることもたくさんあります。最初から完璧を目指す必要はありません。まずは20点でもいいので始めましょう。何もしなければ常に0点です。
最も大切なのは実践を通じたノウハウの蓄積で、それが将来、会社の知的資産や差別化ポイントになります。
コンテンツ一覧・目次
- 第1章:はじめに
- 第2章:読み始める為に必要なスキル
- 第3章:解析の第一歩 – 現状把握
- 第4章:歴史を調べる – 現状把握
- 第5章:指標を確認・決定する – 現状把握
- 第6章:現状の確認 – 問題点の発見
- 第7章:アクセス解析で洗い出し – 問題点の発見
- 第8章:具体的なステップ1 – 問題点の発見
- 第9章:具体的なステップ2 – 問題点の発見
- 第10章:その後 – 問題点の発見
- 第11章:ユーザーテスト
- 第12回:改善案の発案のコツ – 改善案の発案と実行
- 第13回:気をつけたいこと – 改善案の発案と実行
- 第14回:施策の実行 – 改善案の発案と実行
- 第15回:結果はすぐには分からない – 結果の確認と次策
- 第16回:待つしか無いのか?- 結果の確認と次策
- 第17回:他の要因 – 結果の確認と次策
- 第18回:新たな施策を打つ – 結果の確認と次策
- 第19回:情報収集は欠かさずに – 結果の確認と次策
- 第20回:終わりに