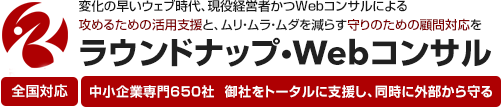ウェブサイトの現状を把握するためのポイント
前の章で、Webサイトの目的や重視するべき指標についてイメージがつかめたと思います。次に必要なのは、現在のウェブサイトがどれくらいその目標を達成できているかを把握することです。
すぐに解析ツールを見てはいけない、見る力が無いと何も見えないから
ここで注意したいのが、すぐに解析ツールを見ないことです。
解析ツールはあくまでサポート役であり、どんな数字をチェックしたいのか、なぜチェックするのか、そういったことが分かった上で見ないと、解析ツールの数字に振り回されるという最も良くない状況になってしまいます。
AIツールは魔法の杖では無い、まずは自分で出来るようになるべし
最近はAIツールに問題点を尋ねたり、Google Analyticsの自動解析機能を利用したりする方法もありますが、特に最初はおすすめできません。
- AIは一般的な回答を示すものの、実際のお客さんと直接向き合っている皆さんの感覚に勝るものはないからです。
- 後述するように、最も重要なのは自らにお客さんを憑依させて、同じ目線で体験すること。
- ツールはあくまで皆さんの能力を掛け算するものです。もともとが0の場合には何倍しても0にしかなりません。
- みなさんがWeb解析のノウハウを学ぶことは必須です。 しかし、少なくとも最初は、AIは過程で現れる面倒な作業の効率化やアイデア出しのサポートとして利用するのが適切です。
実際にユーザー体験をしよう、メモを取ろう
まずは、お客様になりきって、自分自身でステップを追体験しましょう。このとき、気づいたことや改善点はそのままの言葉でメモしてください。整理すると実際のお客さんの感覚とズレが生じるため、生の言葉を大切にしてください。
例えば、問い合わせをした後も不安になって、サイトのサンクスページに書いてあった文章などについて調べたりする。自動返信メールの内容を見て、ちゃんと対応してくれるかなと悩んだりする。 生々しいほど良いです。
解析ツールでチェック可能なポイントを探す
体験を通じて特に重要だと感じたポイントがあれば、そこで初めて解析ツールの活用を検討します。子のタイミングで触れるのがベストです。なぜなら、具体的な目的を持ってツールを使う方が、効率的に知識を得ることができるからです。
指標は柔軟に追加・修正をする
指標は一度決めたら変えられないと考えていませんか?それは違います。後からいくらでも追加や修正をしてもよいのです。 ウェブサイトごとに最適な指標は異なるため、自分たちに合った指標を見つけて常に改善していきましょう。取れない情報も当然あります。
その場合は別の指標で大丈夫か、あるいは違うポイントを優先しましょう。無理な物は無理なのです。
また、GA4やSearch Console以外にも様々な解析ツールがあるので、必要に応じて試してみることもおすすめします。
包括的な解析ツールの本を最初から読むのは非効率
解析ツールの包括的な解説書は網羅性が高い反面、最初から読んでも実践的な理解は難しいものです。まずは自分でチェックポイントを設定し、その必要性を感じてから具体的な情報を調べることで、より深い理解が得られます。
多くの場合、読んでも頭に入らないことがほとんどです。
- なぜなら、それをすぐに実践する機会もないですし、必要性を感じられない、つまりはモチベーションが湧きづらいからです。
- そうではなく、自分でチェックすべきところを間違っててもいいから決める。自分でやったというプロセスを経ると、大きな気づきとモチベーションが生まれます。
自分の気にしていたことは、どうにかして数字が見られるような状況にできるのか。気持ちが大きく変わるのです。
第三者によるユーザーテストも有用
さらに、実際のお客さんや第三者にユーザーテストを実施することで、より客観的で有益な情報を得ることができます。自分たちのバイアスを排除するためにも、自社でのロールプレイと第三者によるユーザーテストを併せて実施しましょう。
ではそうやってお客さんの目を持ちながら改めて皆さんのウェブサイトをぜひチェックしていってみてください
それを踏まえて、お客様目線でステップをを決めていこう
では、具体的なチェックポイントをどう見つけるかというと、お客さんの立場に立って情報収集や比較検討の流れを追体験するのが効果的です。そのために今までの気づきを元にステップに分けていきましょう。
ユーザー行動の具体的な流れ(例)
- パソコンの前に座る(スマホを出す)
- 検索エンジンで特定のキーワードで検索したり、SNSや動画配信サイトで情報を集める
- たくさん出たサイトや情報などの中で、いくつかめぼしい物を見たり保存したりしていく
- その中で御社のWebサイトやアカウントもクリックされて、閲覧される
- 閲覧し、他のサイトと比較されながら検討する、
- 後回しにされることもあるが、不定期に再チェックしに来る
- 結論としてあなたの提供している商品やサービスが良いと思う
- 問い合わせ方法を探す、自分に合った物を見つけようとする
- フォームに入力する(他にも手段はありますが)
- 送信ボタンを押す
実際はこのように、多くのプロセスを経てユーザーは問い合わせに至ります。
前後の行動も含めて考える
さらに、お客さんがなぜそのサービスを探し始めたのか、問い合わせ後のフォローアップや不安の解消方法など、前後の行動も考慮すると、より詳細なチェックができます。理想的には、情報収集からコンバージョンまでの一連の流れを把握しましょう。
ではこの次の章から具体的に各ステップについて追いかけていきます
コンテンツ一覧・目次
- 第1章:はじめに
- 第2章:読み始める為に必要なスキル
- 第3章:解析の第一歩 – 現状把握
- 第4章:歴史を調べる – 現状把握
- 第5章:指標を確認・決定する – 現状把握
- 第6章:現状の確認 – 問題点の発見
- 第7章:アクセス解析で洗い出し – 問題点の発見
- 第8章:具体的なステップ1 – 問題点の発見
- 第9章:具体的なステップ2 – 問題点の発見
- 第10章:その後 – 問題点の発見
- 第11章:ユーザーテスト
- 第12回:改善案の発案のコツ – 改善案の発案と実行
- 第13回:気をつけたいこと – 改善案の発案と実行
- 第14回:施策の実行 – 改善案の発案と実行
- 第15回:結果はすぐには分からない – 結果の確認と次策
- 第16回:待つしか無いのか?- 結果の確認と次策
- 第17回:他の要因 – 結果の確認と次策
- 第18回:新たな施策を打つ – 結果の確認と次策
- 第19回:情報収集は欠かさずに – 結果の確認と次策
- 第20回:終わりに