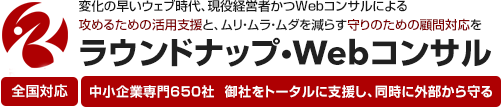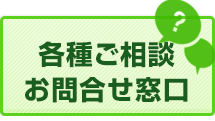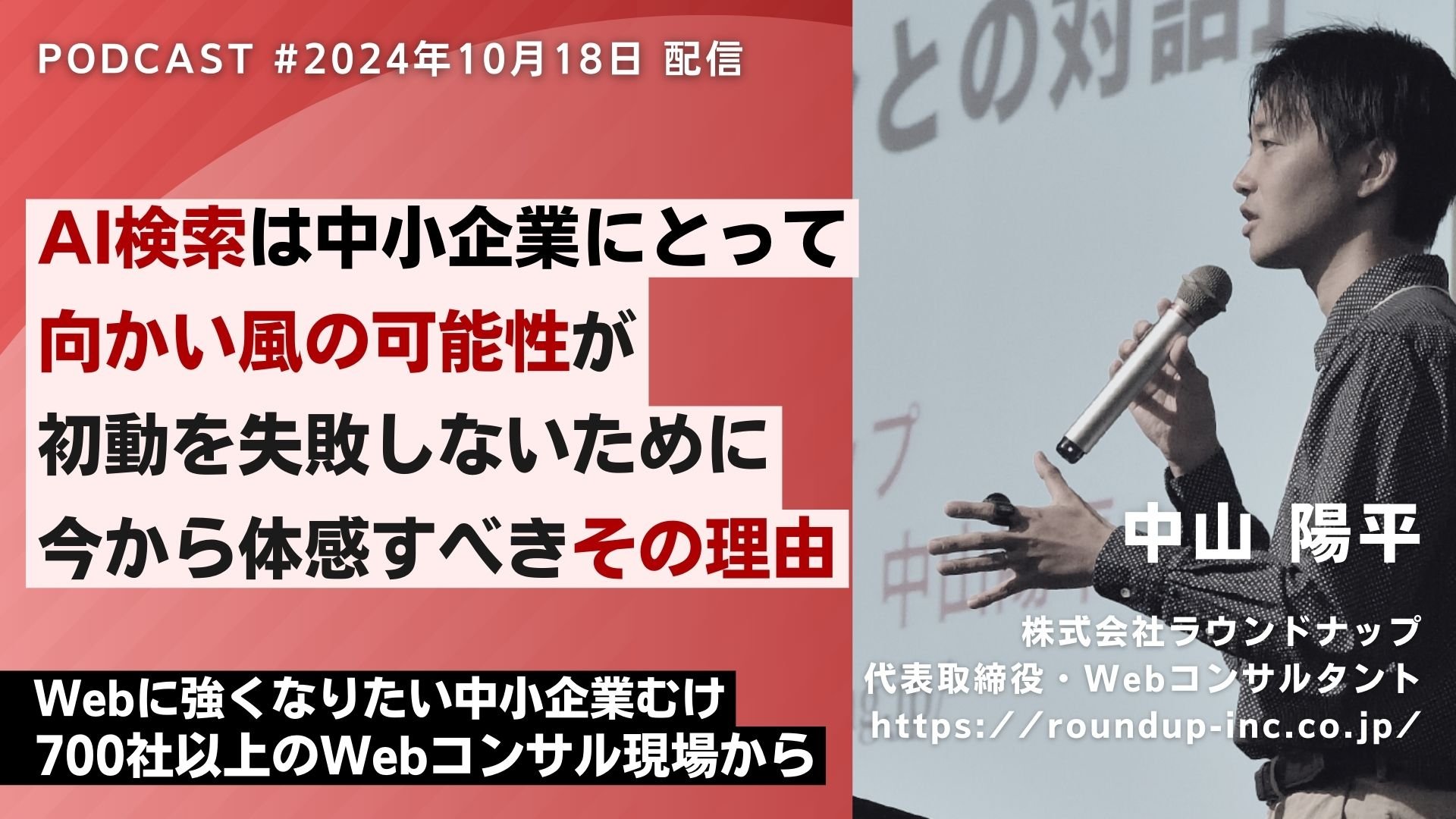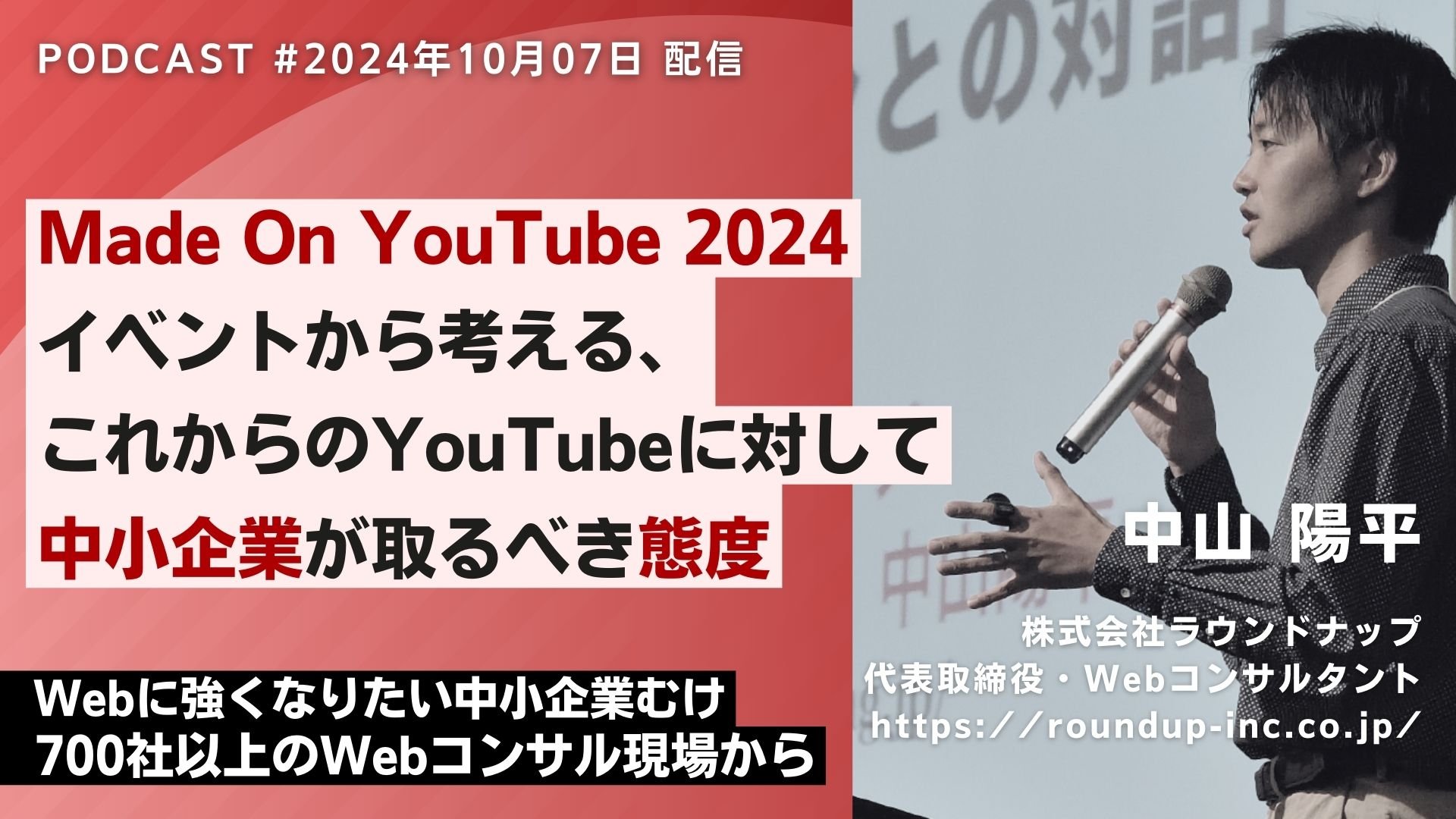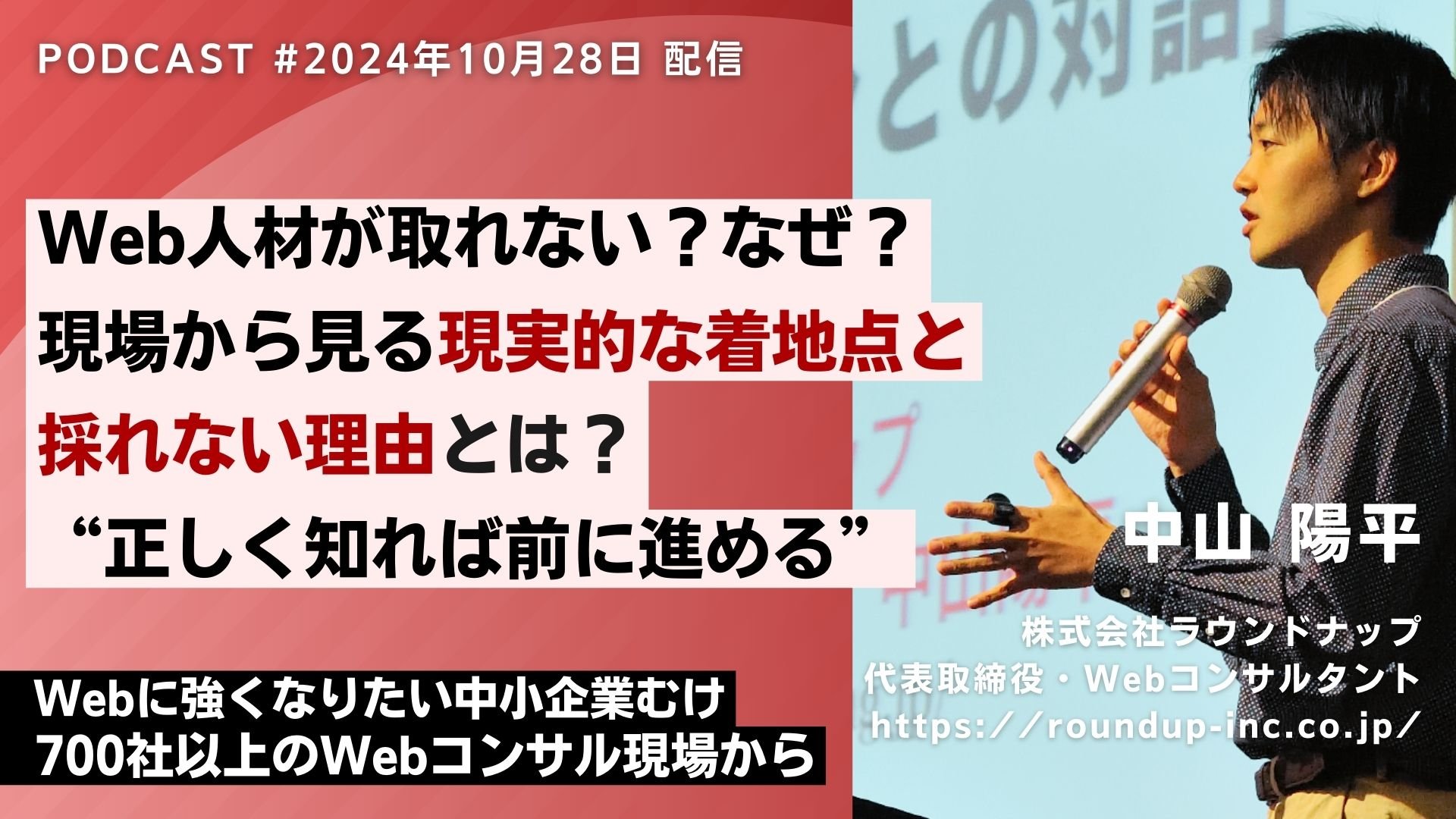Podcast: Embed
Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More
AI検索が当たり前になりつつある今、何が起きているのか
今日は、AI検索が広がっていく中で「自社サイトはこれからも見つけてもらえるのか」という不安と、それに対して今からどんなWeb戦略を考えておくとよさそうか、少し腰を据えてお話ししたいと思います。
まず、背景として押さえておきたいのが「主要な検索エンジンのほとんどが、AIが生成した回答を検索結果の目立つ位置に出すようになってきている」という点です。
Yahoo!検索の「〇〇とは」AI回答
日本だと特に影響が大きそうなのが、Yahoo!検索です。Yahoo!は「〇〇とは」という、いわゆる用語の意味を調べる検索に対して、AIがまとめた回答を一番上に表示する仕様を入れました。
もともとこれはスマートフォン版から始まりましたが、2024年10月にはスマートフォン版「Yahoo!検索」で生成AIによる回答表示機能が提供開始され、その後2025年8月5日からはPC版でも同じ機能が使えるようになっています。
「Z世代とは」といったキーワードで検索すると、上部にAIの回答がまとまって表示され、その中に小さく引用元へのリンクが並ぶ、という形ですね。見た目としては、GoogleのAI概要やBingのAI回答と似ています。
Google検索のAI機能の変遷と現在
Googleも、以前から「Search Generative Experience(SGE)」という名前で、生成AIによる回答を検索結果の上部に表示する実験を続けてきました。日本では2023年8月から、Search Labsに参加した一部ユーザーを対象に日本語版の試験運用が始まっています。
この収録をしていた当時は、「設定をオンにした人だけが使える試験機能」という位置づけでしたが、その後大きな変化がありました。Googleは2025年9月9日に、AI検索の新しい形である「AIモード」を日本語でも提供開始することを発表し、順次すべてのユーザーに展開しています。
そして2025年11月13日現在、日本ではGoogle検索のAIモードが全ユーザーで利用できる状態になっています。つまり、多くの人が意識せずとも「AIがまとめた答え」を検索の入り口で見るようになってきた、という状況です。
主要な検索エンジンがそろってAI回答を出す世界
こうした動きをまとめると、日本でよく使われている検索エンジン上位3つ、つまり
- Google検索(AIモード・AI概要など)
- Yahoo!検索(生成AIによる回答表示機能)
- Bing(AIチャット・Copilot系の回答)
のいずれも、条件が合えばAIが生成した回答を検索結果の目立つ位置に出すようになってきている、ということになります。
ここまで聞くと「インフォメーション系のキーワード(〇〇とは)で集客するのが難しくなりそうだな」という話に思えるかもしれませんが、今回お話ししたいのはそれ以上の部分です。
AI検索が「次の質問の選択肢」を出すようになった意味
個人的に一番インパクトが大きいと感じているのは、「AIが回答したあと、次に聞きそうな質問を候補として並べてくる」というインターフェースです。
Yahoo!検索の「AIに追加の質問をする」ボタン
先ほどのYahoo!検索で「Z世代とは」と調べると、AIの回答が表示された一番下に「AIに追加の質問をする」という青いボタンがあります。これを押すと、自由入力で質問できる画面に進みます。
そのすぐ上には、横にスライドできるカード形式で、
- 「Z世代はどのような価値観を持っているのか…」
- 「Z世代はどのようなテクノロジーに親しみがありますか」
といった「次に聞きそうな質問の候補」が並びます。これをタップすれば、そのまま続きの会話が始まるわけです。
ここでポイントなのは、「ユーザーが自分で次の質問を考えて入力する」のではなく、「AIが提案した候補の中から選ぶ」という形が用意されていることです。
Perplexity(パープレキシティ)も同じ流れ
同じような流れは、Perplexity(パープレキシティ)という検索エンジンでも強く出ています。Perplexityは「AI answer engine(回答エンジン)」を名乗っているサービスで、自然文で質問すると複数の情報源をまとめて答えを返してくれるタイプの検索ツールです。
特に「Pro Search(プロサーチ)」という高度検索機能を使うと、質問に対して
- いくつかの観点ごとに整理された回答
- 参照した情報源へのリンク
- そして「次にこんなことも調べますか?」というリンク
まで自動で出してくれます。
例えば「サーチエンジンランドを運営している会社はどこか」と聞くと、「サードドアメディアが運営していて、SEMツールを提供するSEMrushに買収された」というところまで、かなり詳しく返してくれます。
そのうえで、
- 「サードドアメディアについて詳しく調べますか」
- 「サードドアメディアが運営する他のサービスを調べますか」
といった「次の一手」も提案してくる。これをクリックしていくだけで、どんどん深掘りできる、という体験になっています。
自由入力から「選択肢ベース」へのシフト
ChatGPTのように自由入力で質問を投げるタイプのAIもありますが、検索エンジン側は「次の質問候補」をボタンで提示して、ユーザーに選んでもらう方向へかなり舵を切っています。
理由はシンプルで、
- 候補から選ぶ方が、ユーザーにとって楽
- 多くの人が「確かにそれも知りたい」と思う質問が出てくる
からです。何度か使えば「この候補から選んでいけば、だいたい欲しい情報にはたどり着ける」と感じやすいはずです。
その結果として何が起きるかというと、世の中で発生する「質問のパターン」が、だんだんと絞り込まれていく、ということです。
平均的な質問・平均的な解決策に収束していく検索体験
AIが「次の質問候補」を提案する形が一般的になると、ユーザーの質問は「候補に出てきたもの」の中で完結しやすくなります。自由入力ならバラバラだった疑問が、ある程度決まったパターンの中に収まっていくイメージです。
「中央値」の質問に合わせた世界
統計の言葉でいうと、「中央値」に近いところに、質問のパターンが寄っていく可能性があります。多くの人が
- このテーマであれば、こういうことを心配する
- この商品を探すときは、こういう観点で比べる
という「多数派」のパターンに沿って、AIが質問候補を出していくからです。
しかも、検索エンジン側は個々人の細かい情報(どんなサイトを見ていて、どんな体質で、どんな属性かなど)を、プライバシーの観点から自由に使えるわけではありません。ですから、どうしても
- 「できるだけ多くの人が外れない答え」
- 「大きく間違ってはいないが、平均的な解決策」
に寄せざるを得ません。
虫除けスプレーと「鬼ヤンマのおもちゃ」のような話
例えば、「蚊に刺されすぎて困っている」という人がいたとします。一般的な検索であれば、
- 虫除けスプレー
- 蚊取り線香
- 体質改善
- 網戸や窓の対策
といったメジャーな解決策が並ぶでしょう。
一方で、「実はうちの会社のこの商品、全然違う用途だけど、蚊よけにも使えるんです」というケースもあります。極端な例ですが、「鬼ヤンマの形をしたおもちゃを吊るしておくだけで蚊が寄りにくくなる」といった、ちょっと変わった商品があったとします。
これまでは、きちんとコンテンツを作り、検索エンジンに評価されれば、
- 「蚊に刺されない方法」
- 「蚊に刺されやすい体質 対策」
のような検索結果の中に、そうしたユニークな商品が紛れ込む余地がありました。
ところが、AI検索が「多くの人が選びそうな解決策」だけを候補として出し、その中でさらにAIが回答をまとめてしまうようになると、
- 虫除けスプレー
- 皮膚科や内科での相談
- 生活習慣の見直し
といった「王道の選択肢」以外は、極端に見つかりにくくなる可能性があります。
つまり、
- ニッチな商品
- 既存のカテゴリーから少しはみ出した解決策
- 「その発想はなかった」と思うようなアプローチ
が、ユーザーの目に触れづらくなる懸念がある、ということです。
私自身、この流れを見ていて「マーケティングの打ち手の幅が、以前よりも狭まりそうだな」という感覚を持ち始めています。
ニッチな商品・新しい切り口で戦うための「二段構え」戦略
では、ニッチな商品や新しい切り口でビジネスをしている場合、どう考えればよいのでしょうか。
ここで大事になってきそうなのが、「一度は王道の文脈に乗る。そのうえで、そこで出会えた人に対して別の切り口を提示する」という二段構えの考え方です。
まずは「王道の回答ゾーン」に入り込む
Googleをはじめとする検索エンジンは、大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)を使って、Web上の膨大なコンテンツ同士の距離感を学習し、「このテーマなら、こういう内容を出すのが妥当だろう」という形でAI回答を作ります。
その意味で、まずは
- 一般的な悩み方や質問の仕方
- 平均的な解決策として認識されている選択肢
に、コンテンツとしてきちんと乗っておく必要があります。
例えば、先ほどの「蚊に刺されやすい」という例で言えば、
- 一般的な原因や対策をきちんと整理したコンテンツ
- 生活習慣・環境・市販薬・グッズなど、王道の選択肢を網羅した解説
を、まずはしっかり作る。ここで無理に「うちの商品は全然別のアプローチで…」と最初から推しすぎると、「中央値のゾーン」から外れてしまい、AI回答からも外れやすくなります。
そのうえで「実はこういうアプローチもあります」と提示する
そのうえで、コンテンツの中や次のステップで、
- 「一般的にはここまでが王道の対策です」
- 「ただ、こういう状況の方には、こういうアプローチもあります」
といった形で、自社ならではの提案を入れていきます。
イメージとしては、
- まずは「多くの人が安心できる王道の情報」をきちんと提示する
- その中で、「実はうちはこういう角度からも解決を提案できます」と、少し横道を案内する
という順番です。
これは、今まで以上に「コンテンツの構成」と「出し方」が重要になる、ということでもあります。
AI検索時代に向けて、今から体感しておきたいこと
ここまでの話は、どうしても抽象的になりがちです。正直なところ、私自身も、AI検索の挙動を日々触りながら「これはこの先どう変わっていくんだろう」と試行錯誤している段階です。
ただ、ひとつ確実に言えるのは、「実際に自分でAI検索を使ってみないと、この感覚は掴みにくい」ということです。
Perplexityを一度「メイン検索」にしてみる
例えば、Perplexityの無料版でも良いので、仕事中の検索をしばらくの間、できるだけPerplexityで行ってみる、というのはおすすめです。
自分が
- 何かを調べる
- 候補として出てきた「次の質問」を選ぶ
- そこで出てきた回答から、さらに別のリンクを辿る
というプロセスを繰り返してみると、「この世界で自社が選ばれるには、どう情報を出しておくべきか」という視点が、かなりはっきりしてきます。
Yahoo!の「〇〇とは」検索で、自社業界をイメージしてみる
もう一つ、体感しやすいのがYahoo!検索の「〇〇とは」です。
例えば、
- 「Z世代とは」
- 「インボイス制度とは」
といったキーワードで検索して、AIの回答→追加質問の流れを一通り見てみてください。そのうえで、
「これがもし、自分たちの業界のキーワードだったらどうなるか」
という視点で想像してみると、肌感覚がかなり変わってくるはずです。
組織として「納得感」をつくっておかないと動かない
ここからは、少し組織の話になります。
Web活用がうまく進まない企業さんを見ていて、よくあるパターンの一つが、
- 担当者や一部のメンバーは、変化の必要性をわかっている
- しかし会社全体としての納得感が足りない
という状態です。
経営層の方も、現場の方も、「AI検索がどう変わっているか」を頭ではなく体感でイメージできていないと、
- なぜ今、コンテンツの構成を変える必要があるのか
- なぜ二段構えの戦略にしないといけないのか
といった部分への理解が、どうしても弱くなります。
逆に言えば、例えばこんなルールを期間限定で設けるだけでも、
- 「業務中の調べものは、まずPerplexityかAIモードでやってみる」
- 「Yahoo!のAI回答が出るものは、1日1回は触ってみる」
といった、軽い取り組みから始めるだけで、社内の会話が変わってくるはずです。
もちろん、社外のパートナーに相談するのも選択肢です。ただ、その際にも、「自分たちがAI検索をどう感じているか」という感覚を持っているかどうかで、打ち合わせの密度がかなり違ってきます。
将来のパーソナライズと、いま考えておくべきこと
将来的には、Appleが取り組もうとしていると言われているような、「端末の中に自分の情報をローカルで保持し、それを外部データと組み合わせて検索する」という世界が来るかもしれません。
もしそれが実現すれば、今よりも個々人に合わせた、かなり多様性のある検索結果が出てくる可能性があります。ただし、プライバシー保護の観点からクリアすべき課題は多く、すぐにそうした世界が当たり前になるとは言い切れません。
少なくとも、現時点では
- 多くの人が外れだと感じない、平均的な回答
- 王道の選択肢を中心にまとめたAI回答
が、検索の入り口として出てくる世界が、しばらく続くと考えておいた方が現実的です。
これから1年、Web戦略で意識しておきたいポイント
ここまでの話を、実務寄りに整理すると、今後1年ほどで意識しておきたいポイントは、おおよそ次のようになります。
- AI検索を、自分自身が「お客さんの立場」で体験しておく
Perplexity、GoogleのAIモード、Yahoo!検索のAI回答などを、まずは自分の調べものに使ってみる。 - 王道の悩み・質問にきちんと答えるコンテンツを整える
「ニッチな強みを押し出す前に」、平均的な悩みに対する基本情報をきちんと整える。 - コンテンツの中で「第二段階の提案」を用意する
一般的な選択肢を説明したうえで、「実はこういうアプローチもあります」と自社ならではの提案を入れる。 - 社内でAI検索体験を共有する
経営層・現場を問わず、AI検索での情報探索を一度体験してもらい、感じたことを話し合う場を持つ。 - 変化の速さを前提に「今の結論」に固執しすぎない
GoogleやYahoo!の仕様は今後も変わる前提で、半年〜1年単位で見直すサイクルを組んでおく。
関連リンク
- 生成 AI による検索体験 (SGE) のご紹介(Google 公式ブログ)
- AI Mode in Google Search expands to more languages(Google 公式ブログ・英語)
- 【Yahoo!検索】生成AIがチャット形式で情報を深掘りしてくれる回答表示機能をPC版にも提供(LINEヤフー 公式リリース)
- Perplexity AI 公式サイト
よくある質問
- AI検索が広がると、自社サイトは本当に見つけてもらえなくなりますか?
- すぐに「まったく見つからなくなる」ということではありませんが、AIがまとめた回答の中で紹介されなかった場合、ユーザーの目に触れにくくなる可能性は高まります。特に、ニッチな商品や一般的ではない切り口のサービスは、平均的な解決策に比べて露出機会が減りやすいので、「王道の悩み・質問にきちんと答えるコンテンツ」を整えたうえで、その中で自社ならではの提案を示す二段構えの戦略が重要になってきます。
- ニッチな商品や新しいサービスは、どんなコンテンツ戦略を取ればよいですか?
- いきなりニッチな特徴だけを押し出すのではなく、「多くの人が抱える、比較的一般的な悩み」に対してきちんと答えるコンテンツを用意することが出発点になります。そのうえで、コンテンツの後半や別の記事・セクションで「実はこういうアプローチもあります」と、自社のニッチな強みや別角度の解決策を紹介する形にすると、AI検索からも人の目からも届きやすくなります。
- まず試しておくべきAI検索サービスは何ですか?
- 仕事での情報収集という意味では、Perplexity(パープレキシティ)と、Google検索のAIモード、そしてYahoo!検索の「〇〇とは」などで出てくるAI回答の3つを触っておくとイメージが掴みやすいと思います。実際に自分が調べものをするときに使ってみて、「この世界で自社が選ばれるにはどう見せておくべきか」を考えてみるのがおすすめです。
- AI検索時代でも自然検索(オーガニック検索)対策は意味がありますか?
- 意味がなくなるわけではありませんが、役割は少し変わっていきます。これからは「検索結果の一覧に表示されるため」だけでなく、「AIが回答を作るときの材料として認識してもらうため」にコンテンツを整えるという視点が重要になります。構造化データや、わかりやすい見出し構成、過度に偏らない情報設計など、AIにとっても理解しやすい形でページを作ることが、自然検索とAI検索の両方に効いてきます。
- 社内でAI検索への理解をどう広げればよいですか?
- まずは難しい勉強会よりも、「実際に触ってみる場」をつくることが効果的です。一定期間、業務中の調べものをPerplexityやAIモードで試してもらい、その体験を共有するミーティングを設けると、「なぜコンテンツの作り方を変える必要があるのか」が伝わりやすくなります。そのうえで、外部パートナーと一緒に戦略を考えると、社内の納得感も得やすくなります。
以上で、今回のポッドキャスト内容のテキスト化と関連タスク(用語修正を反映した本文生成・関連リンク・FAQと構造化データの作成)まで完了です。
配信スタンド
- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN
- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj
- Amazon Music Amazon Podcasts
■Podcast /Webinar への質問は
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
運営・進行
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/