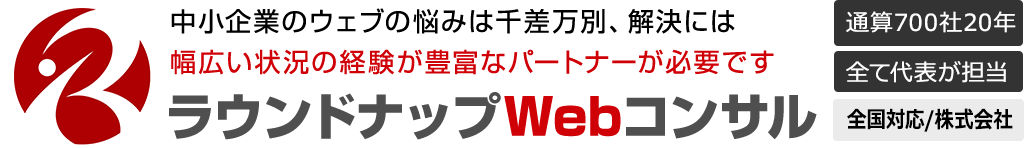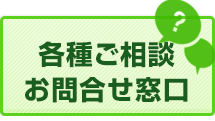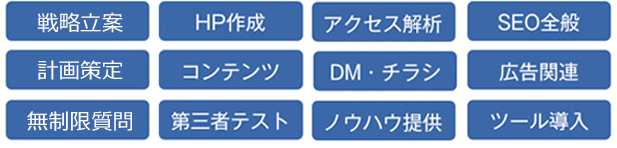関連FAQ
- 会社の事業がBtoBなんですが、Webサイトでのアピールの仕方はBtoCとやっぱり違いますか?
- B2BとB2Cという区分けはあまり意味がないです。それよりも、目の前のお客様がどう動くかを考えることが大切です。
Webの世界では、B2BとB2Cできれいに手法が分かれることはないかもしれません。例えば、企業向け(B2B)の消耗品などは個人の買い物(B2C)に近い意思決定がされますし、逆に個人向けの高級品は、家族会議が行われるなど企業向けに近い動きが見られることもあります。そのため、事業の区分に縛られず、見込み客がどう動くかを考えることが重要になります。 - B2BとかBtoCとかを考えずに進める場合、まず何から考えれば良いでしょうか?
- 大切なのは、見込み客が「どのように動き、何に触れ、どのような情報を得て、どのような意思決定をするのか」を深く考えることです。
自分たちの業界で、お客様が現在どのような価値観で商品やサービスを選んでいるのか、そのステップを考えていくことが改善のスタート地点になります。 - お客さんの要望を聞いてサイトを作った方が良いと言われますが、どこまで意見を取り入れるべきか迷います。
- お客様の意見をすべて鵜呑みにするのは注意が必要かもしれません。お客様自身も本当に欲しいものを把握していない場合があるためです。
お客様自身も、本当に欲しいものを明確に言葉にできるとは限りません。お店で商品を見て回るうちに「これが欲しかった」と気付くように、潜在的なニーズを持っていることが多いです。そのため、お客様の声を参考にしつつも、どのニーズに重点を置くべきかを見極め、自社のターゲットをしっかりと定める方向性が良いと考えられます。 - Webマーケティングの考え方は分かりますが、社内に詳しい人もおらず、最初の一歩をどう踏み出せばいいか分かりません。
- 最初は難しく感じるかもしれませんが、一度経験すれば使いこなせるようになるはずです。信頼できる外部の専門家に相談するのも有効な手段です。
こうした考え方は、社内にOJTのような環境があれば良いのですが、難しい場合も多いでしょう。一度感覚を掴んでしまえば、それほど時間はかからないものです。もし最初の一歩が難しいと感じる場合は、外部の専門家の力を借りることも選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
音声版はこちら
テキスト版はこちら
B2B(ビジネス・ツー・ビジネス)とB2C(ビジネス・ツー・カスタマー)の販売戦略は異なるとよく言われますが、Webやホームページの世界ではどうでしょうか。例えば自分のビジネスがB2Bだったとして、B2Cの手法は使えないのでしょうか。
結論から言うと、B2BとB2Cという区分けをすることはあまり意味がないので、やめた方が良いです。B2Bだから、B2Cだからときれいに手法が分かれることはないからです。
言ってしまえば、Web業界側が売りやすくするためにつけたカテゴリー分けのようなものです。いわゆるB2BビジネスでもB2C的な動きをするケースもありますし、逆もあります。
そんな区分けは忘れて、目の前のお客さんに対してどんな動きをすれば良いのか考えることが最善です。
一般的なB2BとB2Cのイメージ
辞書的な意味としては「B2B」とは、企業向けの販売を指し、一方「B2C」は一般消費者向けの商品やサービスを差します。
そして「B2B」に対する一般的な認識として、社内での稟議や比較検討、意思決定が必要と想像されがちです。しかし、実際は商品によります。例えば、細かい消耗品やAmazonやアスクルなどで扱っている商品などは、B2Cに近い意思決定がなされます。安心できるお店から購入したり、セールが開催されているために購入するなどの行動がそれに当たります。
一方で、B2Cはもっとカジュアルな、例えばSNSを見て即座に購入するような行動がイメージされるかもしれません。しかし、それだけがB2Cの特性というわけではありません。
B2BとB2Cという分類は意味がない
たとえば、高価な商品や自分の社会的地位に影響するような商品、または身につける商品などは、より深く考えて購入する傾向があります。家族の意見が影響を及ぼすこともあるため、それはまるで会議のような形となります。これらの動きは、B2Bに近いとも言えます。
したがって、B2BとB2Cという分類自体がすべてをMECEに分ける役目を果たしていないのです。強いて言えば、考える場所がオフィスであるか、家庭であるかという違いくらいでしょう。
世の中には「B2B専門○○」や「B2C向け○○」といった打ち出しやサービスが存在していますが、それは「B2Bに通じた経験がある」「B2Cでうまくいった経験がある」くらいの意味と考えて下さい。
では、B2BとB2Cにどこまで注意を払うべきか、それに代わってどのような対応が必要かという悩みが次に来ると思います。
まずは純粋に見込み客の動きを見よう
しかし、基本的には、B2BであろうとB2Cであろうと、
- 買い手がどのように動き
- 何に触れ
- どのような情報を得て
- どのような意思決定をするのか、
ということを常にどのようなサービスでも考えることが重要です。
「B2Bはこういうものだ」といった固定観念に囚われるのではなく、自分たちの業界で現在、どのような価値観を持ってお客様は選択しているのか、どのようなステップを踏んでいるのか、どのような情報に接触しているのかといったことを深く考えていくことがスタート地点です!
※このプロセスには、「ブルーオーシャン戦略」の戦略キャンバスが役立つかもしれません。
私自身も「B2Bだからこう」と定式的に考えることはありません
B2BとB2Cという概念は、無意味だとは思いません。考えるスタート地点・きっかけとして有用です。ただ、そこに縛られてはなりません。
実際、提案書やお客様へのアドバイスで「これはB2Bだから」という理由を使うことはほとんどありません。”B2Bでよくあるケース”という形で使うことはありますが、それ以外ではないと思います。
もし「B2BとB2Cの違いは何ですか?」と聞かれたら、その区別自体はあまり意味がないですよー、と答えています。
それより見込み客の、例えばデモグラフィックやジオグラフィックといった要素の方が大事です。デモグラフィックは人口や年齢、性別、家族構成など、ジオグラフィックは地理的要素を指します。さらにソシオグラフィックという社会的な要素も重要です。
だからといってお客さまの意見を鵜呑みにしてはいけない
お客様のニーズをしっかりと追い求めることが重要です。ただし、お客様の意見は多種多様で、過度に意見を採り入れることも問題となり得ます。
それは、お客様自身が本当に欲しいものが何かを確実に把握しているわけではないからです。その場その場で思い出していると言っても言いすぎではないかもしれません。
たとえば、買い物に行く際、皆さんが欲しいものをあらかじめ全て決めているわけではないですよね。商品を探して回り、良さそうなものを見つけ、それが自分の欲しかったものだと気付くのが一般的です。それを能動的に起こすためにウィンドウショッピングという行動様式があります。
実際問題、お客様に何が欲しいかを問うと、多くの場合、お客様自身も明確には答えられないことが多いです。
そのため、お客様の全ての意見を聞き入れると、どのニーズに重点を置くべきかがわからなくなる場合があります。
これはよろしくないですよね。なので、お客様の声を過度に重視するのではなく、それを元にしつつ、ニーズを満たす形で適切なボリュームを確保し、自社のターゲットを決定する方向性が良いと考えます。
困ったら相談する先を持っておくことが大事です
こういった流れは、いったん感覚を摑みプロセスを経験してしまえば、覚えて使いこなせるまでに総時間はかからないと感じています。ただ、最初の一歩が難しいですね。会社内で先輩からOJTを受けるような環境があればよいのですが、難しい企業も多いでしょう。
そういう際は、外部の専門家を入れることをオススメします。弊社でも遠隔コンサルを導入しやすい価格で用意していますので、よろしければご検討下さい。