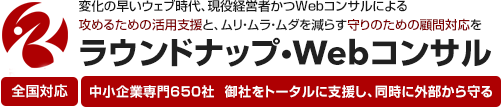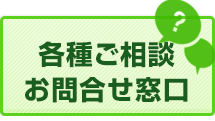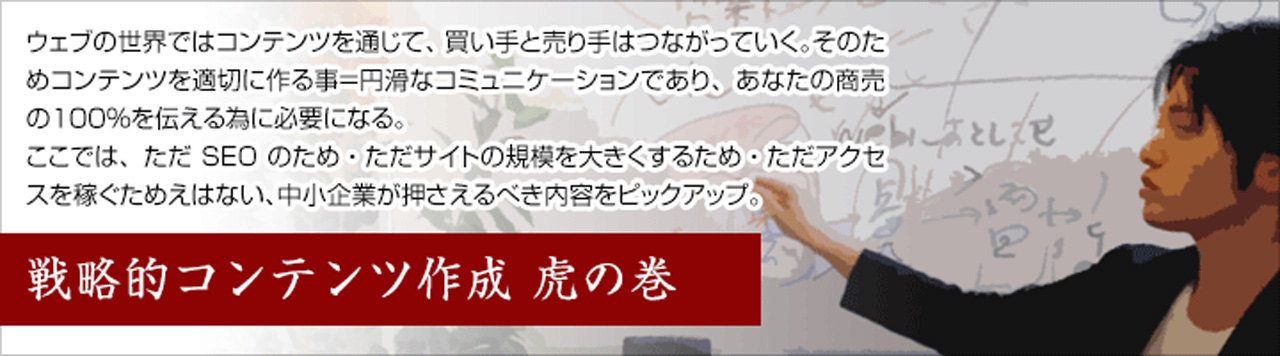
本ページはコンテンツマーケティングのベースとなる「コンテンツ作成」の基本→手順→改善→事例を、目的別に最短ルートでまとめたページです。まずは下の目次から興味の湧いた物をを選んでお読み下さい。
今、WEB戦略において最も必要とされているノウハウ・能力の1つが「WEBコンテンツ作成」に関するもの。
WEBに関しては、主にコンテンツを通じて、買い手と売り手は繋がります。その道筋をいかに最適化して、メッセージを「必要な人に」伝えてあげられるかどうかが決め手となります。非常にコンテンツは重要です。
この特集で得られる物
現場のノウハウや実際に効果を上げた事例に基づいたコンテンツ作成の知識が得られます。表面的なSEOのためのコンテンツや成果につながらないノウハウではなく、海外などで成果を上げた事例を基にしたコンテンツマーケティングの手法、手段を知ることができます。
コンテンツマーケティングという言葉が注目されはじめたのは2014年前後、その頃の最も熱く研究されていた時期の事例をもとに、押さえておくべきポイントをまとめています。原点からしっかり押さえたいという方におすすめです。
お勧めの読み方
目次から気になる項目を順番に読んでいただくことをお勧めします。特定の流れでないと分かりづらいようなものはなく、それぞれが1記事で完結しています。コンテンツ関連やWebマーケティングを生業にしている方も、マーケティングに興味があるという方も幅広くお役に立てる内容です。
どこから読もうと悩んだ方は上から順番に読んでいただくと最もスムーズかもしれません。
コンテンツ目次
コンテンツ活用(コンテンツマーケティング)とは?その定義と概要
コンテンツ活用(コンテンツマーケティング)とは何か?コンテンツ自体はコンテンツ・マーケティングという言葉が出る前からずっと重要視されてきたもの。重要なのはコンテンツを「ただ何かを伝えるためのものとだけ捉えるのではなく、届けたい相手にどうすれば届くかを考えることです。
-
- Webコンテンツとはそもそも何か?なぜ大事なのか?
WEBコンテンツの重要性と役割、良質なコンテンツが集客や信頼構築にどう寄与するかの全体像と考え方が学べます - 戦略的コンテンツ制作の概要
戦略的コンテンツとは何かを噛み砕いて解説。何を考え、どう作ればよいかの基本フレームが得られます - コンテンツには「16種類の形」がある
コンテンツの代表的な16のフォーマットや使いどころ、企画の幅が広がる実務的な一覧 - 〖必須の7項目〗商売に役立つコンテンツ作成におけるTips
ビジネスで成果につながりやすいコンテンツ作成の必須チェックリスト(7項目) - コンテンツ制作で苦労する3つの「キャズム」
制作プロセスで陥りやすい3つの障壁(認知・理解・実装など)とその対処の視点 - Googleがコンテンツの重要性を加速させた、しかし焦ってはいけない
Googleの変化がコンテンツ戦略に与える影響と、焦らず正しい品質で対応するための指針 - 事例:24時間で「6,312人」の見込み客を集めた手法とは?
実例ベースの集客手法(短期で大量リードを獲得した施策)の構成と学べる実践ノウハウ
- Webコンテンツとはそもそも何か?なぜ大事なのか?
コンテンツの活用を考える前に・準備・
いざコンテンツを作り始める前に押さえておきたいポイント。すぐに作り始めるのではなく、まずこのノウハウを押さえておくと。スムーズに進みます。
-
- 絶対に行うべき「明確なゴール設定」
コンテンツ制作前のゴール設定の作り方と、測定軸を明確にする具体的な考え方。 - コンテンツに力を入れる前に、まず売ろうとしている商品を疑え
コンテンツ施策の前提として商品や提供価値を検証する重要性とチェックポイント - コンテンツの「ネタを出す仕組み」と「型」を先に押さえておく
ネタ発想の方法論と再現性あるコンテンツ生産サイクルの作り方 - まず最初の1センテンスを読ませることに集中する
冒頭一文(ファーストセンテンス)で読み進めさせる技術、構成上の優先点 - 閲覧者を見込み客・初回客にするための「モチベーション」の上げ方
読者の行動を促すためのモチベーション設計と誘導フローの作り方 - 補足:海外のWEBコンテンツ制作界隈はどんな雰囲気なのか?
海外事例やトレンド、採用したい外国の手法と日本への応用ポイント - [Tips]コンテンツを作りたいが何を書くべきか浮かばない時
ネタが浮かばないときの即効テクニックと、現場ベースでネタを作る具体的な手順
- 絶対に行うべき「明確なゴール設定」
コンテンツ作成担当者が持つべきマインドセット
コンテンツの品質を決めるのは、作る人のコンテンツに対する考え方や、アウトプットのイメージです。ここでは実際の海外のコンテンツ作成のプロのノウハウなどを引用しながら持っておきたいマインドセットをご紹介しています。
-
- オフラインの人間関係はとても大事
リアルな人間関係がコンテンツ運営に与える価値と、社内外での情報収集・協働の重要性 - 先入観を取り払って申込み350%アップした事例
先入観を外して改善した実例を通じ、ユーザー視点での仮説検証の進め方 - コンテンツ作成者が持っておきたい「6つの心得」とは
コンテンツ作成者のマインドセット(6項目)と日常で使えるセルフチェック方法 - リサーチが大事!「相手の脳に徹底して入り込むこと」
ターゲットの思考を深掘りするリサーチ手法と、コンテンツ設計 - 「読者の心を揺さぶる」ための8つの自問自答
読者に刺さるための自己チェックリスト(8問)と、制作時の視点の転換ルール - 「構成のパターン化・編集ツール・モチベーション」を見なおしてスピードアップ
編集効率化・テンプレ化の具体策と短時間で回すためのワークフロー改善案 - コンテンツ作成者が絶対避けるべき、13の行動
制作でやりがちな失敗13項目と行うべき行動のまとめ - インバウンドマーケターを目指すときに必要な6つの条件
インバウンドに強い人材像と鍛えるべき6スキルが整理され、育成・採用に使える視点。 - 8秒以内?今の買い手のコンテンツの読み方を押さえて離脱率を下げよう
現代のスキミング傾向に合わせた導線設計と離脱防止の具体テクニック - 企業ブログ・会社ブログの作り方と運用方法の基本
企業ブログ立ち上げから運用・編集体制づくりまでの基本設計 - 「マーケティング的ライティング」ができる人材の有無が企業の情報発信力を決める
社内でのライティング人材育成の重要性と、実際に求められるスキルセットの整理
- オフラインの人間関係はとても大事
タイトル・見出し作成のノウハウ
コンテンツにおいて読み始めてもらうために重要なのはタイトルです。また、ページの中を把握してもらうため、興味を持ってもらうために見出しの構成は重要です。そのポイントについてまとめています。
-
- プロが教える8つの見出しパターンとは
見出し作成で使える8つのパターンと使用場面のヒントが一覧で使えるテンプレ - 見出しづくりはやはり重要
見出しに時間をかけるべき理由と、テストする際の評価観点 - 見出しの作り方に決定打はない、基本を押さえテストを繰返すのが大事
見出しは型×テストの重要性を説き、実務での試し方と改善サイクルが学べます。 - 「ピラミッド型タイトル作成法」でコンテンツのタイトルを決める
ピラミッド構造でタイトルを設計する手法と、実際の作り方のステップ - 動詞と形容詞のバランスを取る!
タイトル文言における動詞/形容詞の効かせ方とバランス調整の具体ルール - 読まれる見出し作りの7Tips(SEOmoz由来)
海外記事を踏まえた見出し最適化の7つの実務Tips - そのキャッチコピー本当に「刺さる?」を判断する、ある1つの質問
キャッチの有効性を瞬時に判定するための問いと基準が得られ、ABテストの指標作り - 年末年始のコンテンツはどう作る?参考にしたい33のタイトル
季節コンテンツ(年末年始)向けの実践的なタイトルアイデア集(33案)と使い方
- プロが教える8つの見出しパターンとは
コンテンツの本文・内容作成のノウハウ
主にテキスト系のコンテンツに関して、本文・内容を作る・ライティングする際に押さえておきたい作成ノウハウをまとめています。
-
- 人を引き付ける「マグネット・コンテンツの作り方」
人を惹きつけるコンテンツ構成(フック・見出し・ペルソナ)の実務手順 - 結果につながらないのは、読み手が納得していないから(説得力の話)
説得力を持たせるための根拠提示や論理構成のコツ、読者を納得させる技法 - 過去の有名コピーを参考にするときに、陥りがちな罠
名作コピーを参考にするときの注意点と、模倣を避けつつ学ぶための考え方。 - 読んでもらえないのは、文章を読むのにパワーがいるから(文字量最適化)
読みやすさ重視で最適な文章量と構造の作り方、短縮テクニック - 読んでもらえないのは、文章を読むのにパワーがいるから(可読性)
可読性向上の具体手法(段落・表現・視覚要素)と読み手負荷を下げる実践テク - ブログ記事をもっと読んでもらうための、画像の効果的な使い方
画像選定・配置・説明文など、記事で画像を効果的に使うための具体的なルール
- 人を引き付ける「マグネット・コンテンツの作り方」
サイト運営の仕方
コンテンツを作ることがゴールではありません。その後それを維持管理し続け、Googleに評価され続ける、読者に価値を提供し続けるために必要な観点についての情報をまとめています。
-
- ソーシャルメディアへの取組み方で悩んだ時に…指針となる10の言葉
SNS運用の心構えと始め方の10原則がまとまっていて、方針決定にすぐ使える指針。 - フォームの最適化は、販売フロー全体を考えないと
フォーム改善を単独ではなく販売フロー全体で見るべき理由と、最適化の考え方。 - あなたのブログはGoogleに嫌われているかも?
Googleの評価観点から見たブログ改善ポイントと、よくあるNG例・改善案 - WEB担当者が見逃しがちな社内の資産とは?
社内に眠る情報資産(人・データ・事例)を発掘してコンテンツ化する手法 - 「リンクベイト」だけでは成約まで結びつかない。見込み客育成が大事。
拡散目的だけの施策では不十分な理由と、見込み客育成につなげる設計の考え方 - Webコンテンツの評価はどう行うべきか?
コンテンツ評価の観点(定量・定性)と評価プロセスの設計方法
- ソーシャルメディアへの取組み方で悩んだ時に…指針となる10の言葉
動画コンテンツ
文章を読むのは苦手でも、動画や音声などなら良いという人は年々増えています。とはいえ、すべてを動画で作れば良いというわけでもなく、適材適所、そして動画自体も抑えるべきポイントがあります。それについてトピックスをまとめています。
-
- Zapposは動画でリンク元が倍増?WEB映像で集客する9つのTIPS
Web動画でトラフィックやリンクを増やすための9つの具体TIPS(事例含む) - Webinarとは?そして開催までに押さえておきたいポイントとは。
ウェビナーの利点・失敗例・準備チェック(7ポイント)など、開催前に知るべき実務知識 - 永遠に消し去るべき、動画マーケティング5つの神話
動画マーケでよくある誤解(神話)と現実的に押さえるべきポイント - 連載「YouTube動画マーケティング・スタートブック」トップ
YouTube動画マーケの入門連載入口。基礎から実践まで体系的に学べるガイド
- Zapposは動画でリンク元が倍増?WEB映像で集客する9つのTIPS
業種別活用事例
業種ごとにコンテンツの活用の仕方は変わってきます。特徴のある業種についておすすめのコンテンツなどをご紹介しています。随時追加していく予定です。
-
- プロフェッショナル(士業やコンサルタント業)のコンテンツ
士業やコンサル業向けのコンテンツ設計例と、専門性を活かすメッセージ作りの具体案 - 製造業のコンテンツ〜商品紹介編
製造業の商品紹介向けコンテンツの作り方、技術情報の伝え方や事例
- プロフェッショナル(士業やコンサルタント業)のコンテンツ
良くある質問
- Q. 戦略的コンテンツ作成とは?
- ただ伝えたいことを書くのではなく、相手の購買行動や知りたいことのステップに合わせて戦略的に作っていくことです。言いたいことを言うのではなく、必要な時に必要なものを伝えるために、また伝えたいことを誤解なく伝えるために、考えながらコンテンツを作ることです。一般的にはコンテンツマーケティングとも言われています。
- Q. まずおさえるべき3ステップは?
- ただ言いたいことを言うのではなく、相手に伝わるように適切にコンテンツを作る、そのイメージを描けるようになることが最も重要です。その上で相手を動かすために何を考慮べきか、実現するにはどんなテクニックや情報を用いればいいのか、が重要です。
- Q. タイトルと本文、優先するなら?
- 優先順位は同じです。伝えたいことから逆算することで、本来タイトルも本文も決まっていきます。伝えたいことが決まった後に考えるべき順番としては、端的にそのコンテンツの価値を象徴するものであるタイトルから考えるのが良いでしょう。
- Q. ネタ出しの仕組みは?
- ネタ出しコンテンツのもとをどうするかについて重要なのは、まず自分の頭の中だけで考えないことです。必ず現場、現実の情報や声をもとにすることを強くお勧めします。そうしないと、脳内のお客様に対してコンテンツを作ることになり、多くの場合それは現実とズレがあり失敗します。
- Q. 5分でできる改善は?
- お客さんの気持ちになってコンテンツを読んでもらい、率直な感想をもらうことが有効です。コンテンツ作成で最も邪魔となるのは、自分の余談や経験などです。お客さんと同じ立場で見ることが最も重要だからです。
- Q. BtoBで効く型は?
- B2BでもB2Cでもコンテンツ作成の基本は変わりません。ただ、BtoBに関しては意思決定者と皆さんが直接話し合う相手が違うことがままあります。そのため、意思決定者のことも考えずに作ることが重要です。
- Q. 動画と記事、どちら先?
- ターゲットによります。動画が効く場合、記事が効く場合はこれという定式はありません。また両方ともあったほうがいいケースもよくあります。ただ動画は後から直すのが大変なので、テストを繰り返すならまずはテキスト系のコンテンツから始めるのが良いでしょう。
- Q. 計測は何を見る?
- コンテンツ系はすぐにコンバージョンに結びつかないことが多いので、安易に問い合わせなどの重いコンバージョンだけで判断しないことが重要です。無料ガイドブックや無料のツールなど小さな金番状を設けて、そこに対する誘導度やコンテンツ自体の読料率などをヒートマップで見るなどがスタート地点としては良いと思います。
- Q. 社内体制の最小構成は?
- 重要なのはコンテンツを作るのは非常に時間がかかるということです。そのため、安易に自分一人だけで作ろうとすると、1ヶ月に1本2本という少ない数が限界で、どんなに良いコンテンツでも効果があまり出ないという結果になりがちです。直接的な担当者が1人だとしても、社内で情報源となる人やレビューを頼める人など、手伝ってくれる人を最低でも2、3人は作っておきましょう。また、上司に重要度を説明した上で、適切なバックアップがもらえるようにすることも重要です。